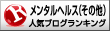【幼児吃音10人に1人 国立リハセンター「過去の研究より多い」 】
職場で小さい「お子さま」たちと
関わることの多いからか目にとまった記事。
吃音は今も原因が解明されていない症状。
難発(………あのね。のように初めの音がなかなか出ない)
連発(あ、あ、あ、あのね。)
伸発(あーーのね。) のいずれか、あるいは複数が会話中にみられます。
現在のところ、吃音症状に対応する
医学的な治療法は確立されていません。
そのため、
成人期になっても吃音症状が出る場合は
吃音とうまく付き合っていく方法を考えていくそうです。
記事にもあるように幼児期に吃音症状があっても
7割ほどが成長に伴って軽減・解消されます。
ただ、言葉を覚え話していく幼児期にあって
吃音症状が出ると本人も家族もとても悩みます。
記事には
保育者向けのガイドラインについても
書かれていました。
本人や家族が
幼児期に1人悩まないように関係者・関係機関が
できることを少しずつ増やしていく必要性を感じました。
今まで吃音症状が出るお子さんとも
関わってきましたが
大切なのは
「その子らしさを失わせない」ことだと考えています。
発吃を抑えようと保護者が躍起になったがために
お子さんが話すのを嫌いになり
それが友達関係にまで影響した、という例があります。
これでは全く逆効果。
発吃があってもその子の人柄には
何のマイナスの影響もないのですから
たくさんお話しして周りと関わると良いですし、
保護者も周りの方も吃音を気にせずに受け止める。
そのくらいの大らかさがあった方が
「その子らしさ」が出て良いと考えています。
今回は吃音のお話でしたが、
吃音だけではなく「大らかさのある環境・社会」が
人を育てるというのは忘れずにおきたいところですね。