




































(四) 弥勒の1√2 ① Mirokuno1√2
人は自分の中から「 迷い 」を撃退することほど難しいことはない。比江島修治も思いあたる迷走が大いにある。しかしそんな修治は雨田博士より「現代」から「古今」への転換をはかることこそを学んだのだった。
だが博士ほどの柔軟な志をもった者でも、人生半ばにしてそれでも失望や痛痒を感じたり、天望から見放されてみなければ、この方式による刺激を実感できないことだったのかもしれない。それほど「無」を読むということは難しい。古今へと還る姿勢をそれなりに新鮮にしつづけることは至難なことだ。そこには修治が「 無為自然 」を感じるという作業が待っていた。しかしそれが一筋縄でいくはずがない。
「 やがて朝露の滴る窓ガラスの上に、秋子の白く細い指先が手短な平和という文字を描き、手招きで誘う夢をよくみるようになった。戦後日本の資本主義から生まれた、あの鳩は一体どうしたというのか・・・・・ 」
と、未だどうしても噛砕けなく、以来、神妙なその潮騒の揺らぎに修治の資本主義は狂おしく曵かれ続けている。
いつも秋子の伍円笛(ごえんぶえ)の音色と逢う度に、雨田虎哉が「 焔の帆(ほのほのほ) 」の赤い火の船に載せられたのと同じごとく修治は、赤鉛筆でラインを引いた学生当時の、すっかり変色した古典の教科書をいま怖るおそる開いて、古今へと眼を遠くさせられているように、深い時間に曳き戻されてはまるで赤い紅葉が降り落ちた跡が、赤黒い古細菌の化石のようになっているかのような錯覚を抱いている。






「 志があれば利刃のごとく百邪を払うことができる・・・・・ 」
と、阿部家の家伝ではそういうが、そうそう魂魄になどなれそうにもない修治は、たゞ宮古島へと目指し那覇空港を離陸した。
雨田博士が還ろうとした奈良は日本仏教の萌芽の土地であるが、その仏教は過去・現在・未来の三世にわたって報応報恩を説く。雨田博士はそのころの日本仏教は十分な理論や構想をもてなかったのに、後にそれを果たしたのは浄土教や禅ではなかったのかという、修治が今機上において考えるのは、その指摘である。修治は何と5年前に、ようやくこの指摘を新鮮に感じたのだった。
西方浄土というが、宮古島は那覇よりさらに西になる。修治はさらにその西方に向かおうとした。

「 すでに日本人は浄土観すら失っている・・・・・。それはそうだろう・・・・・ 」
兜率天にいる弥勒は、未来のいつの日にか人間の住む閻浮提(えんぶだい)に降りてくることになっている。これを「下生」(げしょう)という。降りてくるといっても、人間が8万歳になったときに下生するというのだから、気が遠くなるほどの先である。これがいつしか56億7千万年後の下生ということになった。
「 シッダッタの入滅後56億7千万年後の未来に姿を現れて、多くの人々を救済するとされる・・・・・ 」
だから弥勒は未来仏なのである。
沖縄および八重山一帯の島々では「 ミルク神 」とも「 ミルクさん 」とも呼び、弥勒信仰が盛んである。祭りでは、笑顔のミルク仮面をつけたミルク神が歩き回る。これは弥勒菩薩の化身とされた布袋との関係がある。
修治はそのミルクの顔を泛かべた。
「 そもそも沖縄においては、東方の海上にあって神々が住む( ニライカナイ )という土地があり、神々がそこから地上を訪れて五穀豊穣をもたらすという思想があった。この思想にミロク信仰がとりいれられ、ミロクは年に一度、東方の海上から五穀の種を積みミルク世をのせた神船に乗ってやってきて豊穣をもたらす来訪神「ミルク」であるという信仰がこの地方に成立した・・・・・ 」
沖縄で見られるそのミロク仮面は布袋様の顔をしており、日本の仏像にみられる弥勒仏とは全くかけはなれた容姿をしている。これは、沖縄のミロクが、日本経由ではなく、布袋和尚を弥勒菩薩の化生と考える中国大陸南部のミロク信仰にルーツをもつためである。布袋和尚は実在の人物と考えられ、唐末期、宋、元、元末期の4人の僧が布袋和尚とされている。
彼(ら)は大きな腹をし、大きな布袋をかついで杖をつき、各地を放浪したといわれる。
12世紀ごろの禅宗でこの布袋を弥勒の化身とする信仰が始まり、この「 布袋=弥勒 」と考える信仰は中国南部からインドシナ半島にかけて広まる中で、それが八重山へと伝播することになったようだ。


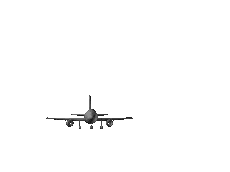




弥勒の下生は56億7千万年後とされているが、この気の遠くなる年数は、弥勒の兜卒天での寿命が4000年であり、兜卒天の1日は地上の400年に匹敵するという説から、下生までに4000×400×12×30=5億7600万年かかるという計算に由来する。
「 しかし、後代になって5億7600万年が、56億7000万年に入れ替わったのだ・・・・・ 」
これは「遠い未来」への比喩であろうから、通説としては面白いが、たとえば浄土宗系の『無量寿経』には、阿弥陀仏の本願を後世の苦悩の衆生に説き聞かせるようにと、釈迦牟尼仏から弥勒菩薩に付属され、この未来仏の出現する時代は厳密には定かではない。仏教の中に未来仏としての弥勒菩薩が登場するのはかなり早く、すでに『阿含経』に記述が見える。この未来仏の概念は過去七仏から発展して生まれたものと考えられている。
「 この弥勒信仰には、上生信仰とともに、下生信仰も存在し、中国においては、こちらの信仰の方が流行した 」
雨田博士は、そう語っていた。
下生信仰とは、弥勒菩薩の兜率天に上生を願う上生信仰に対し、弥勒如来の下生が56億7千万年の未来ではなく現に「 今、現世に 」なされるからそれに備えなければならないという信仰である。
浄土信仰に類した上生信仰に対して、下生信仰の方は、弥勒下生に合わせて現世を変革しなければならないという終末論、救世主待望論的な要素が強いのだ。そのため、反体制の集団に利用される、あるいは、下生信仰の集団が反体制化する、という例が、各時代に数多く見られた。北魏の大乗の乱や、北宋・南宋・元・明・清の白蓮教が、その代表である。
日本でも戦国時代に、弥勒仏がこの世に出現するという信仰が流行し、ユートピアである「 弥勒仏の世 」の現世への出現が期待された。これは一種のメシアニズムであるが、弥勒を穀霊とし、弥勒の世を稲の豊熟した平和な世界であるとする農耕民族的観念が強い。この観念を軸とし、東方海上から弥勒船の到来するという信仰が、弥勒踊りなどの形で太平洋沿岸部に展開した。
そして江戸期には富士信仰とも融合し、元禄年間に富士講の行者、食行身禄が活動している。また百姓一揆、特に世直し一揆の中に、弥勒思想の強い影響がみうけられる。
「 奈良県当麻寺金堂本尊の弥勒仏坐像は、7世紀後半にさかのぼる作で、日本最古の塑像(そぞう)と言われている・・・・・! 」
塑像(そぞう)は、塑造によって作成した彫像などの立体造形のことだ。紙粘土による作品なども含まれるが、鋳造作品の原型作りは通常、塑造の手法を使って行われる。日本では、塑像の作例は奈良時代に集中しており、木彫が彫刻界の主流となった平安時代以降(おおむね9世紀以降)の塑像の作例はまれである。
このために雨田博士は、奈良・当麻寺金堂の塑像(奈良時代、国宝)を訪れたのだ。

これは当麻寺金堂の本尊(像高219.7センチメートル)である。
如来形の弥勒像で、仏壇上に残る痕跡から、元は両脇侍像をしたがえた三尊形式であったと推定される。像は箱型の裳懸座(宣字座)上に結跏趺坐し、台座の前面に裳裾を広げる。印相は如来像に通有の施無畏与願印(右手は掌を正面にして挙げ、左手は掌を上にして膝上に置く)だが、右腕の前腕部の半ばから先と左手首から先は木製の後補で、当初からこの印相であったかどうかは定かでない。
また、この金堂本尊の名称を「 弥勒 」とするのも、文献上は鎌倉時代の『 建久御巡礼記 』が初見で、当初から弥勒像として造像されたという確証はない。両膝部、胴部、頭部の3つのブロックを積み重ねたような造形は中国・隋代やその影響を受けた新羅の仏像彫刻、中でも新羅の軍威石窟三尊仏の中尊との様式的類似が指摘される。さらに球形を呈する頭部の造形には天武天皇14年(685年)完成の興福寺仏頭(旧山田寺講堂本尊)との類似ともみなされる。
本像は塑像(粘土製の彫像)であるが、表面には布貼りをし、錆漆を塗った上に金箔を張っている。これは金堂は治承4年(1180年)の兵火で被害を受けており、また像表面の金箔は治承の兵火以降のものと推察される。像本体と台座は密着しており、本体、台座ともに内部構造の詳細は明らかでない。ともかくも現状は台座の四隅に木製の隅柱があり、台座上下の框(かまち)、反花(かえりばな)なども木製のものが貼り付けられているが、これらは治承の兵火以後のもので、当初の台座表面はすべて塑土で仕上げていた。
「 あの像本体は、両手部分が木製の後補であるほか、左腕、両膝などの衣文に漆喰状のもので修理した部分がある・・・・・ 」
と、雨田博士は指摘していた。
たしかに明治期の修理でも胸部などの損傷箇所に大幅な修理が行われている。そして螺髪は当初は塑造であったが、木製の後補のものに代わり、それも大部分脱落している。光背は平安時代後期か鎌倉時代初期頃の木製である。
博士が言うように、本像は後世の補修部分が多いが、日本に現存する最古の塑像として貴重なのだ。
「 たしか宮古島空港にYS-11型機が就航したのは昭和43年であったはずだ・・・・・ 」
そう思い宮古島へと機影が下降しはじめると、眼の中で七色の日傘を開いた比江島修治は、そこにミルク神と、当麻寺の弥勒塑像、そしてニコライ・A・ネフスキーの姿が重なっていた。


絶妙な機能と形態とを獲得した異空間プロセスが、じつに意外なしくみによって泛上することがある。
「 小生の脳は、ときおり、水分子と熱対流によってそうなってしまうのだ・・・・・! 」
それはMRIがもたらす水分子画像のシンフォニーにも似ているが、阿部家に伝わる「 陰陽寮解体伝書 」には、人間および小動物の脳が非線形の複雑系であることを解き証かすいくつもの言及が交差するのだ。
この時、阿部丸彦の脳内の時空間は反時計回りとなり、心霊は遊離して異空間を翔けめぐる。



「 突如、想定外の角度から脳細胞のパラダイムがひっくり返される、そんな感触に浸されるのだ・・・・・! 」
すると回転中、まことに心地よい加速感がある。が、この加速力はどちらかというと科学の構築というより工学的な快感なのだ。このとき丸彦を止めたボルトがパラパラと外れ、落下する生体は確率、自己形成、イジング、ユニバーサリティ、相転移、カオス、可塑性といった概念を反射的に選び抜いて、一気に不思議な「 億脳を空にさせて開放させる方程式の演算空間 」に向かって行く。そして丸彦は、その異空間を細胞が次々に移動してグリア細胞のラジアル繊維を伝わってくるのであろうことを体感し実感するのである。このとき新しい非線形的な自己形成( self organization )が起こっていた。


「 あのときの秋子の絵葉書、それを見せられたとき雨田博士は焔の帆に載せられたのだ。そして博士は大正13年まで一瞬に引き戻された。その差出に( 佐保の菊と寅 )、宛先は( Gershwin・賀修院 )とあった。何ともそれは博士にとってたしかに母と僕ではないか。すると僕は4歳、これを鵜のみにすると、僕である博士は母と京都に来た。そういうことになる。そして京都に居たとすれば、絵柄は橋姫、そうなると母菊乃と、紙で造られた夢の浮橋を二人渡った可能性がある。兎に角に母の絵葉書は秋子に拾われていたのだ・・・・・! 」
雨田博士の回顧帳を、丸彦は読みながらフッと嫌(いや)な閃(ひらめ)きを覚えた。
博士と清原香織が奈良を訪ねるこの物語が、佳境を過ぎて閉じられるころに、誰かが水甕(みずがめ)に溺死(できし)するのではと、そして丸彦もまた祖の吾輩と同じように、その甕に落ちて鐘の音を聞くのではなかろうかと、そう閃くとしだいに脱力感を感じつつ、冷やされた肝(きも)が脱水されてしまうと、やがて消えるごとく全身がふわりと怪しく嫌に揺れたのだ。
「 もし、そうやとしたら、そないな変死、できしまへン。死ぬいうのやったらそ~ら六道の上等なんがえゝに決まっとる。こゝで踏ん張らなあかンのやないか。そない思うたんや。小生は吾輩のように、じィ~とは、しとられん・・・・・! 」
そう察知した丸彦は、音羽六号の翼を借りて上空より何処へ疎開しようかと世の中の空甕(からかめ)を睨みつけた。
すると世の中の甕とは、全ての甕が空っぽではないか。そこでよくよく考えてみると、人間とはその空からの大甕の中で零(む)を抱きながら浮遊して暮らす動物なのだ。
「 小生は、吾輩の轍(てつ)は踏みとうない。落伍などしィへん。小生は転んでも八起きしたるわ! 」
と、そのとき丸彦は雨田博士の今際の眼、その焔の帆を熾(おこ)しては、産まれ故国の六道の辻をジッと見渡した。すると判然としなかった一切が鮮やかに泛かんできた。漱石先生は「 自己本位 」で行こうと思った時、心が軽くなり、今までにない学問の使命感に燃えたのだ。「 その時私の不安は全く消えました 」と『 私の個人主義 』にそう書き記す。そして自我と自我との対立に悩みながら、心理学や禅を研究しながら、創作を続けていたが、漱石先生は、大正四年『 硝子戸の中 』連載の頃、真に偉大なものに気がついたと思われる。『 道草 』五十七章に「 金の力で支配出来ない真に偉大なものが彼の眼にはいって来るにはまだ大分間があった 」と書いているではないか。また大正四年の『断片』に「大我」と「技巧」「絶対の境地」などの考察があり、禅の追求するところと同じところを考えていたことが分かるのだ。その漱石先生が、偉大なものに気がついてから、自分の過去を振り返って書いたのが『 道草 』であると丸彦には思われる。そしてさらに「 不自然は自然には勝てないのである。技巧は天に負けるのである。策略として最も効力あるものが到底実行できないものだとすると、つまり策略は役に立たないといふ事になる。自然に任せて置くがいいといふ方針が最上だといふ事に帰着する 」という言葉は大正五年『明暗』を書いている頃にそう先生は言われた。これは無私(無我)にて動くとき、天、おおいなる自然の意志の働きが出るということであろう。これは禅に通じる。
まさしくこれこそが「 則天去私 」なのだ。
漱石先生は「 こころ 」を探求して、晩年になって、思想的には「 こころ 」の大きなものに気がついたが、晩年にして「 体得 」せねばならぬと志し、ついにその中途で死んだのである。だから先生は祖の吾輩を水龜(みずがめ)に落とし水死体のままに放置しているのだ。これでは吾輩がまさしく鮮やかに則天去私なのである。その水甕を泛かべると丸彦はそっと合掌した。


「 大正13年といえば、皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)と良子女王(後の香淳皇后)ご成婚・・・・・ 」
雨田虎哉の母菊乃はこの祝賀に馳せて虎の手を引き泉涌寺詣でに出かけたのだ。
そしていつもの道草の帰路、その日ばかりは洛中へと足を運び平安神宮を詣でた後、三条から四条へとそゞろし、河原町の京紙屋をのぞいては、ふと認めた宇治十帖の絵葉書に、さては、と祝賀にはとても姦(かしまし)くとばかりに、奇抜あるいは、さも斬新な発想を泛かばせた。眼の橋姫に鍵盤を叩かせてラプソディ・イン・ブルー( Rhapsody in Blue )の曲を奏でさせたのだ。
そして宛先は何と大胆に亜米利加:Americaの「 Gershwin 賀修院 」、差出は「 佐保の菊と寅 」とだけ書いた。ラプソディ・イン・ブルーはジョージ・ガーシュウィンが作曲したピアノ曲。賀修院とはその彼の名にちなむ。何ともハイカラでモダンな発想であった。しかし、この一枚の絵葉書を菊乃がどう投函したのは不詳である。


「 これでは65年間、博士はさも雲水のごとく托鉢の旅でもしたくなる・・・・・ 」
そう妙な感想を丸彦が抱いたとき、丸彦には「 雉の、ほろうち 」が閃いた。それは雨田博士が八坂神社から帰ると裏山の藪の茂みをじっと見ていた、その、ほろうちである。あのとき雨田虎哉はそして、眼をそうさせたまゝ脳裏には遠い昔の、ある弔いの光景を泛かばせていた。
「 寒さが温んだら、もう一度、瓜生山の頂に上がろう・・・・・ 」
奈良から戻った日にそう思い雨田虎哉は今日もまた同じようにそう思った。
M・モンテネグロに会って以来、そう思い続けてはいたのだが、老いた足取りがなかなかそうはさせないでいた。裏山に現れた雉の後影を見つめながら虎哉は「 やはり瓜生山か・・・・・ 」と思ったのだ。
羽をバタつかせてケンケーンと鳴く。これを雉の、ほろうちという。春を告げる声でもある。早春の草原や果樹園の茂みなどで耳にする。縄張りの主張やメスへのアピールだ。4月ごろ繁殖の季節を迎えると、この時期の雉は、赤いトサカが大きくなり体も大きく見えるようになる。そして行動をより大胆にするようになる。虎哉が想う雉は、やはりどうしても瓜生山の雉なのだ。

雨田博士への見舞いの来客が去れば応接の四脚はポッカリと穴を開けたように、夕暮れの陰であるかにそう見えた。
「 アメノワカヒコの妻のシタテルヒメの泣く声が、風と共に高天原まで届いた。・・・・・そして、高天原にいるアメノワカヒコの父のアマツクニタマとアメノワカヒコの妻子達が聞いて、地上に降ってきて泣き悲しんだ。あゝやはり、これは、あの、ほろうち、ではないか! 」
そう思えると、丸彦は応接の椅子に腰をストンと落として、もう一度阿部秋子の話を泛かべたてみた。
「 ねっ、どうして雨ェ降らないんやろ?・・・・・ 」
と、香織から問われ、「ふーん、どうしてなんやろね。・・・・・ 」と、秋子は答えなく応えた。
そして秋子はまことに辻褄の合わない言葉で、子供は大人社会を選べない。多くの場合、希望と化した予測は裏切られることになる。だが親としては、そこから子供を持つということの、そして子供を育てるということの喜びをいだく不思議さが始まる。意外な個性を持った子が育ち、驚かされることになるのだ、と香織に話したのだ。
これを聴いていた丸彦には、降雨と子供との因果関係に整合性もなく妙な不可思議さを覚えた。
しかし思い出した「 10月の雨 」が阿部秋子をそうあおり立てたようだ。
神に摂理されながら完成に至らぬ「存在しない雨」というものが、この世には無数に存在するのかも知れない。もしそうであれば、秋子の煽(あお)られた、この挫折にも等しい裏面史は、しばしば現実に存在する降り注ぐ雨より刺激的なのだ。だが、あらかじめ自らが挫折することで「 雨を見ること 」を感じさせる時間が現実に存在していることを、丸彦は一体どう考えるべきか。そう想われると虎哉もまた、干(ひ)からびた地に立たされて熱い太陽を身に浴びるようであったのだ。
「 モロー教授は、それをPluieシャワーと名付けました・・・・・ 」
と、秋子から聴かされると、雨田博士はシモーヌ・ヴェイユが『 重力と恩寵 』のなかで「 メタクシュ 」というきらきらとしたギリシア語を何度もつかっていたのを思い出した。メタクシュとは「 中間だけにあるもの 」という意味である。きっと雨にも重力と恩寵が関与しているのであろう。雨は重力とともに地上に落ちてくるが、その前にはいっとき重力に逆らって天の恩寵とともに空中で中間結晶化というサーカスをやってのけているはずなのだ。きっとモロー教授とは、その「 いっとき 」を追いつゞける人だったのだ。
そう思えると、雨田虎哉は錯覚の赤い雨をふと抱かされていた。

「 何かと縮こまりがちで、虫酸が走りそうなこんな時代に、この赤い雨とは・・・・・! 」
と、長い沈黙の中で、ふと虎哉はある種のひらめきを覚えた。その眼の中に、こゝがじつに奇遇なのだが、その赤い雨を見せらたとき、虎哉はふと涙すら覚えた。おもむろにステッキを突きたて、ふっと身体を起こすと、もう曲がらなくなった膝をあえかに固々しく曳き摩りながら静かに香織の肩にとまる鳥のようにして我家である八瀬の山荘へと向かった。その眼には日本で最も古い「記紀」が泛かんでいた。
そして静かに眼を閉じたのだ。
「 そこには随筆ひなぶりを遺した清原茂女の姿がある。その娘の文代は古湯温泉へ養女に差し出されては花雪という芸子となる。花雪はその後、京都上七軒に上がり、やがて花背の疎開先にて労咳で他界する。この花雪の子が、祇園置屋の佳都子であった。その佳都子は芸子時代に阿部幸次郎との間に子女をなした。幸次郎とは阿部秋一郎の二男で富造の兄、すでに病で他界する。さらにその後、佳都子は置屋を営むようになると、その子女を縁戚の清原増二郎に養女として出した。その子女が香織なのだ。そうか、香織の母は祇園の佳都子だったのか。すると阿部秋子と清原香織は義理にしろ、又またとこの姉妹関係!。そうか、それであのとき芹生の千賀子は香織のことを(雉の子や)と呼んだのか。その香織は赤い勾玉まがたまを持つ! 」
こうして眼を閉じた虎哉は、阿部和歌子がニューヨークへと旅立つ朝、狸谷から一乗寺駅へと向かう姿を凹凸詩仙堂のモノ陰より密かに見届けた光景を想い起こした。
「 あと八年は元気でのうてはあかんのやさかいに・・・・・ 」
どうやら老いて身は細くとも気丈夫なようだ。和歌子はそういって凹凸詩仙堂の角から秋子の守る阿部家の屋根を振り返りつゝ、その眼には阿部清四郎の若き面影を湛えていた。虎哉にはしだいにそう思われてきた。千賀子の暮らす芹生には人知れず雉の鳴女の石塚がある。
「 二人の間には阿部富造には知られてはならない秘め事があったようだ・・・・・ 」
和歌子は、アメリカより帰国後に、高野山に上がり清四郎の墓参を果たして洛北の山端に夏の気運を運ぼうとした。それを阿部家の長としての責務であったとするが、虎哉はそういう和歌子の胸の裡を秋子から聞かされている。
しかし秋子の出生は不詳だ。しかも秋子が出生の前に和歌子は渡米している。その渡米後の足跡が不明なのだ。したがってこの和歌子と清四郎の蜜月は憚(はばか)りとして、虎哉が密かに鬼籍にて預かることにした。
「 80の老体で一人渡米など無謀とも思えるが、しかし和歌子も陰陽寮の女子である。また法衣の声の行き届く山端の狸谷に生まれたのであるから、成し遂げて満たさねばならぬ何事かの腹づもりはあったろう。それは、山端に育った女の分別として、蟠(わだか)まる一つや二つの心障りな失念を最期にふりしぼる決着の気構えであった。したがって渡米に際し未だ生きるのだと叩く減らず口は持つ。何とも晴れやかな頬笑みであった・・・・・ 」
満願への門出なのだ。和歌子の気丈さは、すでにその出で立つ姿に現れていた。
まず墨染めに再色し直したモンペ仕立ての京友禅が、達観した女僧さながらに見える。あるいは、その頭上に薪(たきぎ)の束でも載せれば、モダンな大原女(おはらめ)がはんなりと歩くようでもある。まさに大原女のその風俗に似た和歌子の風姿は、島田髷(しまだまげ)に手拭を被り、鉄漿(ふしかね)をつけ、紺の筒袖で白はばきを前で合わせ、二本鼻緒の草鞋(わらじ)を履いている。阿部和歌子はこのスタイルで京都から飛び出すように一乗寺駅へと向かった。
虎哉が最期に眼に刻み残したそんな度胸の気丈さは80歳にして、若返り娘の悪戯(てんご)でも見るかの溌剌(はつらつ)とした趣であった。そんな和歌子の眼に、かって太平洋戦争に突入する直前、渡米しようとした龍田丸の豪華客船に、同じくロスまで渡航しようとする雨田虎哉の実弟定信が乗船していたことなど、和歌子は知る由もなく泛かぶはずもなかったであろう。

「 小生は、じっと帰国後の和歌子の姿を見つゞけている・・・・・ 」
秋子は狸谷不動院から瓜生山へと上がる坂道の途中に狸坂多聞院を施した。
日本では四天王の一尊として造像安置する場合は「 多聞天(たもんてん)」、独尊像として造像安置する場合は「 毘沙門天(びしゃもんてん) 」と呼ぶのが通例である。その多聞天は、仏の住む世界を支える須弥山(しゅみせん)の北に住むとされる。また夜叉(やしゃ)や羅刹(らせつ)といった鬼神を配下とする。この坂道を清原香織は毎日のように上がってくる。
香織がそうしつゞけるのは、雨田博士の永訣の朝、秋子がこの多聞院の庭先で朝の名乗りの篠笛を吹き、それが博士の風葬のごとく感じられたからであった。その香織曰(いわ)く、この坂を、盆暗狸坂(ぼんくらたぬきざか)という。秋子の朝に名乗る笛が終わると、次に香織は雉笛きじを吹いた。
西洋に黄金比があるが、これではなく、日本人が古くから美しいとした比率に白銀しらがね比の1対√2という音律が大和(やまと)にはある。京都の銀閣寺や東寺、奈良法隆寺の五重塔、あるいは千利休の茶室もこの白銀比を使用するのだが、1対√2(1・4)対1の、「1」を「5」に変えると「5・7・5」となる。この数学は日本人が紡ぎ出した言葉(ことのは)であり絵巻物語なのだ。陰陽寮博士の阿部一族が連綿と享け継ぎてきた陰陽五行、天文の音羽、あらゆる笛の旋律、子子(ねこ)の暗譜、そのすべてがこの白銀比である。
雨田博士はこの白銀比を応用して弥勒菩薩を目覚めさせようとした。











奈良 当麻寺









