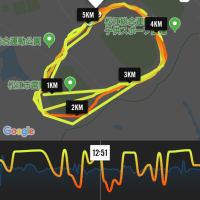年金記録2%に食い違い 社保庁、窓口相談で(共同通信) - goo ニュース
10月24日に、政府は、年金が幾ら貰えるか分かりにくいことが、年金不信につながり保険料未納問題に繋がっているとして、年金見込額等を知らせる「ねんきん定期便」を2007年12月以降から順次導入を検討していると報道後に!・・・社会保険庁が年金の記録漏れが発覚!!!8月21日から一ヶ月間で加入者が窓口で自分の年金記録を確認した件数は12万3952件有ったようです。その内の約20%の2万4145件で、年金保険料を納めたにもかかわらず社会保険庁の記録に反映されないことが判明しました。
記録漏れの半数は転職などで複数の年金手帳を持っている人だそうです。また、結婚で姓が変わった人などが反映されなかったり・・・。同じ年金でも確定拠出年金(401K)は自己責任で運用しますので、元本割れも有るわけですが、拠出したお金はきちっと管理されています。余りにも社会保険庁のずさんな管理には、驚かされます。
では、現在豊かな老後生活を謳歌していると言われる年金生活者の方々の平均金額は?ソフトバンクグループのSBIグループ代表・北尾吉孝氏総監修で「2006年度版 図解 自分に最適な資産運用が一目でわかる本」の中の年金編、国民年金月々3~5万円台、厚生年金月々11~15万円台、共済年金月々15~19万円台と載っています(一人分)。2004年総務省の60歳以上の家計調査によると、標準的な生活費は約25万円強と算出しているそうです。平均から見れば全ての人が不足します。豊かな老後からはかけ離れています。
私も、今春50歳に成りましたので、8月に社会保険事務所に自分の年金の「制度共通年金見込額紹介」を申請し、将来の年金受給予想額を見て愕然としました。私の場合(厚生年金加入期間は307ヶ月)は、62歳~65歳まで報酬比例部分が有り65歳から基礎年金がプラスされ約126万円に成ります。また、38ヶ月努めた保険会社の厚生年金基金が62歳から終身で年約10万円強ですから、二つ合わせると約136万円で、月に直すと約11万3千円で家内の年金をプラスしても20万円にも成りませんので、一生働かなければ生活できません。
以前、年金シミュレーションソフトで自分の年期を試算したときは、17万円ぐらい有ったような記がしましたが・・・そこで、問題になるのが平均標準報酬月額です。この平均・・・月額が変われば当然年金額は変化します。私の公的年金額から逆算すると、25年余りの厚生年金時代の平均が20万程度???と成るはずです。殆どの人が、過去の給料明細書など処分していると思いますがので、計画されています「ねんきん定期便」には幾ら払込で幾ら貰えるかだけでなく、毎年の計算基礎となる標準報酬月額も明示して欲しいものです。そこの大事な部分の改ざんまではなされていないと思いますが・・・。
私の年金は現在この様な計算式から計算されています。
《参考》
老齢厚生年金 男性-昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
この年代の方は、生年月日により60歳から64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が支給開始されます。特別支給の老齢厚生年金は、65歳以後の老齢基礎年金に相当する定額部分と、報酬比例部分から構成されますが、この年代の方には定額部分は支給されません。計算式は以下の通りです。
a、報酬比例部分
*報酬比例部分は、平成15年度の総報酬制導入に伴い、平成15年3月以前と平成15年4月以降をそれぞれ別々に計算し、これらを合算した額に1.031×0.988を乗じて得た額が年金額となります。
報酬比例部分 = ((1) + (2)) × 物価スライド率
(1) = 平均標準報酬月額 × 乗率 ( 7.5 /1,000) × 平成15年3月以前の厚生年金の加入月数
(2) = 平均標準報酬額 × 乗率 (5.769 /1,000) × 平成15年4月以降の厚生年金の加入月数
b、加給年金
定額(配偶者に対する加給年金 : 397,300円)
c、老齢厚生年金
a.と同じ
d、老齢基礎年金
老齢基礎年金 = 794,500円 × (保険料を納付した月数 + 保険料全額免除月数 × 1/3 + 保険料半額免除月数 × 2/3) / 480
老齢基礎年金も老齢厚生年金も加入期間が長ければ、それだけ年金額も多くなります。
ただし、老齢基礎年金には上限額(794,500円)が設けられています。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達した後は支給されません。
(65歳から配偶者が自分の老齢基礎年金をもらうことができるからです。配偶者の老齢基礎年金には、加給年金に代わる振替加算が加算されることもあります。)
また、「配偶者の厚生年金加入期間20年未満、かつ年収850万円未満」でも、加給年金が支給されないケースもあります。加給年金については、さらに細かい支給要件等があります。
※ 計算結果は概算ですので、実際とは異なる場合があります。


★画像は著作権、肖像権を侵害するものではありません。
★画像に著作権、肖像権に申し出があれば即時、削除します。
 | 2006年度版 図解 自分に最適な資産運用が一目でわかる本高橋書店このアイテムの詳細を見る |
10月24日に、政府は、年金が幾ら貰えるか分かりにくいことが、年金不信につながり保険料未納問題に繋がっているとして、年金見込額等を知らせる「ねんきん定期便」を2007年12月以降から順次導入を検討していると報道後に!・・・社会保険庁が年金の記録漏れが発覚!!!8月21日から一ヶ月間で加入者が窓口で自分の年金記録を確認した件数は12万3952件有ったようです。その内の約20%の2万4145件で、年金保険料を納めたにもかかわらず社会保険庁の記録に反映されないことが判明しました。
記録漏れの半数は転職などで複数の年金手帳を持っている人だそうです。また、結婚で姓が変わった人などが反映されなかったり・・・。同じ年金でも確定拠出年金(401K)は自己責任で運用しますので、元本割れも有るわけですが、拠出したお金はきちっと管理されています。余りにも社会保険庁のずさんな管理には、驚かされます。
では、現在豊かな老後生活を謳歌していると言われる年金生活者の方々の平均金額は?ソフトバンクグループのSBIグループ代表・北尾吉孝氏総監修で「2006年度版 図解 自分に最適な資産運用が一目でわかる本」の中の年金編、国民年金月々3~5万円台、厚生年金月々11~15万円台、共済年金月々15~19万円台と載っています(一人分)。2004年総務省の60歳以上の家計調査によると、標準的な生活費は約25万円強と算出しているそうです。平均から見れば全ての人が不足します。豊かな老後からはかけ離れています。
私も、今春50歳に成りましたので、8月に社会保険事務所に自分の年金の「制度共通年金見込額紹介」を申請し、将来の年金受給予想額を見て愕然としました。私の場合(厚生年金加入期間は307ヶ月)は、62歳~65歳まで報酬比例部分が有り65歳から基礎年金がプラスされ約126万円に成ります。また、38ヶ月努めた保険会社の厚生年金基金が62歳から終身で年約10万円強ですから、二つ合わせると約136万円で、月に直すと約11万3千円で家内の年金をプラスしても20万円にも成りませんので、一生働かなければ生活できません。
以前、年金シミュレーションソフトで自分の年期を試算したときは、17万円ぐらい有ったような記がしましたが・・・そこで、問題になるのが平均標準報酬月額です。この平均・・・月額が変われば当然年金額は変化します。私の公的年金額から逆算すると、25年余りの厚生年金時代の平均が20万程度???と成るはずです。殆どの人が、過去の給料明細書など処分していると思いますがので、計画されています「ねんきん定期便」には幾ら払込で幾ら貰えるかだけでなく、毎年の計算基礎となる標準報酬月額も明示して欲しいものです。そこの大事な部分の改ざんまではなされていないと思いますが・・・。
私の年金は現在この様な計算式から計算されています。
《参考》
老齢厚生年金 男性-昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
この年代の方は、生年月日により60歳から64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が支給開始されます。特別支給の老齢厚生年金は、65歳以後の老齢基礎年金に相当する定額部分と、報酬比例部分から構成されますが、この年代の方には定額部分は支給されません。計算式は以下の通りです。
a、報酬比例部分
*報酬比例部分は、平成15年度の総報酬制導入に伴い、平成15年3月以前と平成15年4月以降をそれぞれ別々に計算し、これらを合算した額に1.031×0.988を乗じて得た額が年金額となります。
報酬比例部分 = ((1) + (2)) × 物価スライド率
(1) = 平均標準報酬月額 × 乗率 ( 7.5 /1,000) × 平成15年3月以前の厚生年金の加入月数
(2) = 平均標準報酬額 × 乗率 (5.769 /1,000) × 平成15年4月以降の厚生年金の加入月数
b、加給年金
定額(配偶者に対する加給年金 : 397,300円)
c、老齢厚生年金
a.と同じ
d、老齢基礎年金
老齢基礎年金 = 794,500円 × (保険料を納付した月数 + 保険料全額免除月数 × 1/3 + 保険料半額免除月数 × 2/3) / 480
老齢基礎年金も老齢厚生年金も加入期間が長ければ、それだけ年金額も多くなります。
ただし、老齢基礎年金には上限額(794,500円)が設けられています。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達した後は支給されません。
(65歳から配偶者が自分の老齢基礎年金をもらうことができるからです。配偶者の老齢基礎年金には、加給年金に代わる振替加算が加算されることもあります。)
また、「配偶者の厚生年金加入期間20年未満、かつ年収850万円未満」でも、加給年金が支給されないケースもあります。加給年金については、さらに細かい支給要件等があります。
※ 計算結果は概算ですので、実際とは異なる場合があります。

★画像は著作権、肖像権を侵害するものではありません。
★画像に著作権、肖像権に申し出があれば即時、削除します。