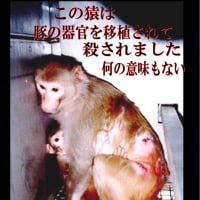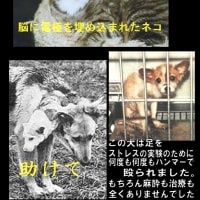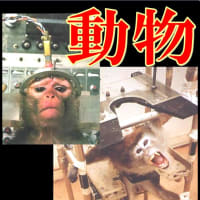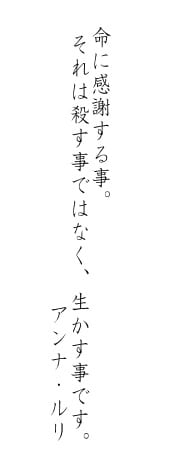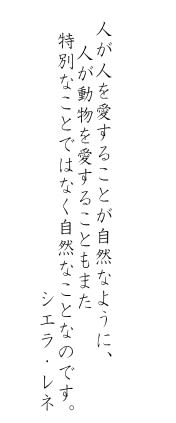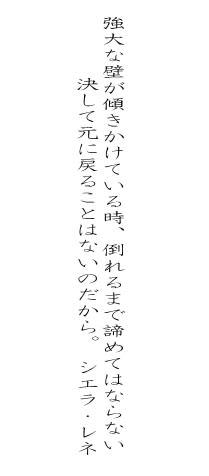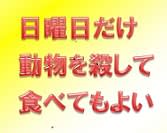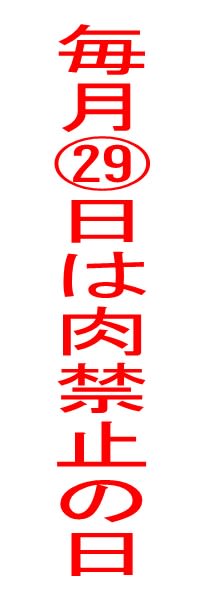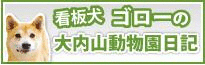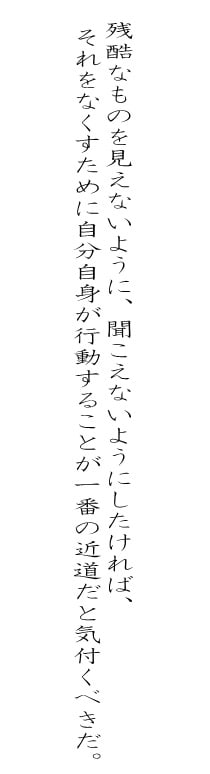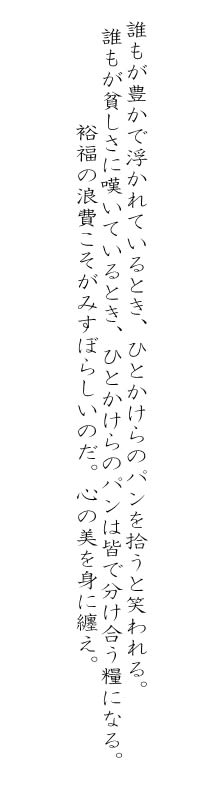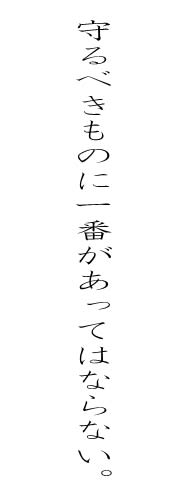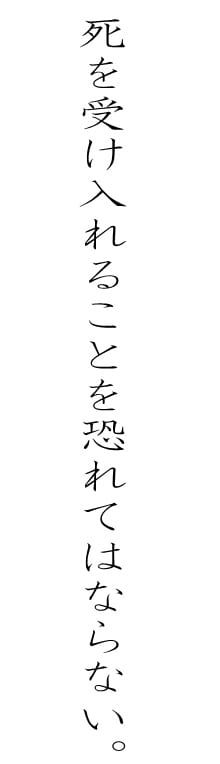子犬を親から引き離す日数は? どうなる動物愛護法改正 - 時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/v4?id=dog-cat0001
■子犬を親から引き離す日数は
5年に一度の見直し
今や飼い犬、飼い猫は15歳未満の子どもの数を上回る。
そんな家族の一員として大切なペットにも関わりの深い動物愛護管理法(動物愛護法)が今年改正される予定だ。
5年に一度見直される動物愛護法。
環境省の動物愛護のあり方検討小委員会は、法律改正について2010年8月から25回にわたり、関係者からのヒアリング、議論を行った。
その結果、昨年12月に報告書が出され、取り締まりの強化、自治体の収容施設、実験動物の取り扱いなど多岐にわたって改善するべき点を挙げた。
中でも、「病気の子猫が送られてきた」「業者と連絡が取れない」などとトラブルが多いペットのネット販売は現物確認の義務化、幼い犬猫などをイベント会場で販売する移動販売には規制の必要性が盛り込まれた。
一方、子犬などを販売するために親犬や兄弟犬から引き離す時期(日齢)は最も大きな争点だ。
「あまりに幼くして親兄弟から離すと社会化されずに、ほえる、かむなど問題行動が出る」と、生後「8週齢」を求める意見に対し、業界は「日齢が長くなると、ワクチン、えさ、設備などコスト増になる」と「45日」を主張し、意見は対立している。
移動販売は「規制」
大きなイベント会場で短期間に動物が展示販売される移動販売。
報告書は「動物の販売後のアフターケアが十分に確保されていない例がある。動物にとって移動、騒音がストレスになりやすく、えさ、水など日常のケアが困難な上、病気の治療もされにくい」などとして規制を唱える。
獣医師で日本動物福祉協会(東京都品川区)調査員の山口千津子さんは「子犬は不特定多数の人間に取り囲まれ、ものすごく疲れる。入場者は自分の犬を会場に連れて行けるので、病気がうつる可能性も。本当に飼えるかどうか熟慮せず、会場で衝動買いすることもあり得ます」と問題視する。
ネット販売「対面説明を義務に」
インターネットによる動物販売はトラブルが後を絶たない。
国民生活センターによると、ペットの相談全体のうち、インターネット販売は11年度(1月20日現在)で13.5%に上る。
相談内容は「約30万円の子犬を購入し、遠方の事業者から空輸で送られてきたが、届いた晩に下痢をし、入院した。事業者は『空輸で送り返すように』と言ったが、弱った子犬を送ることはかわいそうでできなかった。間もなく犬は死に、獣医は『もともと体力がなかった上に空輸でさらに体調が悪化したのでは』と話している。
治療費、葬儀代を負担してほしい」などといったもので、深刻なケースも少なくない。
環境省の報告書でもネット販売は、「飼い主に対する動物の特性や、遺伝疾患や病気の有無についての事前説明が不十分。対面で説明し、現物確認の義務化が必要」としている。
山口さんは「移動販売と同様、幼い犬猫にとって空輸などのストレスは非常に大きい。そもそも一緒に生活する動物を、実物を確認しないで購入することについて考え直してほしい。ぬいぐるみを買うこととは訳が違います」と指摘する。
既にネット・移動販売に関しては、日本動物福祉協会、自然と動物を考える市民会議(杉並区)などの愛護団体と全国ペット協会(千代田区)、日本消費者協会(同)などが協力して07年から、「ペットに病気や障害があるからといって、もののようにたやすく返品できません。すぐ死んだり、病気や障害が見つかると、治療やお金がかかり、つらい思いをします」と消費者に訴えるパンフレットを配り、業界には自主規制を呼び掛けている。
自然と動物を考える市民会議事務局長の塩坪三明さんは「自主規制を要請するようになってから、移動販売はいくつか減りましたが、いまだに主要都市を回る大規模なイベントなどはやめようとしません」と話す。
災害時の対応
東日本大震災ではペット、家畜など数多くの動物が被災した。
特に東京電力福島第1原発事故では、飼い主が避難したために取り残された犬や猫、牛、馬などが餓死・病死したり、今も数え切れない動物が放浪したりしている。
多くのボランティア、獣医師らが福島で救援活動を行ってきたが、救い出されたのはごく一部にとどまっている。
難航した動物救援の背景の1つには法律の不備がある。
そもそも動物愛護法には災害対応の条文がなく、約8割の自治体が地域防災計画などに災害時におけるペットの取り扱いについて明記しているが、自治体間で対応には差がある。
このため報告書には、「災害時に動物救援や迷子動物の対策を推進するための根拠として、動物愛護法に基本的事項を規定するべき」などとされた。
「震災時は、動物を連れて避難するという原則を入れるべきです」と話すのは山口さん。
「東日本大震災では、特に福島第1原発から半径20キロ圏内の警戒区域に入ることができないため、えさやりすらできない。放射能のためにボランティアもなかなか来られない。せめて動物愛護法に同行避難の原則があったら、福島の飼い主はとりあえず動物と一緒に逃げられたはず」と悔しさをにじませる。
法律に同行避難が盛り込まれれば、各自治体は地域防災計画の中で、被災者が連れてきた動物の保護方法など具体的な対策作りを迫られることになる。
親兄弟から離す「日齢」は意見分かれる
一方、幼い犬猫を親、兄弟姉妹から離す「日齢」については意見が分かれている。
現行法は日齢について規制はない。
06年施行の前回改正法の際も議論されたが、まとまらなかった。
報告書では「一定の日齢に達していない犬猫を親や兄弟姉妹から引き離すと、適切な社会化がなされない。特に犬は早期に引き離すと、成長後にかむ・ほえる癖が起きる可能性が高まるとされる」とした。
その上で、親などから離す理想的な時期として、米国で実験結果がある7週齢、欧州などで規制事例がある8週(56日)齢、業者団体が主張する45日齢を併記した。
ちなみに日齢について同省のパブリックコメントは、「8週齢以上」と「8~12週齢」などが計約6万2000件、「45日」「現行のまま」などは約4万6000件だった。
「45日」主張の業界
45日を主張する全国ペット協会名誉会長の米山由男さんは「業界の自主努力で、多くは現在40日程度を守っています。8週にすれば、感染症などを防ぐためのワクチン、餌、成長に合わせたケージの準備などのコストが増え、市場は約3割縮小する」と力を込める。
さらに「8週の科学的根拠が不明。日本の飼い犬は小型犬が多いが、欧米では中型犬で実験している。小型犬は大型より成長が早いから、海外の研究を日本に当てはめるのは疑問」とする。加えて「欧米は犬をあくまで動物として扱うが、日本人は幼い犬を手塩にかけて育て、人間並みの家族として扱う人が多い」と幼犬を好む日本特有の文化があると強調する。
「8週に必ずしも反対ではないが、むしろ賛否以前に繁殖場の改善、行政による業者の検査態勢の強化を優先すべきです」と話すのは、ペットショップ大手のコジマ(同江東区)の会長小島章義さんだ。
コジマは40~45日齢の子犬を繁殖業者やオークション(せり市)を通じて購入した後、ワクチン代は同社が負担し、獣医師が健康チェックをしてから販売している。
「零細な繁殖業者が多いので、8週が導入されれば動物の健康悪化や、日齢を偽ったり、遺棄が増えたりする恐れがある」と懸念する。
「理想は9週齢」と専門家
これに対し、日本獣医生命科学大講師(臨床動物行動学)の水越美奈さんによれば、小型犬と大型犬の成長速度に明らかな違いが出るのは生後5~6カ月ごろなので、8週未満では子犬の行動パターンは同じという。
「むしろ子犬は大きさではなく週齢を合わせて遊ばせた方がいいぐらい。子犬は親兄弟との生活を通じて、犬同士のあいさつや謝り方を学びます。好奇心で家族から離れても、不安になったら母犬の元に戻ってくる。母犬はステーションの役割を果たし、母犬でないと子犬にコミュニケーション技術などを教育できない」と説明。
「40日程度では散歩時に他の犬にわんわんほえる問題が起こり得る。犬は怖いから、やられる前に攻撃的になってしまうのです」と話す。
その上で「子犬同士の遊びが盛んになり、一番社会性を学ぶ時期は7週。8週目に物や人に対して恐怖心が強くなる。完全に離乳するのは9週齢ぐらいなので、理想的な日齢は9週です」と明言する。
獣医師も「8週齢以上」望む声強く
獣医師の中でも8週齢以上を求める声は強い。
ペットを診る動物病院の獣医師約4400人から成る日本小動物獣医師会(港区)は昨年11月、会員を対象に動物愛護法改正に伴う日齢に関するアンケート調査を行った。
回答者は約760人で、「日齢が早過ぎたために起きる悪影響はあるか」との問いに99%が「ある」と答えた。
具体的には、「精神的に未熟なために、移動のストレスで体調不良が起こる」「体力的、免疫的に未熟なために疾病が発症する」「社会化される時間が短いため、警戒・恐怖・依存心、攻撃性など性格形成にゆがみが出る」といった例が挙げられた。
好ましい日齢については「60日以上」がほぼ半数に上り、次に「90日」が13%、「56日(8週)」は10%。「49日以下」は6%に過ぎなかった。
法案めぐり議論紛糾も
NPO法人地球生物会議(文京区)によると、10年度に行政に殺処分された犬は約5万3000匹に上っている。
水越さんは「子犬の飼い主から、『甘がみではなく、出血するほどかまれる』などと問題行動についてよく相談を受けます。犬が捨てられる主な理由の1つである問題行動には、日齢が遠因となるケースもあると思われます」と指摘する。
水越さん自身、現在3匹の犬を飼っている。
犬は2匹が殺処分寸前、1匹はペットショップから譲り受けた。
そのうち3歳のアフガンハウンドについては「ドッグショー用に繁殖されたけれど、成長が遅いために捨てられたと思われます。引き取った時は本来20キロある体重が11キロしかなく、がりがりだった。人や他の犬にガウガウほえて、今でも大変」と語る。
ペットショップから来た6歳のイタリアングレイハウンドは「生後30数日で母犬から引き離されたとみられ、40日齢でわたしが引き取った。この子は他の犬とは全く遊ばず、ドッグランに連れて行ってもわたしのそばから離れない」という。
9歳のイタリアングレイハウンドについては「繁殖用の犬だったらしく、寄生虫フィラリアに感染し、歯はぼろぼろで、触ろうとしただけで悲鳴を上げ、金属のケージをたたく音を怖がる。トイレのしつけもできていなかった」と話す。
このような実体験から水越さんは、「社会化されていない犬を飼うと、本当に苦労する。飼い主にとっても、動物が健康でちゃんと社会化されていることが一番幸せ。だから日齢は非常に重要なのです」と力を込める。
改正法案は議員立法でつくられ、通常国会に提出される予定。
焦点の日齢については議論が紛糾する可能性もある。
飼い犬、飼い猫が計2000万匹を超える今、動物福祉の要である法律を改善していく責任が人間に問われている。
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/v4?id=dog-cat0001
―――――――
実験動物の事を記事にしてもらいたいと色々電話をかけてるときに、偶然この記事を書いた人と話すことができて、調べてみると言ってくれた。
動物のためになるこんな良い記事をぜひまた書いてもらいたい。
8週齢規制なんて全然甘い!
時事ドットコムのページ右下にお問い合わせのリンクがあります。
そこから記事への意見を送って応援しましょう!
国民が本当に何を求めてるか、動物の事はペットの事しかメディアはあんまり分かってないから伝えましょう。
こんにちは。
時事ドットコムの記事「子犬を親から引き離す日数は? どうなる動物愛護法改正」http://www.jiji.com/jc/v4?id=dog-cat0001
を読みました。
動物愛護法が、動物の命を守るために改正されるのではなく、利権が絡む業界団体やそこから金が流れている議員や行政の大反対によって、国民の大多数が望む動物のための法改正が妨害されている事、誰が見ても明らかな癒着構造です。
この記事を書いてくれた記者さんは命に対する思いやりが強く、本当に素晴らしいと思います。
実験動物や動物実験施設の法規制の事も、医学界や動物実験関係者とそこへ癒着している議員などからの大反対で、まったく法律に盛り込まれない危険な状況になっています。
一般メディアが全く取り上げようとしないこの問題の闇を、真のジャーナリストとして、弱者や命を救うための記事をこれからもよろしくお願いします。
応援しています。
全日本動物愛護連合 大阪支部 福島景
keidoubutu-aigo@yahoo.co.jp
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor
絶賛放映中!
http://alfjp.blog96.fc2.com/
動物愛護 映画館 ★ アニマルライツ シアター

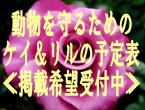

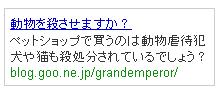
2012/6/9
http://www.jiji.com/jc/v4?id=dog-cat0001
■子犬を親から引き離す日数は
5年に一度の見直し
今や飼い犬、飼い猫は15歳未満の子どもの数を上回る。
そんな家族の一員として大切なペットにも関わりの深い動物愛護管理法(動物愛護法)が今年改正される予定だ。
5年に一度見直される動物愛護法。
環境省の動物愛護のあり方検討小委員会は、法律改正について2010年8月から25回にわたり、関係者からのヒアリング、議論を行った。
その結果、昨年12月に報告書が出され、取り締まりの強化、自治体の収容施設、実験動物の取り扱いなど多岐にわたって改善するべき点を挙げた。
中でも、「病気の子猫が送られてきた」「業者と連絡が取れない」などとトラブルが多いペットのネット販売は現物確認の義務化、幼い犬猫などをイベント会場で販売する移動販売には規制の必要性が盛り込まれた。
一方、子犬などを販売するために親犬や兄弟犬から引き離す時期(日齢)は最も大きな争点だ。
「あまりに幼くして親兄弟から離すと社会化されずに、ほえる、かむなど問題行動が出る」と、生後「8週齢」を求める意見に対し、業界は「日齢が長くなると、ワクチン、えさ、設備などコスト増になる」と「45日」を主張し、意見は対立している。
移動販売は「規制」
大きなイベント会場で短期間に動物が展示販売される移動販売。
報告書は「動物の販売後のアフターケアが十分に確保されていない例がある。動物にとって移動、騒音がストレスになりやすく、えさ、水など日常のケアが困難な上、病気の治療もされにくい」などとして規制を唱える。
獣医師で日本動物福祉協会(東京都品川区)調査員の山口千津子さんは「子犬は不特定多数の人間に取り囲まれ、ものすごく疲れる。入場者は自分の犬を会場に連れて行けるので、病気がうつる可能性も。本当に飼えるかどうか熟慮せず、会場で衝動買いすることもあり得ます」と問題視する。
ネット販売「対面説明を義務に」
インターネットによる動物販売はトラブルが後を絶たない。
国民生活センターによると、ペットの相談全体のうち、インターネット販売は11年度(1月20日現在)で13.5%に上る。
相談内容は「約30万円の子犬を購入し、遠方の事業者から空輸で送られてきたが、届いた晩に下痢をし、入院した。事業者は『空輸で送り返すように』と言ったが、弱った子犬を送ることはかわいそうでできなかった。間もなく犬は死に、獣医は『もともと体力がなかった上に空輸でさらに体調が悪化したのでは』と話している。
治療費、葬儀代を負担してほしい」などといったもので、深刻なケースも少なくない。
環境省の報告書でもネット販売は、「飼い主に対する動物の特性や、遺伝疾患や病気の有無についての事前説明が不十分。対面で説明し、現物確認の義務化が必要」としている。
山口さんは「移動販売と同様、幼い犬猫にとって空輸などのストレスは非常に大きい。そもそも一緒に生活する動物を、実物を確認しないで購入することについて考え直してほしい。ぬいぐるみを買うこととは訳が違います」と指摘する。
既にネット・移動販売に関しては、日本動物福祉協会、自然と動物を考える市民会議(杉並区)などの愛護団体と全国ペット協会(千代田区)、日本消費者協会(同)などが協力して07年から、「ペットに病気や障害があるからといって、もののようにたやすく返品できません。すぐ死んだり、病気や障害が見つかると、治療やお金がかかり、つらい思いをします」と消費者に訴えるパンフレットを配り、業界には自主規制を呼び掛けている。
自然と動物を考える市民会議事務局長の塩坪三明さんは「自主規制を要請するようになってから、移動販売はいくつか減りましたが、いまだに主要都市を回る大規模なイベントなどはやめようとしません」と話す。
災害時の対応
東日本大震災ではペット、家畜など数多くの動物が被災した。
特に東京電力福島第1原発事故では、飼い主が避難したために取り残された犬や猫、牛、馬などが餓死・病死したり、今も数え切れない動物が放浪したりしている。
多くのボランティア、獣医師らが福島で救援活動を行ってきたが、救い出されたのはごく一部にとどまっている。
難航した動物救援の背景の1つには法律の不備がある。
そもそも動物愛護法には災害対応の条文がなく、約8割の自治体が地域防災計画などに災害時におけるペットの取り扱いについて明記しているが、自治体間で対応には差がある。
このため報告書には、「災害時に動物救援や迷子動物の対策を推進するための根拠として、動物愛護法に基本的事項を規定するべき」などとされた。
「震災時は、動物を連れて避難するという原則を入れるべきです」と話すのは山口さん。
「東日本大震災では、特に福島第1原発から半径20キロ圏内の警戒区域に入ることができないため、えさやりすらできない。放射能のためにボランティアもなかなか来られない。せめて動物愛護法に同行避難の原則があったら、福島の飼い主はとりあえず動物と一緒に逃げられたはず」と悔しさをにじませる。
法律に同行避難が盛り込まれれば、各自治体は地域防災計画の中で、被災者が連れてきた動物の保護方法など具体的な対策作りを迫られることになる。
親兄弟から離す「日齢」は意見分かれる
一方、幼い犬猫を親、兄弟姉妹から離す「日齢」については意見が分かれている。
現行法は日齢について規制はない。
06年施行の前回改正法の際も議論されたが、まとまらなかった。
報告書では「一定の日齢に達していない犬猫を親や兄弟姉妹から引き離すと、適切な社会化がなされない。特に犬は早期に引き離すと、成長後にかむ・ほえる癖が起きる可能性が高まるとされる」とした。
その上で、親などから離す理想的な時期として、米国で実験結果がある7週齢、欧州などで規制事例がある8週(56日)齢、業者団体が主張する45日齢を併記した。
ちなみに日齢について同省のパブリックコメントは、「8週齢以上」と「8~12週齢」などが計約6万2000件、「45日」「現行のまま」などは約4万6000件だった。
「45日」主張の業界
45日を主張する全国ペット協会名誉会長の米山由男さんは「業界の自主努力で、多くは現在40日程度を守っています。8週にすれば、感染症などを防ぐためのワクチン、餌、成長に合わせたケージの準備などのコストが増え、市場は約3割縮小する」と力を込める。
さらに「8週の科学的根拠が不明。日本の飼い犬は小型犬が多いが、欧米では中型犬で実験している。小型犬は大型より成長が早いから、海外の研究を日本に当てはめるのは疑問」とする。加えて「欧米は犬をあくまで動物として扱うが、日本人は幼い犬を手塩にかけて育て、人間並みの家族として扱う人が多い」と幼犬を好む日本特有の文化があると強調する。
「8週に必ずしも反対ではないが、むしろ賛否以前に繁殖場の改善、行政による業者の検査態勢の強化を優先すべきです」と話すのは、ペットショップ大手のコジマ(同江東区)の会長小島章義さんだ。
コジマは40~45日齢の子犬を繁殖業者やオークション(せり市)を通じて購入した後、ワクチン代は同社が負担し、獣医師が健康チェックをしてから販売している。
「零細な繁殖業者が多いので、8週が導入されれば動物の健康悪化や、日齢を偽ったり、遺棄が増えたりする恐れがある」と懸念する。
「理想は9週齢」と専門家
これに対し、日本獣医生命科学大講師(臨床動物行動学)の水越美奈さんによれば、小型犬と大型犬の成長速度に明らかな違いが出るのは生後5~6カ月ごろなので、8週未満では子犬の行動パターンは同じという。
「むしろ子犬は大きさではなく週齢を合わせて遊ばせた方がいいぐらい。子犬は親兄弟との生活を通じて、犬同士のあいさつや謝り方を学びます。好奇心で家族から離れても、不安になったら母犬の元に戻ってくる。母犬はステーションの役割を果たし、母犬でないと子犬にコミュニケーション技術などを教育できない」と説明。
「40日程度では散歩時に他の犬にわんわんほえる問題が起こり得る。犬は怖いから、やられる前に攻撃的になってしまうのです」と話す。
その上で「子犬同士の遊びが盛んになり、一番社会性を学ぶ時期は7週。8週目に物や人に対して恐怖心が強くなる。完全に離乳するのは9週齢ぐらいなので、理想的な日齢は9週です」と明言する。
獣医師も「8週齢以上」望む声強く
獣医師の中でも8週齢以上を求める声は強い。
ペットを診る動物病院の獣医師約4400人から成る日本小動物獣医師会(港区)は昨年11月、会員を対象に動物愛護法改正に伴う日齢に関するアンケート調査を行った。
回答者は約760人で、「日齢が早過ぎたために起きる悪影響はあるか」との問いに99%が「ある」と答えた。
具体的には、「精神的に未熟なために、移動のストレスで体調不良が起こる」「体力的、免疫的に未熟なために疾病が発症する」「社会化される時間が短いため、警戒・恐怖・依存心、攻撃性など性格形成にゆがみが出る」といった例が挙げられた。
好ましい日齢については「60日以上」がほぼ半数に上り、次に「90日」が13%、「56日(8週)」は10%。「49日以下」は6%に過ぎなかった。
法案めぐり議論紛糾も
NPO法人地球生物会議(文京区)によると、10年度に行政に殺処分された犬は約5万3000匹に上っている。
水越さんは「子犬の飼い主から、『甘がみではなく、出血するほどかまれる』などと問題行動についてよく相談を受けます。犬が捨てられる主な理由の1つである問題行動には、日齢が遠因となるケースもあると思われます」と指摘する。
水越さん自身、現在3匹の犬を飼っている。
犬は2匹が殺処分寸前、1匹はペットショップから譲り受けた。
そのうち3歳のアフガンハウンドについては「ドッグショー用に繁殖されたけれど、成長が遅いために捨てられたと思われます。引き取った時は本来20キロある体重が11キロしかなく、がりがりだった。人や他の犬にガウガウほえて、今でも大変」と語る。
ペットショップから来た6歳のイタリアングレイハウンドは「生後30数日で母犬から引き離されたとみられ、40日齢でわたしが引き取った。この子は他の犬とは全く遊ばず、ドッグランに連れて行ってもわたしのそばから離れない」という。
9歳のイタリアングレイハウンドについては「繁殖用の犬だったらしく、寄生虫フィラリアに感染し、歯はぼろぼろで、触ろうとしただけで悲鳴を上げ、金属のケージをたたく音を怖がる。トイレのしつけもできていなかった」と話す。
このような実体験から水越さんは、「社会化されていない犬を飼うと、本当に苦労する。飼い主にとっても、動物が健康でちゃんと社会化されていることが一番幸せ。だから日齢は非常に重要なのです」と力を込める。
改正法案は議員立法でつくられ、通常国会に提出される予定。
焦点の日齢については議論が紛糾する可能性もある。
飼い犬、飼い猫が計2000万匹を超える今、動物福祉の要である法律を改善していく責任が人間に問われている。
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/v4?id=dog-cat0001
―――――――
実験動物の事を記事にしてもらいたいと色々電話をかけてるときに、偶然この記事を書いた人と話すことができて、調べてみると言ってくれた。
動物のためになるこんな良い記事をぜひまた書いてもらいたい。
8週齢規制なんて全然甘い!
時事ドットコムのページ右下にお問い合わせのリンクがあります。
そこから記事への意見を送って応援しましょう!
国民が本当に何を求めてるか、動物の事はペットの事しかメディアはあんまり分かってないから伝えましょう。
こんにちは。
時事ドットコムの記事「子犬を親から引き離す日数は? どうなる動物愛護法改正」http://www.jiji.com/jc/v4?id=dog-cat0001
を読みました。
動物愛護法が、動物の命を守るために改正されるのではなく、利権が絡む業界団体やそこから金が流れている議員や行政の大反対によって、国民の大多数が望む動物のための法改正が妨害されている事、誰が見ても明らかな癒着構造です。
この記事を書いてくれた記者さんは命に対する思いやりが強く、本当に素晴らしいと思います。
実験動物や動物実験施設の法規制の事も、医学界や動物実験関係者とそこへ癒着している議員などからの大反対で、まったく法律に盛り込まれない危険な状況になっています。
一般メディアが全く取り上げようとしないこの問題の闇を、真のジャーナリストとして、弱者や命を救うための記事をこれからもよろしくお願いします。
応援しています。
全日本動物愛護連合 大阪支部 福島景
keidoubutu-aigo@yahoo.co.jp
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor
 | 犬を殺すのは誰か ペット流通の闇 |
| 朝日新聞出版 |
絶賛放映中!
http://alfjp.blog96.fc2.com/
動物愛護 映画館 ★ アニマルライツ シアター

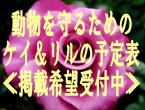

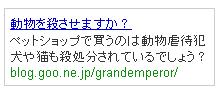
2012/6/9