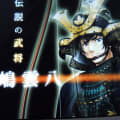前回ブログ記事で洲崎神社の切支丹灯篭を
ご紹介しました。その後、「”切支丹灯篭”の
定義は…?」…と、質問をいただきました。
私、灯篭に関して詳しくはないのですが、
知っている範囲でコメントに返信しました。
切支丹灯篭は、江戸時代初期、キリスト教
禁教の時代に作られた灯篭です。いくつか
特徴があって、隠れ切支丹の人達がこれを
密かに信仰していた…、と伝えられています。
ま、それを疑問視する人もあるようですが…。

切支丹灯篭の特徴としては…。
「灯篭の棹の部分に丸いふくらみがある。」
「灯篭にマリア様が彫られることがある。」
「灯篭に不思議な文字が彫られることがある。」
下の写真は洲崎神社の切支丹灯篭です。
3つの特徴のどれも合わせ持っています。
棹の部分に丸いふくらみがあり、そこに
文字が彫られ、その下にマリア様が…!

「結構、いろんな社寺にありますよ。」なんて
書いたのですが、じゃぁ、どこにあるの…?
…と、歴史マニアさんに突っ込まれました。
これに関して、ブログ記事でお答えしましょう。
まず思いついたところで、石川県七尾の
”本行寺”です。隠れキリシタンの寺として
知られる本門法華宗の歴史あるお寺です。

このお寺は昔、キリシタン武将、高山右近の
修道所があった…、という伝承がありました。
高山右近の遺品と伝わる品や、禁教の時代
密かにかくまわれていた加賀藩のキリシタン
女性達の遺品や茶室が残されていました。

井戸のそばに”切支丹灯篭”がありました。
灯篭の棹の部分にふくらみがあり、そこに
謎の切支丹文字(?)が刻まれています。
見たことのない不思議な形をしています。
これは、父なる神を讃えるマークだとか…。

”加賀藩の隠れキリシタン伝承の寺”だから、
切支丹灯篭があってもおかしくないですね。
高山右近がお茶を点てる時に、この井戸で
水を汲んだ…との伝承のある”右近の井戸”。
井戸の傍らに、さりげなく置かれていました。

本行寺には古い茶室があり、前庭にもう1つ
切支丹灯篭らしきものが置かれていました。
棹のふくらみやマリア像も確認できますね。
”切支丹灯篭”は、高山右近などキリシタン
ゆかりの地で見つけることができるかも…。

さて、秀吉による禁教令が出た桃山時代に、
高山右近が潜んでいた、と伝えられる京都
伏見には、切支丹灯篭が3つもあります。
その1つは、伏見にある酒造りの資料館
”月桂冠大倉記念館”に庭にありました。
棹に丸いふくらみがあって、何か所か
修復の跡がある江戸時代の石灯篭です。

そしてもう1つは、同じく京都の伏見にある
長建寺境内の片隅に置かれていました。
「マリア灯篭 江戸幕府によるキリシタン禁教
時代に流行」との立札が建てられていました。
京都での切支丹信仰を語っているようです。
切支丹信仰との関係は、よくわかりませんが
桂離宮には7つも切支丹灯篭があるそうです。

切支丹灯篭、それ以外に思いついたのは、
滋賀県米原市にある、青岸寺のものです。
以前、ブログ記事に書いたことがありました。
ここはちょっと珍しい灯篭で、上にお地蔵様、
下にマリア様、両方のお姿が彫られています。

お庭を作った時、どこからか運びこまれた
不思議な灯篭…。元は2つあった灯篭を
組みあわせたものかもしれないですね。
切支丹灯篭は、江戸時代、禁教の時代の
遺物の他、新しく作られたものもたくさん
あるようです。謎の切支丹文字までそっくり
復刻されたレプリカも見たこともありました。

謎に包まれた隠れ切支丹の遺物ですが、
たまたま神社やお寺でこれを見つけると、
四葉のクローバーを見つけた時のような
ハッピーな気分になって思わず写真撮影。
気に留めると結構、あちこちにあります。
みなさんもぜひ、見つけてください…!