『明月記』は鎌倉時代の公家である藤原定家の日記です。この中に鳩についての記述があり、これが日本での鳩レースの始まりだとする人がいます。しかし、これがどうも怪しいのです。
見てきたわけではないので絶対に違うとは言えませんが、書いていないことを想像で補うには限界がありますので、勝手に創作してはまずいだろうと思います。
では、まず一つ目です。承元2年(1208)9月28日の記述。

ここにある「近年天子上皇皆鳩を好みたまふ、長房卿、保教等、もとより鳩を養ひ、時をえて馳走す」とあるのを、ここの「馳走」は「競争」のことだとして、鳩のレースが行われていたのだと、してしまうのです。
しかし、文の前後を読んでみると、鳩の「競争が行われていた」とは思えません。
前段で、鳩をとりに門に昇った男が帰りに松明で火事を起こしているのを取り上げ、近年皆鳩を好んでいるがと上の文を挟み、続いて後段で、鳩を取りに鐘楼に登って災禍になり町が疲弊するのは、鳩の事では済まず国家の衰微とも言えることだ、と嘆いている。
ここから読み取れるのは、鳩を取りに町中の門塔や鐘楼に昇るような行いを指して「馳走す」と書いているのではないでしょうか。鳩を取りに駆け回っているのであって、鳩が馳走しているのではないと思います。
簡単に鳩の競争・鳩レースと言いますが、具体的にはどのように競争させるのでしょうか?
当時、寺社などに棲みついていた鳩は、もともとは日本にいなかった鳩で、ドバト・イエバト・ドウバトなどと呼ばれており、唐から輸入されたものを放生会などで放ったのが野生化したものです。それを、食用や愛玩用に捕まえて、飼っていたのでしょう。
鳩には帰巣性があり、巣から離れたところから放すと、距離にもよりますが巣に戻ってきます。家で飼っていて、籠や小屋から出して放しても逃げずに、飛んでもまた家に戻ってくるように馴れた鳩は、家から離れたところから飛ばすと家へ戻ってくる性質があります。
このような鳩を競争させる場合には、複数の鳩をある地点から同時に飛ばせば、家に戻って来る順番を確かめることが出来ます。同じ家の鳩ならば、このような競争は可能です。
ところが、違う家の鳩を競争させる場合には、どうすればいいでしょうか。飛ばす地点は同じでも、帰ってくる家は違います。隣の家で、庭続きで鳩小屋があり互いによく見えるのなら、どちらが早く帰ったのか判断できますが、家が離れている場合にはどのように順位をつければいいでしょうか? 勝敗の審判が問題になります。
この時代に、この問題を解決して鳩レースを行っていたのなら、その技術は一度きりのものではなく後世にも伝わっているはずだと思いますが、他には見えません。
ちなみに、『吾妻鏡』ではこの部分の「馳走」が「奔走」となっています。
次の記述です。建暦2年(1212)7月10日の記述。

「鳩合」と書いてあります。「負態云々」ともありますので、何等かの競い合いで罰ゲームがあったようです。歌合や花合などが知られていますが、「鳩合」が競技だとすれば、どのようなものなのでしょう。罰ゲームがあるので勝敗をつけたようです。競う両者が鳩を持ち寄り、何かを比べるのでしょう。鳩の姿形でしょうか。羽色の美しさや体の大きさ、または鳴き声でしょうか? あるいは闘鶏のように、二羽の鳩を喧嘩させるのでしょうか? 鳩はおとなしい生き物ですが、発情期には巣や雌をめぐって喧嘩をする場合もあります。野生ならば逃げれば終わりますが、狭い所では流血の事態にもなります。「鳩合」とあるだけでは内容は分かりません。
それなのに、「鳩合」を、鳩を飛ばせて速さを競うことだと、何の根拠もなく推測する人がいます。これでは、鳩レースは日本が発祥ということになりますが・・・。
ちなみに、鳩レース発祥の地であるベルギーでは、1810年ごろに鳩レースが始まったと言われています。










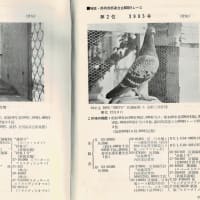
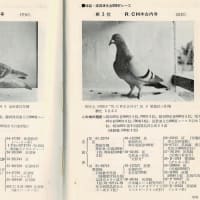
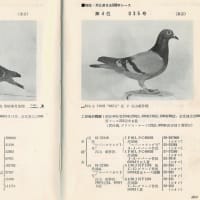
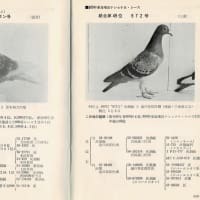
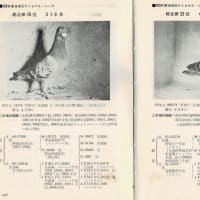
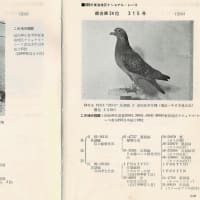
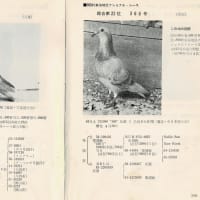
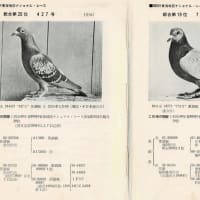
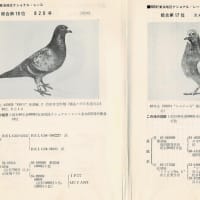
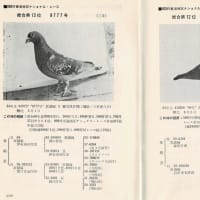
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます