C)中国へ
中国への昆布ロードが始まったのは、清朝の汪楫ワウシフ一行が琉球から帰った後、天和3年(1683)から貞享ジョウキョウ3年(1686)頃だといわれています。長崎経由が本格化したのは元禄11年(1698)とされています。
那覇の昆布座(18世紀末設置)が置かれた所にすぐ近い村が、古くからの市が開かれた所で、その村を若狭町村といいます。沖縄唯一の漆器の産地でした。若狭町の町は若狭市の市が転じたもののようです。村の名前からすれば、若狭(小浜か敦賀)から渡って来た人が市を開いた村だと言えそうですが、証拠はありません。ただ、若狭町村の市は古く14世紀からあり、ワカサイチと呼ばれていました。若狭から昆布などを売りに来ていたのかも知れません。
薩摩藩は琉球を通じて昆布を清国に売り、代償に薬種(竜脳リュウノウ ・沈香ジンコウ・山帰来サンキライ ・辰砂シンシャ・麝香ジャコウ・牛黄ゴオウ など)を得て日本で売り、財を築きました。薬種は富山の薬売りが買いましたが、昆布を薩摩に集めたのも富山の薬売りでした。
富山の薬売りは全国を22に分け、独特な組制度を持っていました。このうち薩摩藩組26人脚キャク は昆布を通して薩摩藩と密着し、能登屋(密田家、後に北陸銀行を設立)などの信用のある富山売薬行商人に低利融資をして北前船を造船させ、それで昆布を運ばせたのです。
薩摩藩の清国との昆布交易は密貿易に近いものでした。幕府に知られてはならないものだったのです。それで、昆布を薩摩まで運ぶのに、西廻り航路をとらずに、太平洋側を航海するという危険もおかしました。当然、遭難する船もありました。能登屋の持船の北前船「長者丸」(650石積み、21反帆)は天保9年(1834)9月中旬、松前箱館で薩摩藩向昆布を五、六百石積込み、10月上旬出港しました。南部田之浜で艀テンマ を修理し、11月上旬に仙台唐丹湊トウニミナト(釜石)に着きます。そして、11月23日に同港を出帆するものの、朝4時頃大西風に吹き流されて遭難してしまいました。翌年4月、米国捕鯨船ジェームス・ローバ号に救助されるまで昆布を食べて飢えをしのぎましたが、3名が死亡していました。9月にローバ号がハワイに着き、そこからカムチャッカ・オホーツク・アラスカ・エトロフへと送られました。
このような困難もありましたが、薩摩藩は清国との昆布交易で財政を立て直し、蓄財もなしました。そして、嘉永6年(1853)には、鹿児島にガス灯・ガラス・陶磁器・紡績・火薬・弾丸・小銃・大砲などの洋式の製造所(集成館)を建設しました。
この「集成館」でつくった武器で、薩摩藩は倒幕へと至ったのです。昆布が日本の近代の扉を開く原動力となったのです。










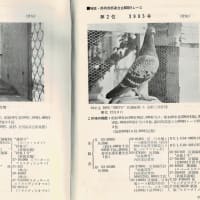
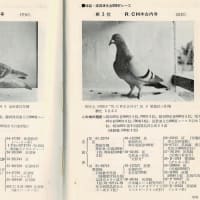
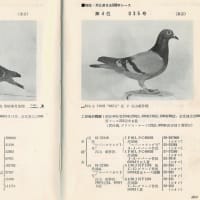
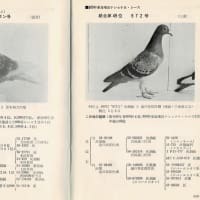
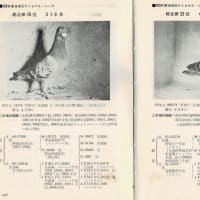
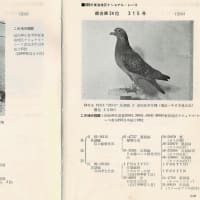
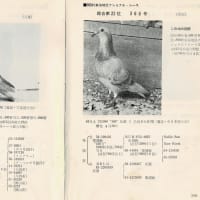
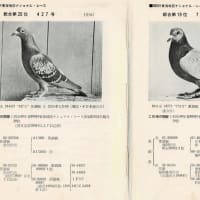
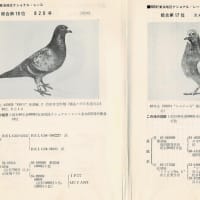
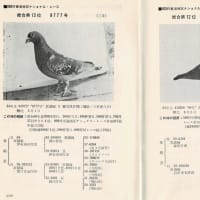
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます