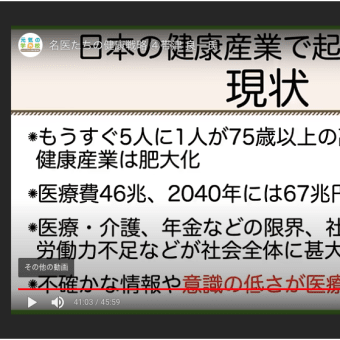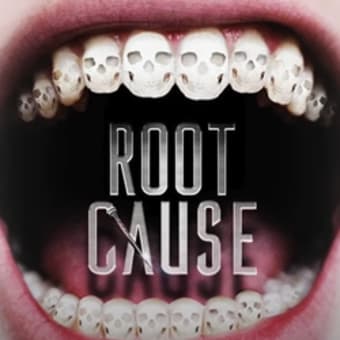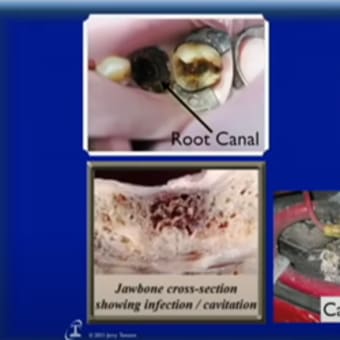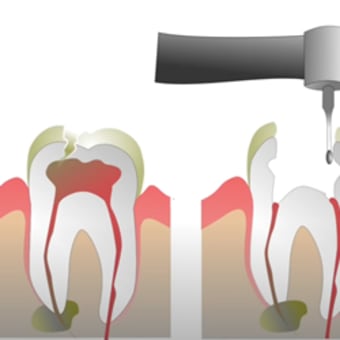八世紀のチベット仏教から派生した蔵方(チベット)医学の基本は「解剖」だったと言われます。また、現在の中国では、西欧医学と東方医学を統合する「中医学」という組織によって中国医学界をバランスよく発展させる努力をし始め、欧米からそれを学びに訪れる人が絶えないと言うことです。
明治時代に、旧来からの漢方や東洋医学を捨て去り、西洋医学一辺倒できた日本と違う賢明な選択をした中国の医学界の今後に世界の注目が集まっています。
東方医学には「中国医学」と「インド医学」「チベット医学」の三つがあり、日本で云う漢方医学は、江戸時代までに得た漢の時代までに確立された中国医学を基礎として独自に発展したものと言われています。
西欧医学と東方医学の統合を目指す中医学と呼ばれる現在の中国の医学と比較し、質量ともに、立ち後れていることが分かったのもつい最近のことです。一方の検査や緊急医療は日本が得意。
日本では、昭和53年に招いた中医学の専門家との交流で漢方医学の遅れが確認され、いま新たな勉学が開始されています。日本の医療現場も、西欧医学と東方医学の統合を目指した新たな医療体系の確立に期待が集まっていますが、鍼灸が医療現場の第一線で活躍しない間は、薬漬け医療システムからの脱却は無理といわれている。
仏教が生まれたのはインドですが、外来民族の侵入によってそれが散財し、完全なかたちはチベットにしか残っていないと云われています。チベットでは「医学僧」と呼ばれる地位が確立され、チベット仏教の修行を積んでから医学を修めたようで、これからの時代の一つのヒントが隠されているような気がします。
医療やお茶、お花など、本来、人間の生と死を受け持つ仏教と関連のあったものも、日本では個別の文化「○○道」として栄えたようで、仏に変わって人々に功徳を施すという目的や感謝の気持ちなど、本質的な部分は忘れてしまったようです。いま話題の大相撲の世界も、世界に広めようとする目標のない、独りよがり的な発想から早く脱却せねば、世界に広める改革は起こりえない。単に日本「独自」の文化をPRするといった時代ではなく、違った世界と交わることで初めて「伝統文化」も、世界に向けてより発展、普及するのではないでしょうか。
2024/09/13追稿
いまの日本、がん治療に抗がん剤を使ってるようでは、世界の笑いもの。東方医学を広めるどころではないようだ!