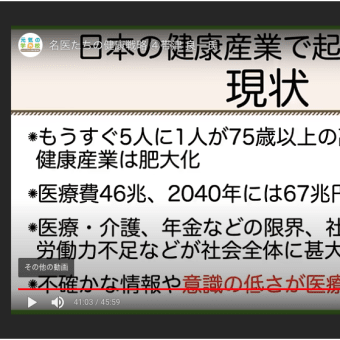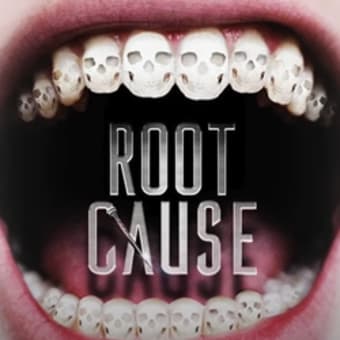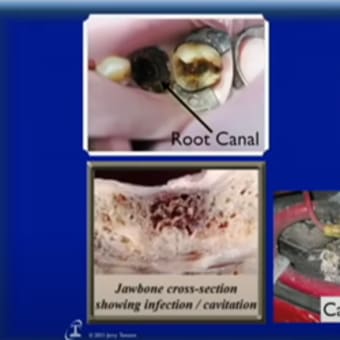血液循環の仕組みを説明する『第四の水の相』
私たちの身体の中には、毛細血管をすべて含めると、総延長10万キロメートル―すなわち地球二回り半―にも及ぶ長さの血管があると言われています。図8は毛細血管の中を通る赤血球の写真です。右上の挿図は個々の赤血球が円盤状の扁平な形をしていることを示しています。ここで大事なポイントは、毛細血管の太さよりも赤血球の方がずっと大きいことであり、従って赤血球は毛細血管の中を流れる時には、図8に示すようにひしゃげた形に変形しながら通って行かざるを得ません。 8図 8図 従って、毛細血管の中の血液の流れにおいては大きな抵抗があるはずです。このことを考慮すると、心臓のポンプ作用のみでは、すべての毛細血管を通しての血液循環の流れを引き起こすには不十分である、と一部の科学者は考えてきました。 |
ポラック博士はこの身体の中の血液循環の仕組みを説明することの出来る驚くべき実験を行いました。それは図9に示すように、親水性の素材で出来た透明なチューブを、水の入った容器の中に沈めてみたのです。その結果、図9に矢印で示してあるように、チューブの中を水が自動的に流れることを発見したのです。勿論、エネルギー源がなければ、このような運動は生じません。この場合のエネルギー源は外界から来る光であり、その光エネルギーをチューブの親水性表面の近傍の水が吸収して、『排除層』すなわち『第四の水の相』を形成して、マイナスの電荷を帯びるようになります。 9図 9図 |
その一方で、チューブの中心部分ではバルクの水が形成されて、ヒドロニウム・イオン(H3O+)が集まります。このヒドロニウム・イオンはプラスに帯電しているために、お互いに反発して離れようとしますが、そのためにチューブの中心部分で水の流れが生じるのです(図10)。 10図 10図 |
左右どちらの方向に水が流れるかということは、初期の微妙な条件の違いによって決定されますが、いずれにしても外界から赤外線などの光のエネルギーを受け取っている限り、チューブの中を水が自動的かつ持続的に流れ続けるのです。
この実験結果から、ポラック博士は、私たちの身体の中で血液循環が起こるためには、心臓のポンプ作用に加えて、血管内で形成された『第四の水の相』が、外界からの光エネルギーを吸収して、血液が物理的に血管の中を流れるのに必要な運動エネルギーへと変換する作用が必要である、と考えています。
すなわち、「『第四の水の相』を考えないと私たちの身体の中の血液の循環は説明できない」ということになります。これまた大変驚くべき研究成果です。
もう一つ、「水の記憶」を示す“高度希釈実験”にある
“デジタル生物学”の提唱、というタイトルに興味を持ちました。
“デジタル生物学”の提唱、というタイトルに興味を持ちました。
その フランス人科学者 Jack Beveniste(ジャック・ベンベニスト)について書かれた記事の中に、次のような文言が・・・・。
ある科学者の言葉です。
「水が情報を保存するなんて当たり前のことさ。
でもそれじゃビジネスが成り立たなくなってしまうだろ。
だからみな黙っているのさ。
生き延びるためにはとにかく金がなくてはならない。
だからそんな事実なんか誰も知りたくない、
それどころか全く迷惑に思っているのだよ」
でもそれじゃビジネスが成り立たなくなってしまうだろ。
だからみな黙っているのさ。
生き延びるためにはとにかく金がなくてはならない。
だからそんな事実なんか誰も知りたくない、
それどころか全く迷惑に思っているのだよ」
コロナ騒動も世界規模のビジネスのために行われているのでしょうね〜。
「第四の水の相」と上記ページのプラズマの世界と関連するような・・・。

16日追稿
目に見えない水の世界を理解することによって世の中を知り、学校の教科書やマスコミ情報、書籍や小説からは得られないように封印された自分や人々を知ることで、悪用して利権を我がものにする存在を知り、その先にある真実を学ぶ。そういったきっかけが、今回の話から「悟れる」人が、一人でも二人でも生まれるといいな〜、と思っています。