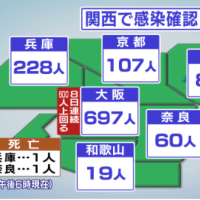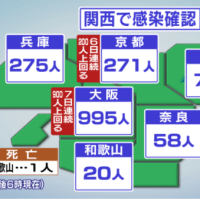(タイトル掲句:『御袋を使用した俳句 | 俳句季語一覧ナビ』より)
母の亡き日永に淡(うす)き影法師
影法師は、私のそれ。
日脚が伸びてきたとは言え、日差しは弱く、ものの影はなべて淡い。
母は、私を幼名で呼んでいた。母に対するとき、私は、普段の「ワタシ」でも「オレ」でもなく、母の子としての「僕(ボク)」になった。「ボク」は、母の内部にあるがままに、同時に私のアイデンティティの一部をも構成しており、そのことが、母が生きている限り私が安んじておられる要因ともなっていたと思う。母が亡くなると同時に私の内部にあった「ボク」の部分も永久に失われた。親を喪ったときに一般的に語られる喪失感は、そのことにも起因するのだろう。
最後に母の口から私の名を聞いたのは、死ぬ5日前のことだった。もつれた舌を懸命に操り、ようやくしぼり出したような声音であった。味覚障害のため、水さえ拒むようになっていたから、口腔内の乾燥は極度に達していたはずだ。しかし、湿らせたガーゼを母の口に当てるなどということはためらわれた。それは、後悔の念の一因となっている。
今でも、母の私を呼ぶ声とその呼び方の変化、そのときどきの表情を、痛ましく思い出す。その間、身動きしていなかったことに、後で気づくのが常である。

母の亡き日永に淡(うす)き影法師
影法師は、私のそれ。
日脚が伸びてきたとは言え、日差しは弱く、ものの影はなべて淡い。
母は、私を幼名で呼んでいた。母に対するとき、私は、普段の「ワタシ」でも「オレ」でもなく、母の子としての「僕(ボク)」になった。「ボク」は、母の内部にあるがままに、同時に私のアイデンティティの一部をも構成しており、そのことが、母が生きている限り私が安んじておられる要因ともなっていたと思う。母が亡くなると同時に私の内部にあった「ボク」の部分も永久に失われた。親を喪ったときに一般的に語られる喪失感は、そのことにも起因するのだろう。
最後に母の口から私の名を聞いたのは、死ぬ5日前のことだった。もつれた舌を懸命に操り、ようやくしぼり出したような声音であった。味覚障害のため、水さえ拒むようになっていたから、口腔内の乾燥は極度に達していたはずだ。しかし、湿らせたガーゼを母の口に当てるなどということはためらわれた。それは、後悔の念の一因となっている。
今でも、母の私を呼ぶ声とその呼び方の変化、そのときどきの表情を、痛ましく思い出す。その間、身動きしていなかったことに、後で気づくのが常である。