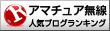アマチュア無線局長は小さな外交官とかいう言葉をよく本で読んだ。その通りだな、世界が相手だから・・・マナーも問われるし。サッカーは世界の合言葉というような TV解説者もいたがまあその通りだね。
中学時代、BCLをしていて、放送波を聞いていたらアマチュア無線の信号が聞こえ・・・という私のような同じパターンで無線を始めた局は多いだろうな。
BCLも最初は日本語放送を受信することがほとんどで、英語放送など、まず何言ってるか、内容がわからない。局名アナウンスを聞き取ることに集中する。
がそれもあまり面白くないようになった。無線局を開局するまでは、少し難しい 中南米の出力数キロワットの地元向け放送局を狙うようになった。受信機はFR-101や ドレークのR-4C、R-1000など・・・。アンテナは40mくらいのLW。
3MHZ、4MHZ、6MHZ帯あたりの周波数は 中南米放送局がとても多い。80年頃は春、秋のDXシーズンは南米方面のパスがFBだった。アマチュア無線も同じくコンデションが上がりだした。
ブラジルは公用語がポルトガル語、他の国はスペイン語だ。(たまに英語放送もあったが)。スペイン語は歯切れがよく、又 各国の音楽を聞くのも大変興味があった。ボリビア、ペルー、エクアドルなどのフォルクローレ。そのなかでもペルーのワイニョの土臭い感じのするものは、混信のなか聞くと日本の地方の民謡のようにも感じる場合もあった。
コロンビア、ベネズエラは陽気なラテンPOPS、サルサのメロディは気分が晴れる。ブラジルはサンバ。
まあFMのように良好ではないが楽しめた。また CMを聞き取るのも面白い。”インカ・コーラ”のCMは多かった。(名前も南米的、中々いける味だとか)。
日本時間の夕方17:00頃から受信でき、21:00頃までの4時間くらいが南米局受信タイムだ。が冬の朝のロングパスなどで現地の夜の番組が聞こえる場合もあった。このようなときよく聞こえたのが、サッカー中継である。
アナウンサーが興奮して実況中継をしてる。、南米アナはすごい早口でまるで機関銃のようにポンポンと言葉が出てくる。ゴールのときが最高潮だがそれは地元チームが点を入れた場合のみ。喜怒哀楽丸出しのアナウンスが南米的。
日本で行われた過去のトヨタカップでは 副音声でスペイン語やポルトガル語が流れていたが、日本語アナなど余計な話を聞くよりこっちが面白い。
すごい実話だが、83年の東京で行われたグレミオ(ブラジル)VSハンブルガーSV(西ドイツ)の試合は、副音声でグレミオの地元のポルトアレグレのラジオ局、”グアイーバ”が 本国向け生中継の放送した。
この試合は、延長戦に入ったのだが、日本のNTV系列は 延長戦放送なしという 当時はおそまつな中継だった。試合の最後までTVで見えなかった。残念だった。
ここでBCL 南米DXerは グアイーバのブラジルからの短波放送を受信したという記録がある。すごいね。12月だったから15:00頃でも 南米からのパスがあったようだ。ポルトアレグレは地球の真裏に近く 出力も10KWくらいだっただろうか、いつもよく聞こえる常連局だったが・・・ 懐かしい話だ。
今もたまに 南米局を探してるが・・・人工ノイズばかりだ・・・寂しいなあ。