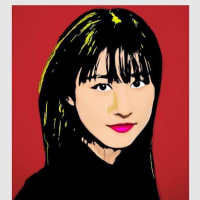余計な装飾を剥ぎ、ナチュラルに楽曲の良さを示して見せた、新たなR&B継承者のステージ。
中盤に差し掛かり、椅子に腰掛けての「ショット・クロック」が終わった後、おもむろに「昨年(2018年)この曲で私の人生は変わったの」と話してから「ブード・アップ」がスタート。1994年生まれの英・ロンドン出身のエラ・メイが全米R&Bチャートの頂点に立ち(英出身のアーティストが全米チャート1位となるのはあまり聞かない……1992年のリサ・スタンスフィールド以来とのこと)、2019年の第61回グラミー賞で最優秀R&B楽曲賞を獲得した、文字通り世間の評価を一変させた2017年リリースの楽曲だ。その“あなたとイイ仲なのよね”という意味のラヴ・ソングのコーラス・パートでエラ・メイが手を左右に振ると、それに合わせてオーディエンスもシンガロング。エラ・フィッツジェラルドから名付けられた名前を持つ、R&B界の未来を担うフィメール・アーティストとして広く知られる新星が、ここ東京にもついにやってきたのだ。
ただ、日本ではR&Bの“ウケ”が良くないのか、チケットは当日券も出た。実際、キャパシティが約5000人の東京国際フォーラム ホールAだが、2階席の中段から最後列までは全て空席。おそらく2000席くらいは空席があっただろうから、グラミーウィナーの公演としては寂しさも覚えてしまう。また、東京国際フォーラムは収容人員こそ多いものの、2階席は4、5階相当の高さとステージとの距離があり、客席上部の空間も広いため、座席によっては臨場感という点でやや物足りなさを感じてしまうかもしれない。音響面に問題があるとかではないが、たとえばパシフィコ横浜と同様に、国際会議を行なう大規模なホールというのは、体感としてステージとの緊密性に欠けるところがあるのかもしれない。
開演前に周囲を見渡し、そんなことを頭に浮かべながら“その時”を待っていると、定刻より20分遅れで暗転。イントロダクションにデビュー・アルバム『エラ・メイ』のインタールード的トラック「エモーション」(アルバムではE:Emotion、L:Lust、L:Love、A:Assertive、M:Mystery、A:Aware、I:Innerとそれぞれの頭文字を繋げるとエラ・メイ(ELLA MAI)になる言葉をスポークンワード的に語る)を流した後に、「グッド・バッド」で幕開け。アフロヘアのヴィジュアル・イメージが強かったが、目に入ってきたのはロングのツインテール・スタイル。一見TLCのレフト・アイ風にも見え、中低音域のヴォーカルワークからはリアーナあたりのクールネスも見て取れた。バンドはキーボード、ベース(キーボード)とドラムスにエラ・メイの両側やや後ろに女性バックコーラスが並ぶという布陣。派手な装飾などはなく、ステージから発する声と音で勝負するというシンプルなスタイルだ。
中盤でステージアウトする際にエド・シーランへの客演曲「プット・イット・オール・オン・ミー」をBGMとして挟み込み、「エヴリシング」の後に「10,000アワーズ」「エニモア」「シー・ドント」とEP曲をメドレー風に組み入れ、「トリップ」をラストにした以外は、ほぼデビュー・アルバムの曲順どおりの曲構成。実にシンプルではあるが、アルバムの世界観をライヴに踏襲したともいえる。世界観が作られているアルバムの楽曲構成を下手にいじることはせず、歌の本質で勝負する……そんな気概を勝手に感じていたがどうだろうか。
「ワッチャマコールイット」ではサビで素早く両腕を左右に振るキュートな姿でシンガロングを求めたり、「ブード・アップ」では客席に“乱入”して歓声の波に包まれにいくなどのパフォーマンスがあったが、軸となるのは90~2000年代の“R&Bクラシックス”の王道といえるシンプルながらも中毒性を持ったミディアム~ミディアム・スロー。派手な演出や誇張はせず、あくまでも楽曲のムードに寄り添ってグルーヴに任せる形が心地よい。EPからの「シー・ドント」でローリン・ヒルの「ドゥー・ワップ(ザット・シング)」を絡ませてくるあたりは、これまで自身の肌身でナチュラルに感じてきたR&B/ヒップホップを、エラ・メイなりの熱量で咀嚼してアウトプットしているよう。瞬発力という意味での高揚は抑え気味ゆえ、人によってはやや抑揚の幅が小さいステージングはメリハリのなさと取る向きもあろうが、全体的に低温ながらもチラチラと漲るパッションが垣間見えるヴォーカルワークは、ジワジワと身体の中を火照らすのに十分。
また、単なる良きR&Bの懐古に終わらず、トラップ調のトラックを組み込んでミディアム・スローでもしっかりとビートを刻んで乗れるグルーヴを構築しているところは、“懐かしくも新しい”というエラ・メイらしさが出ているところか。UK出身でUSフィールドでウケたというのは、US R&Bの良さを匂わせた、90年代~アーリー00年代の楽曲を意識して、という部分は少なからずあるだろう。それほど派手ではないのに中毒性を生むというスタンス、大雑把に言えばメロウネスをしっかりと構築出来るところが、彼女の強みでもある。ヴィジュアルはアフロながらも地味な部類に入るルックスだと思うが(この日はキュートなツインテールだったが)、一度マイクを持てば歌唱とともに輝く、ステージで演じて華になるというのもミステリアスな要素にも転化され、好奇心をそそられるところになっているのかもしれない。今回のステージでも椅子に座っての歌唱曲がいくらかあり、終盤へ向けても一気にクライマックスへ向かうということもない構成だったが、ゆったりしながらも身体を揺らせるヴァイブスが走る展開に恍惚を覚えたのは、揺るぎないメロウネスが根付いているという証なのだと思う。
もう一つ、気に入った点は、エラ・メイの両サイドにいたバックコーラス。同期も使いながら、ドラムは過不足ない程度に加えるというトラックを軸にした、R&Bマナーに則ったバンドのサウンドメイクをバックに、当初はエラ・メイのサポートをきっちりと務めたものの、「ガット・フィーリング」の際にはエラ・メイとの掛け合いの後でそれぞれがソロ・パートを披露。これが単なるサポートとしてのバックコーラスという手合いのものではなく、確実に“歌える”シンガーだったのも、歌唱を大事にするR&Bを分かっていての起用なのだろう。思えば、エラ・メイは元々高校卒業後に3人組ガールズ・グループのアライズ(Arize)に参加して、英版『Xファクター』に出演。その後、解散の憂き目にあっているが、ガールズ・グループの王道セットともいえる3人組で花開かせずに終わった過去を、ソロとして成功した現在にその過去を上書きしているといったら、無理があろうか。そう感じさせるほどコンビネーションも良く、それぞれが歌い始めた瞬間に自分の世界を築ける実力を持ち合わせていた。
椅子に座ってしっとりと歌った「ネイキッド」では、オーディエンスにモバイルフォンのライトを照らすことを促し、満天の星空のなかで子守唄のごとくたおやかに歌う光景も。ラストの「トリップ」も最後だからと無理にヴォルテージを高めようとすることもなく、安定したクールなヴォーカルワークで歌い切った後、オーディエンスへの感謝を告げながら「アリガトー」とサラッとステージアウト。実質70分ほどではあったが、若き世代がR&Bを継承しているという姿に立ち会えた喜びもあって、満足度の高いステージとなった。
まだ、気は早いが、2ndアルバムはどのような方向性になるのかが、非常に気になるところ。それを含めたライヴでの楽曲構成も興味深い。日本ではなかなか根付かないシーンだが、客層は若い女性が多かったことを考えると、ブレイクの火種は燃え続けているようだ。エラ・メイをきっかけに日本でも良きR&Bが頻繁に聴かれる時代になることを期待したい。
◇◇◇
<SET LIST>
00 INTRODUCTION~EMOTION (*)
01 GOOD BAD (*)
02 DANGEROUS (*)
03 SAUCE (*)
04 WHATCHAMACALLIT(*)
05 CHEAPSHOT (*)
06 SHOT CLOCK (*)
07 BOO'D UP (*)
~INTERMISSION~(BGM by Ed Sheeran feat. Ella Mai “Put It All On Me”)
08 EVERYTHING (*)
09 10,000 HOURS
10 ANYMORE
11 SHE DON'T(include phrase of “Doo-Wop(That Thing)”original by Lauryn Hill)
12 OWN IT (*)
13 RUN MY MOUTH (*)
14 GUT FEELING (*)
15 CLOSE (*)
16 NAKED (*)
17 TRIP (*)
(*)song from album “Ella Mai”
<MEMBER>
Ella Mai(vo)
(back vo)
(back vo)
(key)
(key,b)
(ds)
◇◇◇