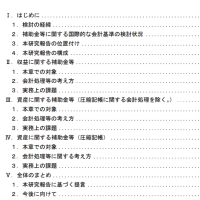新収益基準の解説記事。あずさ監査法人のパートナーへのインタビュー形式で、新収益基準がもたらす経営へのインパクトを解説しています(あずさの宣伝記事?)。
変更点の具体例は...
「アフターサービスを例に説明しましょう。たとえば、PC(パソコン)販売店がPCを売り、これに無料修理などのアフターサービスをつけたとします。従来なら代金の全額をPCの販売時に売上として計上していたのが、新基準では代金をPCの対価とアフターサービスの対価に分け、アフターサービスの対価は、その実施まで売上計上のタイミングが後ろにずれることになります。」
「IFRSを適用している日本の大手消費財メーカーが、流通企業に払っていた物流手数料を売上高から減額するため、約400億円、全体の3%相当の売上高が減る決算予測を出しています。日本基準の下でも、こうしたケースは珍しいものではなくなるのでしょうか。
新基準導入の結果、「減収」となる可能性は高いです。顧客への支払いについては、実体判断が必要で、名目のいかんにかかわらず、実質的に取引価格のマイナスとなるものは、売上高から控除されます。別な例を挙げれば、名目上、販売促進費であっても、実質的にはリベートであれば、売上高から控除されるため、減収に見えることになります。」
適用時期の判断が難しいといっています。
「1990年代以降の会計ビッグバンにおいて時価会計の導入、退職給付会計、減損会計など、日本の会計基準はグローバルスタンダードに近づくように切り替えられてきました。これらはすべて即時強制適用でしたから、経営者はこれに従わざるをえませんでした。ところが今回は早期適用が認められる一方で、強制適用までは時間があるため、導入時期の判断は経営者に委ねられています。自社にとって新基準適用に伴う負荷とメリットでは、どちらが大きいのかと考えながらの決断になります。」
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事