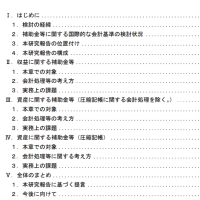サイゼリヤが、BNPパリバ証券と結んでいた豪ドルを巡るデリバティブを解約し、153億円を損失計上するという記事。
「同社は豪州から加工食品などを輸入しており、為替リスクの回避を狙いデリバティブ契約を結んだ。契約は為替相場が一定水準より円安で推移すればサイゼリヤにメリットがあるが、一定水準より円高になると損が膨らむ内容だった。」
デリバティブ契約解約に関するお知らせ(PDFファイル)
「解約した理由は、未曾有の金融危機に起因する為替相場の変動の影響が、当社の経営にとって今後の大きな不安定要因であり、それをいち早く解消することが必要であると判断するに至ったからであります。」
「今後は、リスク分析・管理体制の強化を行い再発防止に努めてまいります。」
10年以上前の一般向け解説書に次のような記述がありました。
「デリバティブ損失事例を読み解くと、常に気づかされるのは、商品購入(や投資)の責任者が、実は何を買ったのかに気づいていないということである。商品についての知識がなく、一体何が起こったのかといぶかり、生じてしまった損失をどうしたらよいかがわからない。キャンセルやヘッジの方法など、もちろん知らない。
大抵の場合、わざわざデリバティブの中でも特にリスクの高いものを選び(だからニュースになったともいえる)、それを管理しているのは1人だけ、多くても数人というのも特徴である。これは、取引を報告する責任がなく、牽制を受ける相手もいないということにつながる。・・・」(足立智彦著「デリバティブ規制で金融はこう変わる」1995年8月発行)
サイゼリヤの場合は、比較的早く開示し対応したので、この記述ほどひどくはないと思いますが・・・。
10年前と大きく違うのは、会計基準です。現行基準ではデリバティブは時価評価が原則ですから、損失が隠ぺいされ、知らないうちに傷が大きくなってしまうという事態はある程度避けられているといえます。旧基準では、実際にマイナスのキャッシュフローが生じる(あるいは予定していたキャッシュフローが得られなくなる)まで損失計上を先送りすることが、可能でした。
当サイトの関連記事
<東証>サイゼリヤがストップ高 デリバティブ損失確定で(2008/12/11 10:25)
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事