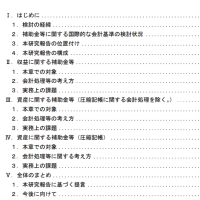「700万円損」負けるまで買わせる仕組債販売の闇 狙いは表面からは見えにくい多額の手数料
仕組債の隠れたコストに焦点を当てて問題点を指摘している記事。
仕組債をめぐる状況は...
「金融庁がハイリスク商品の一種、仕組債の販売に対する締め付けを強めている。当局の働きかけを受けた日本証券業協会は2月、勧誘ルールの見直しを含む自主ガイドラインの改正案を公表した。
仕組債の販売をめぐっては、あこぎな商売で顧客から大切な資産を巻き上げてきた悪徳事業者に対し、当局が正義の鉄槌を下すという勧善懲悪ムードが形成されつつある。」
仕組債の単純化した解説。投資家が債券の利息の中に含めて受け取っているオプションプレミアムが、大幅に中抜きされているということです。
「理解しやすいように、話を以下のようなサイコロゲームになぞらえて、極端に単純化してみよう。
仮にサイコロを振って「1」「2」「3」「4」「5」の目が出れば、投資家は元本に対して数%の利益を得られるとしよう。この状況が「ノックアウト」にあたる。しかし「6」が出ると、元本の数割程度の損失が発生するとする。この状況を「ノックイン」という。」
「実は「サイコロゲーム」の参加者は、サイコロを振るたびに(つまり仕組債を購入するたびに)、参加料(コスト)を支払っている。証券界は長らく「仕組債にコストは存在しない」との建前を貫いていたが、金融庁は2022年、仕組債の隠れた実質的なコストが年率換算で「8~10%程度」に上るとの試算を公表。庁内では「なかには実質コストが20%超に上る悪質な商品も存在する」(中堅職員)との見立てもある。
投資家はゲームに勝利して利益を得ているのに、実際には多額のコストを支払っているというのは一見、矛盾しているように思えるかもしれない。
この「サイコロゲーム」には、外側から見えにくい“仕掛け”がある。「1」~「5」の目が出る(つまり購入した仕組債がノックアウトする)場合に発生する賞金(オプションプレミアム)は、ゲームの参加者である投資家が総取りしているわけではない。
実際には、胴元(金融機関)と投資家が分け合うことになっている。そしてコスト構造の不透明さをよいことに、胴元側がオプションプレミアムの大部分を中抜きしているケースが珍しくないのだ。これが隠れた実質コストになっている。」
「金融庁はノックアウト、ノックイン、満期償還を含む仕組債全体の運用実績を合算して分析。その結果、投資効率は株式や債券など一般的な商品類型よりも劣っている事実が明らかになった。」
「要するに、ノックアウトで稼ぐことができる利率に比して、ノックイン時の損失が大きすぎるということだ。」
確率的には、投資家が相場よりほんの少し高い利息を得られて得をする場合の方が多いのでしょう。しかし、実は、その裏側で、大きなリスクを負わされているわけです。リスクが実現して、多額の損失を被る場合もあり、その確率は、決して小さくはありません。
700万円損した人の例。最初に買った仕組み債では、損は出ませんでしたが、次々と別の仕組み債を勧められたそうです。
「説明を聞いた男性は当初「リスクが高いのでは」と難色を示したが、担当者は執拗に説得を続け、結局、男性はソフトバンク社の株価に連動するEB債に2000万円をつぎこんだ。証券会社の担当者とのやりとりは基本的に、銀行の店舗内で行われたという。
約半年後の2022年12月、ソフトバンク株の急落によってEB債のノックインが発生し、男性は約700万円の損失を被った。「銀行の店舗で、まさか危ない商品をつかまされるとは思っていなかった。亡父から託された大切なお金だった。子供のマイホーム購入資金に充てることができたはずなのに」と悔やむ。
参加者にサイコロを振らせ、「1」から「5」の目が出る(ノックアウトする)と参加者が一定の利益を得る。味をしめた参加者に対し、胴元はより多くの「賭け金」を詰み上げさせる。こうしてサイコロを繰り返し振り続けさせ、「6」の目が出る(ノックインが発生する)までの間、顧客に過大なリスクを背負わせたままゲーム参加料(オプションプレミアムの中抜き)という甘い汁を吸いつくすのだ。」
企業が保有する場合には、全体を時価で処理するか、そうでなければ、債券部分とデリバティブ部分を分けて処理(デリバティブ部分は時価)するのが原則ですが、通常の債券と同様に扱う場合も定められているようです。
これもひどい。
金融庁も問題視する「ファンドラップ」、高齢者を狙う金融機関の甘い誘い(DOL)
「このファンドラップは15本の投信に分散投資していて、それらの投信の信託報酬もファンドラップの契約者が支払う必要がある。顧客の資産配分の状況や各投信のその時の時価によって変わるが、追加手数料は1%ほどになるという。
つまり、基本報酬と合わせて運用資産残高の2.5%ほどの手数料を毎年支払わないといけないのだ。
3~5%の利回りを求める投資で、この手数料は高くないだろうか。」