dynaudioの 20cmウーファー 20W75をベースにしたシステムは、D21AFをツィーターに使う場合は
ミッドレンジを使わなくてはまとまらないという結論に達した。
メーカー発表の資料を見ても D21AFは3Wayまたは4Way用と書いてあるし。
20W75は、2500hzくらいでクロスさせないと粗さが出てしまうようで、一方D21AFは、5Khz以上で
使う方が良さそうだった。かつ、LCネットラワークのクロスは -12dB/Octが聴いた感じでは
良いようだった。
ウーファー用のBOXの容量とダクトのサイズもデータが取れたので、20W75を入れた試作BOXは、
部屋から退去となった。頑丈な箱なので、そのうち30cmのユニットでも探してサブ・ウーファ-で
復活させたいものだ。
さて、20W75のデータは取れたものの、この時期、ベランダでの箱づくりは気が重い。
ということで、手元に残ったのは CONTOUR1.8しかない。このSPも、癖があるが それなりに
評価は高いみたいなので、暫く付き合うことにした。
金田式DCアンプで普通に鳴らすと、低音は出るが、どうも団子状で好きな音ではない。
それに中域が薄い感じだ。高域も若干ヒステリックに響く。
金田式DCアンプをBTL接続にして2台で鳴らすと、低域は出過ぎるくらいに出てくれるが
鈍くて 「どうも??」という感じだ。
アンプはEL156のシングルが、音的には好みで 「いい感じ」に鳴ってくれるが 音量を
上げるとSPの能率が低いので、すぐにクリップしてしまう。夜に聴くのには最高なのだが。
それならば、EL156のppアンプを作るというのが最適の解なのだが、基本パーツは揃っているが
寒さのせいか、シャーシ加工から始めることを思うとおっくうだ。
出来れば、設計出力100W、実質80Wくらいを狙うと、結構、電源など大がかりになる。
当然、モノラル構成にもなるし。
なので、これはジックリと考え、時間をかけて作るべきだろうと思い、次善の策を考えた。
(1)EL-12を復活させppアンプを作る。
(2)使いにくいが、6384ppに再度、挑戦してみる。
(3)無難にEL34ppを作ってみる。
EL-12については、設計値での最大出力は25Wくらいなので、EL156sの15wから、それ程上がるのでは
ないので、今回はパス。音の良さは期待できるのだが、、、、。
(3)のEL34は、一応、昔、LUXから保守用として提供されたTELEFUNKEN製をストックしているが、
昔(もう30年ほど前)使った印象では、大したことがなかった。
6384については、季刊「管球王国」のNo.5で是枝氏が発表された記事を読み すごく魅かれたので
すぐにCopyしてみたが、使った Cetronの6384はバラつきが大きいのか8本中の2本がプレートが
真っ赤になったりした。類似管のTUNG-SOLの6AR6は、音の傾向がソフトというか膨らみがあり
どうも好みではなかった。
それで、なんとか本家のBendix製を集めてみたが、どうも高域に癖があり、常用のアンプには
ならなかった。
が、EL156sの例で、わかったが どうやら当時の私の技量と耳では ちゃんとしたアンプを造れて
いなかったようだ。
ということで、因縁の6384ppに再度、挑戦してみることにした。出力トランスはTANGOのXE-45-8だ。
シャーシと、初段と位相反転の球はEL156Sに使ったのをそのまま使うことにした。
EF184の5結と6N1P(パラ)のP-K分割による位相反転だ。
6384のプレート電圧は370V、カソード電流は55mA、SG電圧は270V。
念のため、手元に残っていた6AR6を使ってみた。予想以上に いい感じの音が出てきた。
が、ちょっと低音が膨らむ感じだ。Cetronの6384を2本とBendix製2本の組み合わせに変更する。
CONTOUR1.8から、初めて聴く音が出てきた。引き締まった低音とボーカルが以前よりも浮き上がる
感じの音だ。何というか抜けが良いというのか、定位がいいというのか、それぞれの楽器が
あるべき位置に居るという感じだ。
がVRを上げると、思ったよりも早い段階でピアノのアタック音がクリップしている。
たぶん6N1PのP-K分割が早い段階でクリップしているのだろうと推測。
供給B電圧を上げ、プレートとカソードの抵抗を33kから20KΩに替えて、電流値を増やす。
これで、かなり良くなった。オーケストラの高域パートが これまで出なかったスムーズな
音に変わった。
何年ぶりに聴いたか忘れる このレコードから すごい音が出てきた。この人の録音は低音といい
すごく音圧がある。日本のレコード会社とは明らかに違う録音手法を感じる。
最新の画像[もっと見る]
-
 プレーヤー復活へ
2ヶ月前
プレーヤー復活へ
2ヶ月前
-
 プレーヤー復活へ
2ヶ月前
プレーヤー復活へ
2ヶ月前
-
 ORANGE社の小さなアンプ
2年前
ORANGE社の小さなアンプ
2年前
-
 MDギターの改造
2年前
MDギターの改造
2年前
-
 MDギターの改造
2年前
MDギターの改造
2年前
-
 MDギターの改造
2年前
MDギターの改造
2年前
-
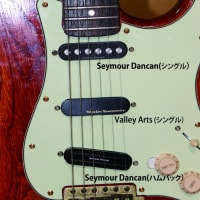 Schector改造記 番外編 その2
3年前
Schector改造記 番外編 その2
3年前
-
 Schector改造記 番外編 その2
3年前
Schector改造記 番外編 その2
3年前
-
 Schector改造記 番外編
3年前
Schector改造記 番外編
3年前
-
 Schector改造記 その5
3年前
Schector改造記 その5
3年前









