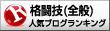稽古開始前、小学生のI君にマンツーマンで受身などを一通り練習させた後、I君が少し飽きてきたようなので、趣向を変えて、I君が好きなパンチやキック主体の日本拳法道式の突き蹴りを教えてみました。
基本の構え、フォーム、力の抜き方、入れ方などを簡単に教え、左右の、突き、直蹴り、中段回し蹴りを数十本ずつ反復練習させたのち、私のボディー相手に打たせてみると、子供でも結構威力があります。
今のうちから練習させたら中々良くなりそうです。
合気道と当身技(あてみわざ)は、別物のようですが、そうではありません。(*注意 当身技=打撃技の事)
合気道の開祖、植芝盛平翁先生は「実戦における合気道は、当身が七分、投げが三分。」と言っておられ,当身技を重要視されていたそうです。
また、実戦合気道として名高い、養神館合気道の創始者、塩田剛三先生も著書”合気道修行”の中で次のように述べられています。
「(実戦は当身七分に対して)
私の体験から言っても、まさにそのとおりだと思います。
それなら、関節技はどうなるのか、と問い返されそうですが、たとえば酔っ払いにからまれたとかいう場合なら、関節技で制圧した方がいいケースもあるでしょう。
しかし、死ぬか生きるかというような状況に身をさらした場合や、多勢を相手にした場合などは、一瞬の勝負になりますので、当身や瞬間的な投げじゃないと身を守り切れません。
逆に言えば合気道の本質はそういうギリギリの闘いにおいて発揮されると言ってもいいでしょう。
さて、当身といっても、合気道の場合は拳や蹴りなどにこだわりません。
体中いたるところが当身の武器になります。
演武会で、私がよく、突進してくる相手を背中で弾き返したり、すれ違いざまに肩で相手を吹っ飛ばしたりするのをごらんになった方もいるかと思います。
ああいうふうに、触れたところがそのまま当身となるわけです。
これは、相手の攻撃をよけてから反撃するのではなく、逆にその攻撃の中に入っていくことによって可能となる技です。
といっても、ただやみくもに体を相手にぶつければいいのではなく、そこに体全体から発する力を集中させなければなりません。
体中どこにでも自在にこの力(集中力)を発揮させることによって、合気道本来の完全に自由な闘い方が可能になるわけです。
また、こういった瞬間の攻撃の場合、もはや当身とも投げとも区別できないようになることがあります。
しかし、そんなことはどうでもいいのであって、とにかく相手が崩れればそれでいいわけです。
形をいくら区別してもしようがありません。
塩田剛三先生著”合気道修行”より引用」
このように、合気道の当身について説かれています。
また、少し古い本ですが、日本伝合気柔術の鶴山晃瑞先生著”図解コーチ 合気道”(昭和50年発行)では次のような記述があります。
(*注意 柔(やわら)=合気道の前身の柔術のことだと思います。ここでは合気道と同意味にとっても良いでしょう。)
「(”当技について”の項より)
現在の学生合気道のあいだには、「やわら」として当然必要とされる「当身」が付随しない体技が普及している。
「当身」と言っても、柔(やわら)と空手ではその目的と方法論において異なる。
空手は一撃破壊が究極目的の打撃法であることに対し、柔の当身は相手の攻撃意欲を押えることにある。
合気道の当身の目的を掲げてみると、
1 相手の気をそらす為。
2 つかんだ手、腕等の軟骨や筋肉に刺激をあたえる為。
3 相手の機先を制する為。
4 防護体をとる為。
等となる。
合気武道に当身を使わない場合は、武術であることを放棄したものとみて差し支えない。
以下、合気武道の当身についてふれる。
中略
(”合気武道の当身”の項で)
当ては「仮当」と「本当」の二種に分けられる。
一般論としては、当身というと、空手道の当身と混同した解釈がとられている。
とくに古い柔道の解説本には、この当身が特に混同されている。
ところが、「やわら」の「当」と空手道の「当」とは、考え方が根本から違っている。
空手道の「当身」は日本伝統古武術の「仮当」と「本当」の中間を狙ったもので、目的も、狙いもまったく異なっている。
これから合気武道を研究される方は、まず、このことを理解しておく必要がある。
中略
(”当身に使われる各部”の項で)
次項の図は合気武道で当身に使われる主たる使用部分である。
一見この図は、空手と似た形態に見えるが、一撃破壊の空手術とは、合気武道の基本技法は、その使用法が違う。
空手は、「突き」、「打ち」、「当て」、「蹴り」の攻め技が主体となることに対し、合気武道では、「やわら」で極めるまでの崩しが目的となっている。
鶴山晃瑞先生著”図解コーチ 合気道”より引用」
以上の事から、合気武道における当身技のイメージが掴めたかと思います。
武術合気道に当身技は必要不可欠です。
京築合気道研究会は、日本拳法道を応用した合気道における当身技の指導も今後行っていく予定です。
(”京築合気道研究会”は2007年1月13日より、道場名を”合気道 真風会”へ変更致しました。)
【ホームページ】