講師を勤められたのは”関西地区本部長であるY先生です。
講習会は午前の部と午後の部があり、ほぼ丸一日に渡るものでしたが、時間があっと言う間に過ぎていったように感じるほど、楽しく充実したものでした。
もちろん技術的な面でも、たくさんの新たな気づきを得ることが出来ましたが、最も印象に残っているのは、講習会の一番始めにY先生がおっしゃった”脚下照顧(きゃっかしょうこ)”の話です。
”脚下照顧”とは、元々は禅の言葉で、良く禅寺の玄関などでみられる言葉です。
”脱いだ履物は、キチンと揃えて、頭を前に向けて下駄箱へ納めましょう。”と言う事です。
いい道場か、そうでないかは、生徒さん達が履物をキチンと揃える習慣があるか、そうでないかでわかるそうです。
このようなマナーは、むしろ海外の道場の方が徹底されており、日本人の方が出来ていないそうです。
合気道修行者ならば、”脱いだ履物は、キチンと揃えて、頭を前に向けて下駄箱へ納めましょう。”
以上は”脚下照顧”の表面的な意味であり、心掛けの事です。
しかしの本来の意味はもっと深いものです。
自分の足下(あしもと)を顧(かえり)みるとは「我が身」や「我が心」を振り返れ、自分が今どうゆう立場にいるか、よく見極めて事に当たれと言うことです。
つまり、他人を批判したり、論じたりするよりも、まずは自分の足下を見つめること、自分を顧みることを忘れぬようにと言う意味です。
禅では日常の全てが修行であり、日常の中や身近な足下にこそ心理があると考えるそうです。
私達の合気道にも、全く同じことが言えると思います。
合気道修行者ならば、より足下の氣を抜いてはいけません。
道場だけが修行の場所ではなく、日常生活も修行の一部と考えて、どんなに忙しいときでも、履物はそろえて脱ぐという、心のゆとりが欲しいものだと思いました。
そして、まさしく自分を顧みたとき、正しい履物の納め方を、自分が出来ていなかった事に気づき、反省しております。(今まで前後の向きが逆で納めてました。)
”他人を批判したり、論じたりするよりも、まずは自分の足下(あしもと)を見つめること、自分を顧みることを忘れぬように。”
これぞ本当の”脚下照顧”でした。(冷や汗)
”合気道 真風会”のみなさん、今後は、私と一緒に”脱いだ履物は、キチンと揃えて、頭を前に向けて下駄箱へ納めましょう。”ネ!
最後に、Y先生、熊本支部のS先生、また福岡のI先生、講習会の際は大変お世話になりました。
自分の合気道を見つめ直す、大変素晴らしい一日となりました。
本当にありがとうございました。
まだまだ未熟な私達ですが、これからも、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。
人気ブログランキングに参加中。
クリックして応援お願いします!
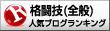
コメント一覧

DK
最近の「合気道 真風会通信」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2005年
人気記事








