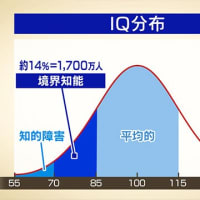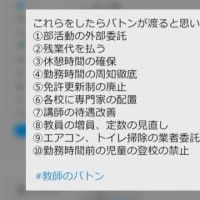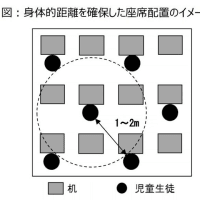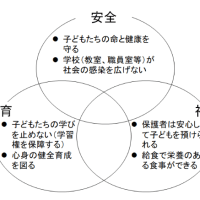「ノートが取れない」中学生。日本の子どもたちの読解力はなぜ落ちたのか。新井紀子さんインタビュー
2019年12月に発表されたPISAの結果で、日本の読解力の低下が大きな話題となった。以前から日本の子どもたちの読解力低下を指摘してきた、国立情報学研究所教授であり「教育のための科学研究所」代表理事・所長も務める新井紀子さんに、この結果をどう受け止めるのか、さらにそもそもなぜ「読解力」が必要なのかを聞いた。
この先はこちらをご覧下さい。
※無料で読めるのは期間限定らしいので、お早めにお読み下さい。
いやー、全くもってその通りだと思います。
筆者は新井先生の発言を全面的に支持すると共に
文科省の役人たちは何もわかっちゃいないので
一人でも多くの市民の皆様に新井先生の発言に触れていただくと同時に
文科省にNOを突きつけていただきたいと思います。
大学入試改革のように。
では、記事の中で特に筆者が印象的に感じた新井先生の発言を抜粋します。
「(PISAの読解力順位低下について)今回順位が下がった、ということ以上に、この結果に関して「戦犯は誰だ?」といった記事の多さが気になりました。文部科学省やSNSに原因を求めるような。さらに読解力のために、1人1台タブレットを導入すべし、という拙速すぎる結論の多さには呆れました。明後日の方向に議論が進んでいることに危機感を持っています。」
「タブレット導入で今まで7時間かかっていた授業が2時間で終わり、残りは深く考える時間に当てる、というような授業は、麹町中学校のようなある意味「特殊な環境」の学校だけでできることだと思います。保護者も経済的な余裕があり、民間からも支援が集まるような私立学校並みの環境が整っている。それが本当に地方でもできるのかを検証せずに、タブレットという言葉が一人歩きしています。」
「ちなみにアクティブラーニングは格差を広げてしまいます。それは、戦後最初のアメリカ主導の学習指導要領である、デューイ式の「生活単元学習」の失敗で明らかになっています。小学生のうちは比較的ワイワイやっていますが、中学生になると、できる子が言ったことに他の子は追随します。だから、授業を全てディスカッションでやることが素晴らしいという主張は、現場を見ていない人の寝言に過ぎません。あるいは、学習指導要領の歴史をきちんと踏まえていないか。中高一貫校から旧帝大や早慶に進んだ官僚が増えると、多様なクラスメートと交流してこないので、こういう夢物語が増えて困ります。」
3つめに紹介した新井先生の発言は、先日筆者が投稿した私論「新学習指導要領で公立中学校の授業が崩壊するという予言」にも通じるものがあると、手前味噌ながら思いました。
一つ疑問があります。
新井先生は、国立情報学研究所教授をつとめていらっしゃいます。
すなわち、国立の研究所で地位のある方が、これだけ現場や現実を理解した見識を書籍・インターネットで発信されているのに
(しかもちゃんとデータを根拠にして)
なぜそれが教育行政にフィードバックされないのか?ということです。
先生の言葉を借りるなら、「中高一貫校から旧帝大や早慶に進んだ官僚が増えたから」なのでしょうか?
「子どもの読解力低下は、必ず数年後に企業の採用や研修のコストとして、あるいは税収の低下として跳ね返ってきます。そのときになって嘆いても遅い。子どものことを現場に行って考える人がもっといて欲しいなと思います。」
こう新井先生は指摘されています。
でもその前に、公教育が崩壊すると思います。
授業がわからなければ、不安または不満がたまる。
不安を処理しきれない子は不登校になり、不満を処理しきれない子は非行に走ったり「楽しみ」をもとめていじめを始めたりする。
それを、子どもたちの努力不足や道徳心不足だとするのは間違いだと思います。
また、読解力不足は「コミュニケーション力不足」の原因にもなりますから、今までよりも些細な原因で大きな児童生徒間のトラブルが発生してしまうようになるとも予想されます。
この間の私論にも書きましたが、市民が真剣に意見を言えば、状況は変わる可能性があります。
大学入試改革がそれを示してくれました。
インターネットとマスメディアの力に期待するしかないな、と思いました。
2019年12月に発表されたPISAの結果で、日本の読解力の低下が大きな話題となった。以前から日本の子どもたちの読解力低下を指摘してきた、国立情報学研究所教授であり「教育のための科学研究所」代表理事・所長も務める新井紀子さんに、この結果をどう受け止めるのか、さらにそもそもなぜ「読解力」が必要なのかを聞いた。
この先はこちらをご覧下さい。
※無料で読めるのは期間限定らしいので、お早めにお読み下さい。
いやー、全くもってその通りだと思います。
筆者は新井先生の発言を全面的に支持すると共に
文科省の役人たちは何もわかっちゃいないので
一人でも多くの市民の皆様に新井先生の発言に触れていただくと同時に
文科省にNOを突きつけていただきたいと思います。
大学入試改革のように。
では、記事の中で特に筆者が印象的に感じた新井先生の発言を抜粋します。
「(PISAの読解力順位低下について)今回順位が下がった、ということ以上に、この結果に関して「戦犯は誰だ?」といった記事の多さが気になりました。文部科学省やSNSに原因を求めるような。さらに読解力のために、1人1台タブレットを導入すべし、という拙速すぎる結論の多さには呆れました。明後日の方向に議論が進んでいることに危機感を持っています。」
「タブレット導入で今まで7時間かかっていた授業が2時間で終わり、残りは深く考える時間に当てる、というような授業は、麹町中学校のようなある意味「特殊な環境」の学校だけでできることだと思います。保護者も経済的な余裕があり、民間からも支援が集まるような私立学校並みの環境が整っている。それが本当に地方でもできるのかを検証せずに、タブレットという言葉が一人歩きしています。」
「ちなみにアクティブラーニングは格差を広げてしまいます。それは、戦後最初のアメリカ主導の学習指導要領である、デューイ式の「生活単元学習」の失敗で明らかになっています。小学生のうちは比較的ワイワイやっていますが、中学生になると、できる子が言ったことに他の子は追随します。だから、授業を全てディスカッションでやることが素晴らしいという主張は、現場を見ていない人の寝言に過ぎません。あるいは、学習指導要領の歴史をきちんと踏まえていないか。中高一貫校から旧帝大や早慶に進んだ官僚が増えると、多様なクラスメートと交流してこないので、こういう夢物語が増えて困ります。」
3つめに紹介した新井先生の発言は、先日筆者が投稿した私論「新学習指導要領で公立中学校の授業が崩壊するという予言」にも通じるものがあると、手前味噌ながら思いました。
一つ疑問があります。
新井先生は、国立情報学研究所教授をつとめていらっしゃいます。
すなわち、国立の研究所で地位のある方が、これだけ現場や現実を理解した見識を書籍・インターネットで発信されているのに
(しかもちゃんとデータを根拠にして)
なぜそれが教育行政にフィードバックされないのか?ということです。
先生の言葉を借りるなら、「中高一貫校から旧帝大や早慶に進んだ官僚が増えたから」なのでしょうか?
「子どもの読解力低下は、必ず数年後に企業の採用や研修のコストとして、あるいは税収の低下として跳ね返ってきます。そのときになって嘆いても遅い。子どものことを現場に行って考える人がもっといて欲しいなと思います。」
こう新井先生は指摘されています。
でもその前に、公教育が崩壊すると思います。
授業がわからなければ、不安または不満がたまる。
不安を処理しきれない子は不登校になり、不満を処理しきれない子は非行に走ったり「楽しみ」をもとめていじめを始めたりする。
それを、子どもたちの努力不足や道徳心不足だとするのは間違いだと思います。
また、読解力不足は「コミュニケーション力不足」の原因にもなりますから、今までよりも些細な原因で大きな児童生徒間のトラブルが発生してしまうようになるとも予想されます。
この間の私論にも書きましたが、市民が真剣に意見を言えば、状況は変わる可能性があります。
大学入試改革がそれを示してくれました。
インターネットとマスメディアの力に期待するしかないな、と思いました。