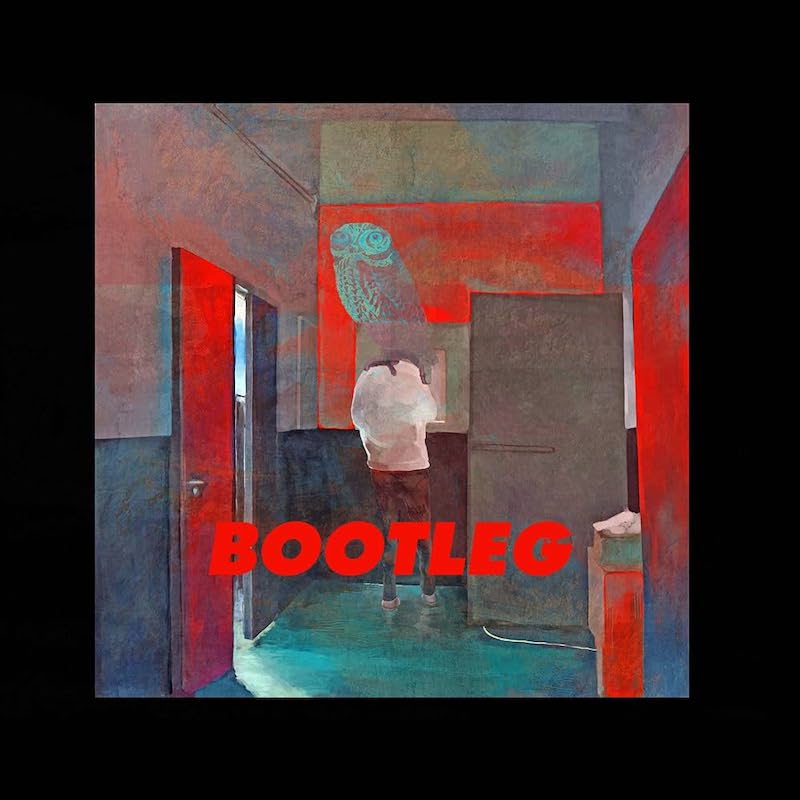記事元:https://news.yahoo.co.jp/articles/9174945

https://realsound.jp/
<中抜>
もしかしたら日本の音楽リスナーのなかには、“複製品”、“模倣品”というワードに対するネガティブなイメージを持つ人も多いかもしれない。おそらくそうしたイメージは、「それぞれの作品に宿るアーティストのオリジナリティこそが重要である」という考え方に起因するのだと思う。Vaundyは、そうした日本における音楽の受容のされ方を踏まえたうえで、意図的に今回のアルバムに『replica』というタイトルを冠している。もともと彼は、「オリジナルはレプリカの来歴から生まれる。」という言葉を原型にして大学の卒業制作と向き合い、今作はまさにその理念のもとに制作されたアルバムだ。
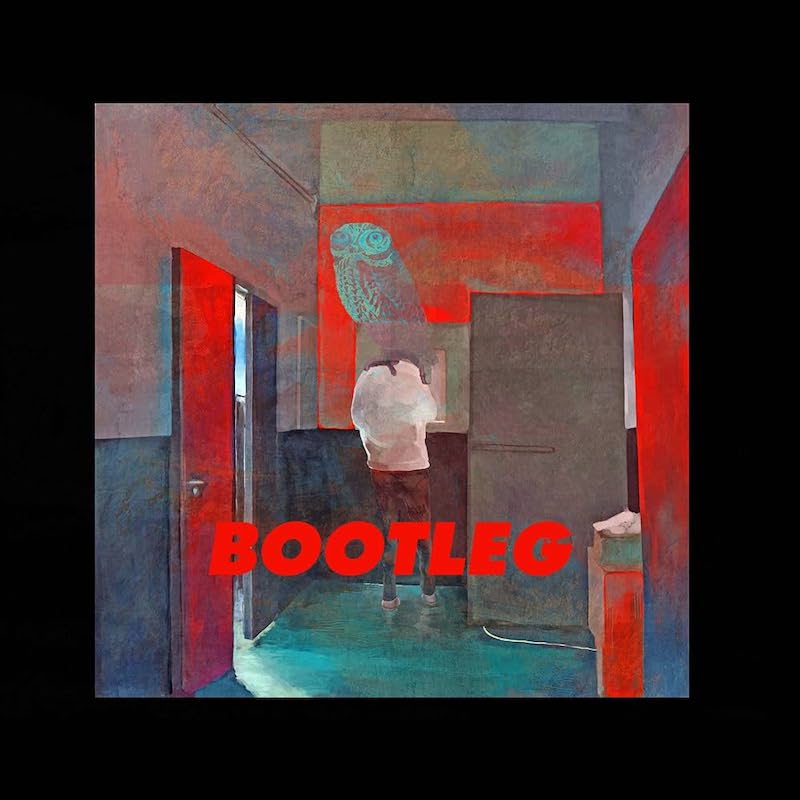
筆者がこの言葉を聞いてまず思い出したのが、2017年にリリースされた米津玄師のアルバム『BOOTLEG』だった。
このアルバムそのもののポップミュージックとしてのクオリティの高さは言うまでもなく、当時特に驚かされたのが、自らの作品に『BOOTLEG』=“海賊盤”と名づける批評性の高さだった。 収録曲「Moonlight」における〈本物なんて一つもない でも心地いい〉という歌詞は、まさに『BOOTLEG』というタイトルと呼応するものであり、また彼は、「Nighthawks」は、BUMP OF CHICKENとRADWIMPSへのオマージュとして作った曲であると明言している。その他にも、「春雷」はPhoenixをはじめとしたフレンチポップへのオマージュ、「かいじゅうのマーチ」は、歌詞の内容と曲のテイストの関係性においてThe CureやThe Smithsをはじめとしたネオ・アコースティックのニュアンスを取り入れていることを、まるでマジックの種明かしをするかのように次々と『ROCKIN'ON JAPAN』2017年11月号のインタビューで明かしていた。同インタビューでは、「あなたたちからすれば偽物の、いろんなものをコラージュしてできた、がらくたの塊みたいな自分だけれど、これだけ美しいアルバムを作ることができるんだって、いま一度証明したかった」(※1)とも語っており、これは後述するVaundyの理念と深く共鳴するものである。
また、『BOOTLEG』の制作エピソードから派生して、彼の創作論が語られたインタビューもある(※2)。
「音楽って、フォーマットじゃないですか。“型”のようなもので成立している部分があるのは事実で、そのなかでいかに自由に泳ぐかじゃないかと。自分がやりたい音楽って、基本的に普遍的なものなんですよ。普遍的なもの、多くの人間、コミュニティ、国や地域などいろんなものの根底に流れているものを普遍性だと言うのであれば、それは“懐かしさ”と言い換えられると思っていて。つまり、どこかで聴いたことがある、どこかで見たことがある、というようなものだと思うんですよね。(中略)そんななかで、最初にリスペクトがあり、その上でどうオマージュするかということをすごく考えながら作っていました」(リアルサウンド:米津玄師が語る、音楽における“型”と”自由”の関係「自分は偽物、それが一番美しいと思ってる」より)
あらためて『BOOTLEG』を聴いて感じるのは、米津がインタビューで語っているように、ポップミュージックとしての高い普遍性を誇る作品であるということだ(その普遍性の高さは、同作の大ヒットによっても裏づけられている)。また、それまでにリリースされた3枚のアルバムと比べると、タイアップ曲(アニメ主題歌に書き下ろした「ピースサイン」「orion」など)や他者とのコラボレーション曲(「fogbound( +池田エライザ )」「灰色と青( +菅田将暉 )」「打上花火」をはじめ、「爱丽丝」のアレンジには常田大希が参加している)が飛躍的に増えている。普遍を目指す、つまり“ポップを目指す”ということは、自分ひとりだけの世界の外へと踏み出すことであり、今から振り返ると『BOOTLEG』は、その後「Lemon」や「パプリカ」などの特大ヒットを契機として、さらに広い世界へと向かっていく米津にとってブレイクスルーのポイントとなった作品であると言えるだろう。
※1:https://rockinon.com/interview/detail/167520
※2:https://realsound.jp/2017/10/post-122911.html
 https://natalie.mu/music/news/552871
https://natalie.mu/music/news/552871