近代世界の誕生【上巻】―グローバルな連関と比較1780-1914―
C・A・ベイリ (著), 平田 雅博 (翻訳), 吉田 正広 (翻訳)

グローバルな世界史は今流行のテーマ。
イギリスの歴史家の主著だというこの書物にも注目したい。
目次からも、骨太の作品であることがうかがえる。
読むのが楽しみだ。
単行本: 356ページ
出版社: 名古屋大学出版会 (2018/12/11)
言語: 日本語
ISBN-10: 4815809291
ISBN-13: 978-4815809294
発売日: 2018/12/11
内容紹介
一国史や地域史を超えて、グローバルな相互連関から「近代世界」の成り立ちを解明。革命の時代から第一次世界大戦にいたる「長い19世紀」を中心に、西洋近代化とは異なる視点で世界史を問い直し、政治・経済から人々の衣食住まで、新しい全体史を描ききるグローバル・ヒストリーの代表作。
書籍の目次
序 章
本書の構成
問題1 「原動力」と経済要因
問題2 グローバル・ヒストリーとポストモダニズム
問題3 深まる「近代の謎」
標準化に向き合う —— 身体的実践
身体の外部に築かれたもの —— 交通・通信と複雑性
第Ⅰ部 旧体制の終焉
第1章 旧体制と「初期グローバリゼーション」
小作農と領主
差異の政治学
国家辺境の支配権
新たな政体の先駆け
「グローバリゼーション」の前史
初期グローバリゼーションと初期近代のグローバリゼーション
次章に向けて
第2章 旧体制から近代性への道
最後の「大いなる栽培化」と「勤勉革命」
アフリカ=アジアの物質文化、生産、貿易における新たなパターン
アフリカ=アジアの「勤勉革命」の内的限界・外的限界
貿易、金融、革新 —— ヨーロッパの競争上の強み
愛郷心・愛国心を育む国家の展開
批判的公衆
アジアやアフリカの公衆の発展
むすびに ——「後進性」、遅れ、結合
次章に向けて
第3章 収斂する諸革命 1780-1820年
世界的危機を熟考する同時代人たち
1720-1820年の世界的危機
国家の正当性の破壊 —— フランスから中国へ
近代左翼と近代国家のイデオロギー的起源
国民対国家・帝国
第三の革命 —— 世界じゅうの穏健で商業的な人々
次章に向けて
第Ⅱ部 生成する近代世界
第4章 世界革命のはざま 1815-65年頃
「国家の破綻」の評価
イギリスの海上覇権、世界貿易、農業の復活
移民 —— 安全弁?
「新世界秩序」の敗者たち 1815-65年
ハイブリッドな正当性の問題 —— 誰の国家なのか
国家の強化とその不十分さ
アジアでの正当性をめぐる戦争 —— 概略
アジアの諸革命の経済・イデオロギー的要因
ヨーロッパにおける飢餓と反乱の時代 1848-51年
グローバルな出来事としてのアメリカ南北戦争
収斂か差異か
議論をふり返って
第5章 工業化と新都市
歴史家、工業化、都市
工業化の前進
工業の不在と貧困
生産、消費、政治の中心としての都市
グローバル危機の都市への影響 1780-1820年
新しい都市の人種と階級
労働者階級の政治
世界的な都市文化とその批判者たち
むすびに
第6章 国民、帝国、エスニシティ 1860-1900年頃
ナショナリズムの諸理論
ナショナリズムはいつ現れたのか
誰の国民か
ナショナリズムの永続化 —— 記憶、国民協会、出版
共同体から国民へ —— ユーラシアの諸帝国
ナショナリズムの位置づけ
国家を持たぬ人々 —— 迫害か同化か
帝国主義とその歴史 —— 19世紀後半
「新帝国主義」の特質
国民国家からなる世界?
初期グローバリゼーションの根強さ
グローバリゼーションから国際主義へ
国際主義の実践
むすびに
注
第Ⅲ部 帝国主義時代の国家と社会
第7章 近代国家の神話とテクノロジー
近代国家の諸局面
国家と歴史家
国家の定義の諸問題
近代国家の定着 —— 地理的広がり
正義の要求と権力のシンボル
国家の資源
社会に対する国家の義務
国家の手段
国家、経済、国民
貸借対照表 —— 国家は何を達成したか
第8章 自由主義、合理主義、社会主義、科学の理論と実践
思想史を取り巻く状況
有徳の共和国の腐敗 —— 古典的テーマ
世界に広がる有徳の共和国
自由主義と市場の到来 —— 西洋の例外性?
自由主義と土地改革 —— 急進的理論と保守的実践
自由貿易か、国民的政治経済か
人民を代表する
世俗主義と実証主義 —— 国境を越えた親近性
社会主義の受容とその各地での反響
グローバルな背景の中の科学
世界レベルの専門職化
むすびに
第9章 宗教の帝国
同時代人の見た宗教
近年の歴史家たちの見解
新しい宗教スタイルの出現
宗教的支配の様式、その主体と限界
宗教的権威の形式化と「帝国」宗教の創造
教義と儀式の形式化
内外の辺境における「帝国」宗教の拡大
巡礼とグローバル化
印刷と宗教伝播
宗教建築物
宗教と国民
むすびに —— 時代の精神
第10章 芸術と想像力の世界
芸術と政治
世界の芸術における混合性と統一性
水平化する力 —— 市場、日常、博物館
出現途上の国民の諸芸術 1760-1850年
芸術と人々 1850-1914年
西洋以外 —— 適応と従属
建築 —— 都市の鏡
世界文学へ?
むすびに —— 芸術と社会
次章に向けて
第Ⅳ部 変化、衰退、危機
第11章 社会的ヒエラルキーの再編
変化と歴史家
「自由の時代」のジェンダーと従属関係
奴隷制の全盛期
契約農奴としての小作農と農村労働者
小作農の解放
農村の従属関係はなぜ存続したか
「ジェントリ」の変容
ジェントリへの挑戦
生存への道 —— 国務と商業
ヨーロッパにおける少数の「大土地」所有者
存続する至上権
連続性か、変化か
第12章 先住民の絶滅と生態系の破壊
「先住民」が意味するものとは
1820年頃以前のヨーロッパ人と先住民
「亀裂の時代」における先住民
白人の大量流入 1840-90年
大量流入の実像 —— ニュージーランド、アフリカ南部、アメリカ合衆国
野蛮性の制御 —— 回復と周辺化
終 章 大加速 1890-1914年頃
「来たるべき世界」を予言する
農業不況、国際主義、新帝国主義
新しいナショナリズム
国際的な自由主義の奇妙な死
まとめ —— グローバリゼーションと危機 1780-1914年
グローバルな比較と連関 1780-1914年 —— むすびに
変化の原動力は何だったか
グローバルで国際的なネットワークにおける権力
競合する統一性と普遍的な複雑性の再検討
1914年8月
謝 辞
訳者あとがき
注
参考文献
図表一覧
事項索引
人名索引
著者について
C.A.ベイリ
(Christopher Alan Bayly)
1945年、イングランド生まれ。オックスフォード大学卒業後,1970年に同大にて博士号取得。ケンブリッジ大学教授,シカゴ大学教授を歴任し,2015年に亡くなる。インド史,イギリス帝国史,グローバル・ヒストリーを専門とし、代表作の本書『近代世界の誕生』以外にも多数の著作がある。1990年にブリティッシュ・アカデミーのフェローに選出され、2004年にウルフソン賞を受賞。2007年にはナイト爵を受勲し、没後の2016年にトインビー賞を受賞。
C・A・ベイリ (著), 平田 雅博 (翻訳), 吉田 正広 (翻訳)

グローバルな世界史は今流行のテーマ。
イギリスの歴史家の主著だというこの書物にも注目したい。
目次からも、骨太の作品であることがうかがえる。
読むのが楽しみだ。
単行本: 356ページ
出版社: 名古屋大学出版会 (2018/12/11)
言語: 日本語
ISBN-10: 4815809291
ISBN-13: 978-4815809294
発売日: 2018/12/11
内容紹介
一国史や地域史を超えて、グローバルな相互連関から「近代世界」の成り立ちを解明。革命の時代から第一次世界大戦にいたる「長い19世紀」を中心に、西洋近代化とは異なる視点で世界史を問い直し、政治・経済から人々の衣食住まで、新しい全体史を描ききるグローバル・ヒストリーの代表作。
書籍の目次
序 章
本書の構成
問題1 「原動力」と経済要因
問題2 グローバル・ヒストリーとポストモダニズム
問題3 深まる「近代の謎」
標準化に向き合う —— 身体的実践
身体の外部に築かれたもの —— 交通・通信と複雑性
第Ⅰ部 旧体制の終焉
第1章 旧体制と「初期グローバリゼーション」
小作農と領主
差異の政治学
国家辺境の支配権
新たな政体の先駆け
「グローバリゼーション」の前史
初期グローバリゼーションと初期近代のグローバリゼーション
次章に向けて
第2章 旧体制から近代性への道
最後の「大いなる栽培化」と「勤勉革命」
アフリカ=アジアの物質文化、生産、貿易における新たなパターン
アフリカ=アジアの「勤勉革命」の内的限界・外的限界
貿易、金融、革新 —— ヨーロッパの競争上の強み
愛郷心・愛国心を育む国家の展開
批判的公衆
アジアやアフリカの公衆の発展
むすびに ——「後進性」、遅れ、結合
次章に向けて
第3章 収斂する諸革命 1780-1820年
世界的危機を熟考する同時代人たち
1720-1820年の世界的危機
国家の正当性の破壊 —— フランスから中国へ
近代左翼と近代国家のイデオロギー的起源
国民対国家・帝国
第三の革命 —— 世界じゅうの穏健で商業的な人々
次章に向けて
第Ⅱ部 生成する近代世界
第4章 世界革命のはざま 1815-65年頃
「国家の破綻」の評価
イギリスの海上覇権、世界貿易、農業の復活
移民 —— 安全弁?
「新世界秩序」の敗者たち 1815-65年
ハイブリッドな正当性の問題 —— 誰の国家なのか
国家の強化とその不十分さ
アジアでの正当性をめぐる戦争 —— 概略
アジアの諸革命の経済・イデオロギー的要因
ヨーロッパにおける飢餓と反乱の時代 1848-51年
グローバルな出来事としてのアメリカ南北戦争
収斂か差異か
議論をふり返って
第5章 工業化と新都市
歴史家、工業化、都市
工業化の前進
工業の不在と貧困
生産、消費、政治の中心としての都市
グローバル危機の都市への影響 1780-1820年
新しい都市の人種と階級
労働者階級の政治
世界的な都市文化とその批判者たち
むすびに
第6章 国民、帝国、エスニシティ 1860-1900年頃
ナショナリズムの諸理論
ナショナリズムはいつ現れたのか
誰の国民か
ナショナリズムの永続化 —— 記憶、国民協会、出版
共同体から国民へ —— ユーラシアの諸帝国
ナショナリズムの位置づけ
国家を持たぬ人々 —— 迫害か同化か
帝国主義とその歴史 —— 19世紀後半
「新帝国主義」の特質
国民国家からなる世界?
初期グローバリゼーションの根強さ
グローバリゼーションから国際主義へ
国際主義の実践
むすびに
注
第Ⅲ部 帝国主義時代の国家と社会
第7章 近代国家の神話とテクノロジー
近代国家の諸局面
国家と歴史家
国家の定義の諸問題
近代国家の定着 —— 地理的広がり
正義の要求と権力のシンボル
国家の資源
社会に対する国家の義務
国家の手段
国家、経済、国民
貸借対照表 —— 国家は何を達成したか
第8章 自由主義、合理主義、社会主義、科学の理論と実践
思想史を取り巻く状況
有徳の共和国の腐敗 —— 古典的テーマ
世界に広がる有徳の共和国
自由主義と市場の到来 —— 西洋の例外性?
自由主義と土地改革 —— 急進的理論と保守的実践
自由貿易か、国民的政治経済か
人民を代表する
世俗主義と実証主義 —— 国境を越えた親近性
社会主義の受容とその各地での反響
グローバルな背景の中の科学
世界レベルの専門職化
むすびに
第9章 宗教の帝国
同時代人の見た宗教
近年の歴史家たちの見解
新しい宗教スタイルの出現
宗教的支配の様式、その主体と限界
宗教的権威の形式化と「帝国」宗教の創造
教義と儀式の形式化
内外の辺境における「帝国」宗教の拡大
巡礼とグローバル化
印刷と宗教伝播
宗教建築物
宗教と国民
むすびに —— 時代の精神
第10章 芸術と想像力の世界
芸術と政治
世界の芸術における混合性と統一性
水平化する力 —— 市場、日常、博物館
出現途上の国民の諸芸術 1760-1850年
芸術と人々 1850-1914年
西洋以外 —— 適応と従属
建築 —— 都市の鏡
世界文学へ?
むすびに —— 芸術と社会
次章に向けて
第Ⅳ部 変化、衰退、危機
第11章 社会的ヒエラルキーの再編
変化と歴史家
「自由の時代」のジェンダーと従属関係
奴隷制の全盛期
契約農奴としての小作農と農村労働者
小作農の解放
農村の従属関係はなぜ存続したか
「ジェントリ」の変容
ジェントリへの挑戦
生存への道 —— 国務と商業
ヨーロッパにおける少数の「大土地」所有者
存続する至上権
連続性か、変化か
第12章 先住民の絶滅と生態系の破壊
「先住民」が意味するものとは
1820年頃以前のヨーロッパ人と先住民
「亀裂の時代」における先住民
白人の大量流入 1840-90年
大量流入の実像 —— ニュージーランド、アフリカ南部、アメリカ合衆国
野蛮性の制御 —— 回復と周辺化
終 章 大加速 1890-1914年頃
「来たるべき世界」を予言する
農業不況、国際主義、新帝国主義
新しいナショナリズム
国際的な自由主義の奇妙な死
まとめ —— グローバリゼーションと危機 1780-1914年
グローバルな比較と連関 1780-1914年 —— むすびに
変化の原動力は何だったか
グローバルで国際的なネットワークにおける権力
競合する統一性と普遍的な複雑性の再検討
1914年8月
謝 辞
訳者あとがき
注
参考文献
図表一覧
事項索引
人名索引
著者について
C.A.ベイリ
(Christopher Alan Bayly)
1945年、イングランド生まれ。オックスフォード大学卒業後,1970年に同大にて博士号取得。ケンブリッジ大学教授,シカゴ大学教授を歴任し,2015年に亡くなる。インド史,イギリス帝国史,グローバル・ヒストリーを専門とし、代表作の本書『近代世界の誕生』以外にも多数の著作がある。1990年にブリティッシュ・アカデミーのフェローに選出され、2004年にウルフソン賞を受賞。2007年にはナイト爵を受勲し、没後の2016年にトインビー賞を受賞。










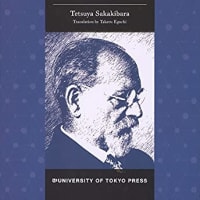
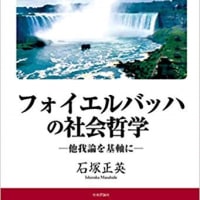
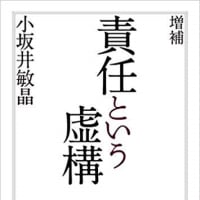
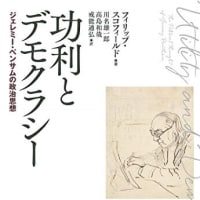
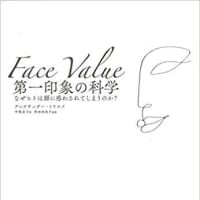

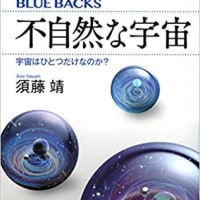
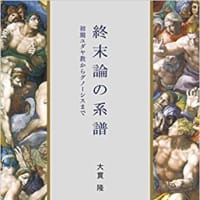
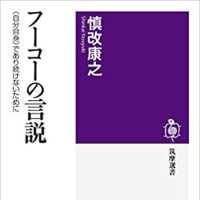
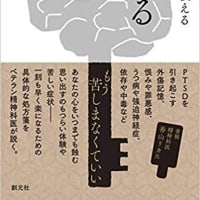
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます