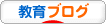「ホリスティック」という概念を一言で定義するのは容易ではないが、仮に世界や人間の営みを全体的なつながりのなかで捉える観点としておく。一人の人間を「あたま」と「こころ」と「からだ」をバラして別々に捉えるのではなくて、それらが一つにつながって相互に作用しあっている全体を見る。そんな全体としての人間は単独で存在しているのではなくて、他の人や社会、モノや自然など、自分をとりまく環境と相互にかかわりあい、影響しあいながら成長していく。人間だけではなくて組織についても同じことが言える。学校は地域や社会と切り離しては成り立たないし、学校図書館も学校という「学びの共同体」とかかわりなく語ることはできない。そう考えると、学校図書館専門職は、他の専門性をもった教職員とともに学校という地盤を耕し、生徒と教師の豊かな学びと成長を促す肥沃な土壌をつくりながら、自らの専門性を育てていくことも、その使命としなくてはならないだろう。そこで問われるのは、子どもの現実とどう向き合うか。型にはまった学びに子どもを当てはめるのではなく、一人ひとりの子どもを、その全体を見据えて元気づけ、学ぶ意欲を高めるにはどうすればいいか。そんな観点から、学校と学校図書館のあり方を問い直したい。そう考えて連続セミナー「ホリスティックな知を育む学校・図書館をつくる」を企画した。第1回目は、菊地栄治さんをお迎えして、大阪の二つの高校の実践をとおしてホリスティックな教育改革について考える機会をもった。
第2回目は、10月21日に「多様な教育を推進するためのネットワーク」代表の古山明男さんをお迎えする。古山さんは、生徒を選ばない塾を経営し、さまざまな若者の現実と向き合うなかで、学校の外から学校や教師の現実を見つめてこられた。そこから見えてきた学校が抱える問題を指摘し、すべての子どもを一元的な価値観・学力観に適合させるのではなく、一人ひとりの子どもに応じた多様な学びを実現できるように学校システムの改革を呼びかけておられる。
 |
変えよう! 日本の学校システム 教育に競争はいらない |
| クリエーター情報なし | |
| 平凡社 |
ブログ:「変えよう! 日本の学校システム 教育は制度がネックだ」
今回は、オルタナティブ教育にも詳しい古山さんに「ホリスティックな知とは何か?」というテーマで、いまご自身が一番表現したいとおっしゃる、シュタイナーとクリシュナムルティの人間観と教育思想を語っていただく。人間の全体性を深く見つめて独自の教育を創りあげた、この二人に共通するのは時代に対する危機意識であり、自由で愛に満ちた人を育てることが真の社会変革をもたらすとして学校をつくったことである。ひるがえって私たちの現実を見つめなおしてみると・・・制度や職務の壁でがんじがらめになって、ひたすら「学力」のみを追い求めてきたひずみがあらわになった我が国の学校と社会に、はたして脱出口はあるのだろうか? 学校を内側から変えていくことはできるのだろうか? 学校図書館が単に本や居場所を提供することを越えて、子どもの全体的な成長と学びの場になるには、どうすればいいか。そんなことを考え、話し合う機会にしたい。
現時点での参加希望者は20名。まだ教室に余裕があるので、今からでも参加申し込みをしていただけます。
「ホリスティックな知とは何か? シュタイナーとクリシュナムルティ」
日時:10月21日(日)13:30~15:30
会場:立教大学池袋キャンパス 14号館6階601教室
参加費:1000円(学部生は無料)
申込:holisticslinfo@gmail.com
また、講演終了後には、この秋に開館した新しい立教大学池袋図書館の見学ツアー(無料)もあります。参加を希望される方は、セミナー参加申込と同じアドレスにご連絡ください。