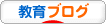昨年12月に書いた『「総合的な学習の時間」から考える「本物の学び」』で考えたことをもとにして、新たな自主講座をはじめます。
子どもが切実な問題意識をもって自ら設定した課題に取り組み、経験や知識を再構成して、新たな気づきや発見にいたる探究の過程で、学ぶ意味を実感する・・・学校教育の過程で子どもが本気になって取り組む「本物の学び」(authentic learning)の機会を生みだしていくには、教師自身の能力開発と学校図書館の活用が鍵になると考えます。
司書教諭や学校司書は、学校図書館をどのように整備し、子どもの学びにどのように関わればいいのか。教師は、学校図書館を活用して、子どもたちの学びをどのように導いていけばいいのか。こうした問題について、お互いの経験知を共有するために、探究的な学びに関わる教員及び学校図書館職員の学びのための自主講座をはじめることにしました。
つきましては、下記のとおりキックオフ・ミーティングを開催して、自主講座の基本的な考え方を整理してプログラムを検討したいと思います。総合的な学習の時間や問題解決学習にかかわる先生方、司書教諭や学校司書の皆さん、その他、関心のある方のご参加をお待ちしています。また、この案内を広く関心のある方々に広めていただければ幸いです。
日時:3月1日(日)13:00~16:30
場所:神戸市勤労会館 307号室
テーマ:「探究的な学びと学校図書館の活用」
内容:講座の目的、計画の概要、諸概念の整理、日程、進め方などについて話し合います。
お問い合わせ、参加を希望される方は下記にご連絡ください。
holisticslinfo#gmail.com (#を@に変えて送信してください)
スタッフ:
足立正治(元甲南高等学校・中学校教諭、大阪樟蔭女子大学非常勤講師)、天野由貴(椙山女学園大学図書館司書)、中津井浩子(甲南高等学校・中学校司書教諭)、山本敬子(甲南高等学校・中学校図書館司書)ほか。
企画・運営:学校図書館勉強会(神戸)
こちらは案内のチラシです。ダウンロードしてご自由に配布してください。
いわゆる「ゆとり教育」批判を受けて2011年に改訂された学習指導要領は、「生きる力」という理念を継承し、「思考力・判断力・表現力等の育成」を掲げて、各教科において基礎的・基本的な知識・技能を習得、活用する学習活動を充実させるとともに、総合的な学習の時間を中心として教科等を横断した課題解決的な学習や探究的な活動を行うことを求めています。そして、総合的な学習の時間の指導にあたっては、「学習過程を探究的にする」だけでなく、「他者と協同して取り組む学習活動にする」ことも求められています(学習指導要領解説 総合的な学習の時間編 学習指導のポイント、平成20年7月、文部科学省)。また次の学習指導要領の改訂では、生徒が能動的に学習活動に参加する「アクティブ・ラーニング」が導入されようとしています( アクティブ・ラーニング次期学習指導要領の主役に / 初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問) )。こうした教育方法革新の要請は、学校図書館の活動とどのように関わるのでしょうか。それを考えるヒントが20世紀初頭に活躍したアメリカの哲学者ジョン・デューイの考え方の中にあります。
デューイは、講義形式の授業によって知識を伝授する、伝統的な教育方法に疑問をもち、生徒が「能動的な活動」や「経験」をとおして学ぶことが必要だと考えて「問題解決学習」を提案しました。経験から学ぶということは、自ら体験したことを振り返って、そこで起こったことの関連性を考えること、すなわち「反省的思考」をおこなうことを意味します。問題解決学習は、子どもが自らの社会生活のなかで抱いた疑問や問題を解決するために、事象間の関連を問い、そこから科学的認識を獲得する「探究」の過程をたどります。デューイは、そのような学習過程を展開する学校の要(かなめ)に「図書室」を位置づけています(『学校と社会』)。デューイにとって図書室は「子どもの経験や疑問、発見などを持ち込んで議論し、書物として集積された他者の経験をとおして理論と実践を有機的に関連させる場所」であり、書物は「経験を解釈し、拡充する上で貴重である」としています。
自主講座では、「探究」をキーワードにして、近年、活動理論との親和性も注目されているジョン・デューイの教育観を再検討し、現代の教育課題に応える学びのあり方と学校図書館の関わりを、いくつかの側面から総合的に捉えて探究したいと考えています。たとえば、ひとつは、空間と資料と人が有機的に関わりあう学びの「場所」(知能環境あるいは学びの広場)として学校図書館をどのように整備するか、ふたつ目は、多様なリテラシーの基盤となる情報やメディアのリテラシー(あらゆる形態の情報やメディアを選択、評価、活用する力)をどのように育むか、そして、もう一つは、探究活動を進めていく思考と感性をどのように培っていくか。
「いかに教えるか」ではなく、子どもの学びに寄り添うことを軸にして、皆さんの経験を持ち寄って、実際に生徒の意欲を掻き立て、気づきや学びをもたらした経験や、逆に生徒の意欲を削いだり、失敗した経験なども話し合いたいと思います。具体的な実践知を共有することで、探究的な学びに関わる教師及び学校図書館職員の能力開発や司書教諭のリカレント教育のプログラムを提案することができればいいと考えています。職種や経験を問わず、私たちの試みに賛同して能動的に参加してくださる皆さんのお越しをお待ちしています。