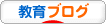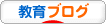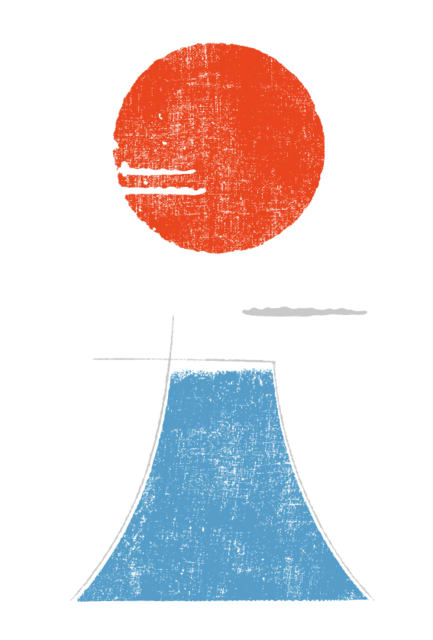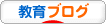

台風の季節も過ぎて、このところ、めっきり秋めいてきましたね。
今回は、少し前にフェイスブックに投稿した内容をもう少し詳しく書いたものを、久しぶりにブログに掲載することにしました。
秋のお話しといえば、「ごん狐」がよく知られていますね。
子どもたちに読んであげる機会も多いのではないでしょうか。
いたずら好きの子ぎつね「ごん」が、自らの行動を振り返り、反省を繰り返しながら一人前の大人として成長していくお話かと思いきや…思いがけない衝撃の結末が待っているという、お馴染みの作品ですが、内容に違和感があって、ぼくは、どうも好きになれませんでした。
周知のとおり、一般に流布され、教科書にも掲載されている「ごん狐」は、新見南吉が「紅い鳥」に投稿した「権狐」を、鈴木三重吉が近代文芸の作品として洗練された表現に書き換えて掲載したとされています。以前からそのことが気になっていたので、先日、近くの図書館に行ったときにたまたま目についた『校訂新見南吉全集』(大日本図書)の第10巻を借りてきて、「スパルタノート」に掲載されている原作を読んでみました。
すると、冒頭に茂助じいさんの人となりや筆者との関係など、物語の展開に直接的に関係がないと思われることが詳しく書かれていたり、「背戸口」や「ちがや」といった、今の子どもたちに馴染みのない風物も出てきて、たしかに、書き直された「ごん狐」のほうが子どもたちにも読みやすくなっていることが分かります。でも、その一方で、ぼくが「ごん狐」で腑に落ちなかった個所については、原作に書かれていなかったり、別の言い回しになっていて、ずいぶん違った印象を受けます。それに、書き言葉としては冗長と思われる文体も、これを口承という視点でとらえると、つまり目の前の聴き手に語っている場面を想定すると、かえって自然で、生きてくるようにも思えます。
そこで、ここでは「ごん狐」で違和感のあった個所をいくつか取り上げて、原作の「権狐」と比べてみようと思います。(一般に流布されている書き換えられた「ごん狐」は、青空文庫に掲載されています)
まず、兵十が捕った魚を川に捨てて逃げてきたごんが、首に巻き付いた「うなぎの頭をかみくだ」いてはずしたとか(一)、魚屋から盗んだいわしを兵十の家に投げ入れたごんが「うなぎのつぐないに」いいことをしたと思った(三)などといった表現は原作「権狐」には出てません。「うなぎの頭をかみくだ」かなくても鰻を首からはずすことはできたかもしれないのに、どうして、わざわざ原作にない内容を付け加えたのでしょう? 同じように、原作の権狐は、ただ、ばくぜんと「何か好い事をした様に思へ」ただけなのに、あえて「つぐない」をしたいと思ってやったように書き換える必要はあったのでしょうか。たしかに、ごんの気持ちは明確に伝わってきます。あいまいな表現を具体的でイメージしやすい表現に書き換えることで、めりはりのついた分かりやすい作品になっています。でも、それは、原作に対して、あくまでも一つの解釈にすぎません。このように「分かりやすく」するために、読者をひとつの解釈に導いていくのは、ぼくには「余計なお世話」のように思えます。
他にも、原作の「権狐」が兵十の家に栗や「きのこ」をもっていった個所は、「ごん狐」では「まつたけ」に書き換えられていて、(今のぼくたちから見ると)なにか特別に価値のあるものをもっていったような印象を受けますが、「栗ばかりではなく、きの子や、薪を」もっていった権狐の気持ちは、少し違うように思います。
また、その栗や「まつたけ」をごんがもっていってやっているのに、兵十が神様にお礼を言うなんて「おれは、ひきあわないなあ」(「ごん狐」)と思う場面も、原作では「権狐は、神様がうらめしくなりました」となっています。ここも、権狐は引き合うか引き合わないかといった損得勘定をしたとは言い切れないでしょう。もしかしたら、何もしていないのにお礼を言ってもらえる神様がうらやましくて嫉妬したのかもしれません。
さらに、ごんが最後に栗をもって兵十の家を訪れた場面では、「物置」で縄をなっていた兵十が気づいて、わざわざ「納屋」にかけてあった火縄銃をとってきて火をつけた(「ごん狐」)のは、いかにも不自然ではないでしょうか。兵十がもとから「納屋」で縄をなっていた原作のほうが、すんなりと納得できます。そして、きわめつけは、兵十に撃たれたごんが、「お前だったのか…、いつも栗をくれたのは」と気づかれて、「ぐったりと目をつぶったまま、うなづきました」(「ごん狐」)という箇所です。原作は「ぐったりとなったまま、うれしくなりました」となっています。このときの権狐の気持ちについては、いろいろ考えさせられ、議論を生むところでしょうが、むしろ、それゆえに、ただ「うなづきました」とするよりも、権狐の心情にさまざまな想像を巡らせ、多様で深い読みを促されて、ぼくは好きです。
こうしてみると、ぼくが「ごん狐」が好きになれなかったのは、おせっかいな書き換えのせいではないかと思えてきます。分かりやすい表現にして子どもたちに興味をもってもらおうという意図は分かりますが、あえて原作にないものを付け加えて、一つの解釈に誘導するのではなく、子どもたちが権狐の複雑な心情に寄り添って、それぞれに想像力を働かせて多様な読みができるようにしておきたいというのが、ぼくの想いです。
というわけで、ぼくは、けっして一般に流布して定着している修正版の「ごん狐」を否定するわけではありませんが、新見南吉の原作「権狐」のほうを読み語る試みも、もっと行われるといいなと思った次第です。いずれにしても、このお話しを読み語るときのポイントは、中山という山里の秋の風情と権狐の心の動きを描き分けることで、どこまで聴き手の心に豊かな世界を創出できるかに尽きるでしょう。チャレンジする値打ちはありそうです。
追伸:
参考までに、「権狐」から「ごん狐」への改変の経緯を詳細に分析し、その意義を考察した論文がある。
新見南吉「権狐」論―「権狐」から「ごん狐」へ―(木村功)
掲載誌 岡山大学教育学部研究集録 / 岡山大学教育学部学術研究委員会 編 (通号 111) 1999.07 p.1~10
この論文によると、改変の要点は、時代性・地域性の削除、語句の平易化、「語り手」の消去、「贖罪」の強調であり、それによって、現在、一般に流布している「ごん狐」は、口承の影響を残す新見南吉の「権狐」を、鈴木三重吉が近代的な物語性をもった文字テクストへと変換させたものである。その結果、「ごん狐」は、鈴木三重吉の意識とは別に、全国規模の出版網をとおして流通性を高め、不特定多数の読者によって物語が広く消費されることに貢献したという。これは、出版資本主義の趨勢の帰結するところであり、1904年に標準語が東京中流社会の言語であると規定されたことと相まって、共通性・普遍性を指向する「国語」の標準を保持する近代文芸テクストとして、新しい小国民の創出に関わったという。
わたしは、この論旨に同意するとともに、こうして原作とは異なる価値をもつ作品へと改変された「ごん狐」が、いまだに新見南吉・作とされているところに、わたしは違和感を覚えるのである。正確には、「新見南吉・原作、鈴木三重吉・改編」と表示されるべきであろう。その上で、わたしは、あえて、地域性の削除、語句の平易化、「語り手」の消去、「贖罪」の強調とは異なる価値観をもつ、口承文芸としての「権狐」を、あらためて評価しなおし、「近代的な物語性をもった文字テクスト」である「ごん狐」とともに読み継いでいこうというのが、わたしの提案である。