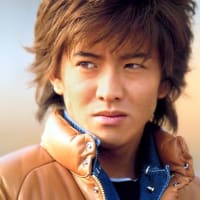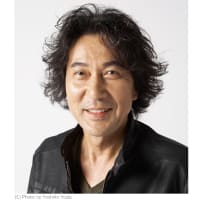「寄せるアジング」編
どうも、フィネス?Mキャロ?いやいや、常に我道を行くマイアジングですw。最近になり自分の真髄するようなものが出来上がってきました。少し長めの文章だけど、まーよそのアジングブログとは違う内容だから見てもらえると良いかな・・・。
いや、ほとんど釣りと無縁の日々だったのでリハビリがてら、マザコンI(友人)と暴風アジングでガチ勝負。結果、ボーズと3匹で惨敗www。
しばらくアジングをやらなかった・・・・マザコンIが豆アジを3匹釣って調子にのる。
ムカついたので2日目はなんとか自力で4匹釣る。
最後の3日目は、感覚を取り戻してきた、全盛期には及ばないが調子に乗って19匹の釣果となった!いやはやシッカリやってないと感覚鈍るものね。頑張ったお陰で、また前アタリの捉え方を思い出せました。
最近、思うのはアジングは、決められた暗号を解読することと似ていると思う。
言っている意味の分からない人もいるかもしれないが、アジが「ワームを口に入れて吐き出し」をするという行為までに、捕食スイッチが入らないといけない。
無論、フィネスフィッシングにしても、キャロにしてもプロによって現在どっちのほうが釣れるみたいな賛否両論があるんだろうが、これら魚の居場所や状況に応じて暗号は変わるものだ。
重要なのがアジ単体の捕食スイッチを入れるよりも、アジの群れとしての全体の捕食スイッチを入れるという事であるといえる。全体像をとらえるということ、その重要性にどれだけの人が気付いているだろうか?
群れスイッチと固体スイッチは違う。
たとえば、トップウォーターで活性を上げて、ミノーやワームで釣るという釣りや。また、普通のバイブレーションの後に、シリコン製のバイブレーションを使ってスレた固体を寄せて釣るという釣りは「群れスイッチの釣り」である。
それと、僕がジグヘッド単体の釣りを推奨しない理由は、大きく2つあります。
まず、これから秋~冬にかけては確実に暴風期にあたりハードフィッシングな日が続くと推測できる。こういう日にジグヘッド単体の釣りはよっぽどの好条件フィールドでなければほぼ通用しなくなる。
2つ目は、アジの群れは足元付近がスレてくると沖へ沖へと群れの固定位置を変え続ける習性があり、飛距離のあるキャロアジングは一つのアドバンテージである。無論、群れスイッチにおいて「釣られるという現象」はスイッチのOFF以外なにものでもない。
私の使用する自作キャロは確実に接近戦の釣りをものにしており、Mキャロのように飛距離ばかりを意識したキャロとはモノが違うのからだ。むしろ、私の場合、JH単体を使用するよりもアタリが分かりやすいのだ。これは私のタックルバランスの影響もあるかもしれないが、前アタリを増幅する仕掛けを凝らしている。
話を群れに戻すが、アジの群れは2タイプが存在する。
釣れる場所で釣るというだけのアジングは応用力が期待できないでしょう。じゃー魚影が薄いアジングエリアではどうすればいいか?
今、開発中の「寄せるアジング」です。確かにガルプ臭や撒きエサを使用して寄せる事もあるかもしれませんが・・・しかしながら、不完全です。
嗅覚に頼る「寄せる釣り」は嗅覚自体の順応が早い事から不完全な釣りと言わざるおえない。かと言って、視覚による寄せる釣りでは「見切り」という現象が発生します。
視覚でもなく、嗅覚でもなく、魚を寄せる。群れへのアプローチ方法を考える。
シーバスとアジングの最大の戦略的違いはここじゃないかな。シーバスはまずは一匹釣ることから開始するんだろうけど、アジングの場合は1匹釣っていかに連荘モードを続かせるかが大事だからね。少しでも気を抜いたら、簡単にスレてしまうからね。
アジのボイルが「至るところ」から聞こえるというシチュエーションは、ある意味パラダイスに見えるかもしれません。しかし、アジンガーにとって実はそうではなく。魚が群れとなっていない事の現れです。
至るところからボイルが聞こえる=アジが広範囲に散っている=1匹釣ると全体が散る、ドリフトができない
限られた範囲内でボイルがある=アジが群れとなっている=大きな釣果が期待できる
これに気付いたアジンガーは果たして何人いるでしょうか?
アジングにおいて、ごく限られた範囲にボイルが集中している事、これが「群れスイッチ」が入っている状態と言えるでしょう。ではそのアジの操作術とはいかにしてやるべきか?
本題はそこです。トレース方向や角度の戦略が一番重要になるのですが、水面下の群れの動きをイメージしささいなんて言っても、なかなか難しいでしょう。大事なのはボイルが出ているところが、群れの角のような部分で、それを立体的に捉えて、そのステイしている群れの規模を推測し、端から釣り上げて、ヒット後はすぐに群れから離して上げることなのです。
「魚を寄せる」という観点で臭いは強力な武器ですが諸刃の剣のような部分もあり、「臭い」なんてのは分散して、流れにのって潮下に消え、群れが潮下へと移動してしまうことから、群れスイッチに対しては逆効果になる。
アジの単体スイッチが入ったとしても、群れスイッチが入らないとアジングの持ち味は消えてしまうし、一定以上の数量より上を目指す事は難しいでしょう。何度も言いますが、アジングの面白さは、何匹も連続して釣れるという状況にこそあります。大きなアジを釣ることにあらず。大きな魚を釣りたいなら最初からシーバスを狙えば良いのであり、そこは次元の違いがある。
しかしながら、アジングでのナーバスなシーンを振り返ってみると、それは釣り人の技量というよりもアジ自体が群れ化していない事に原因がある。今、タックルバランスだのメーカーのロッドを使えだのウンチクを語る胡散(うさん)臭いネタの出しあいこをしている人間は、ほとんど「群れ化」の話題が無いのは、本当にアジングを理解しているのかと思う事がある。
それはアジ同士が頭を向かいあっているような「サークル」とよばれる群れの形態時と、対極にあるアジの写真で同じみの一定方向に頭を向け、ピッシと整列してならぶ「列」と呼んでいる群れだ。アジをいかにして「列」の群れと化させるか?群れスイッチの入れ方を模索しています。
どんな地域へ行ったとしても通用するアジングの確立です。口ばかりの嘘八百ならべても仕方ないでしょう。本当の実力を隠して、実は金儲けが先手先手をきっていたのでは、釣り人として終了です。フィネスフィッシングなんてのは不要でしょう。サークル状態のアジを離島まで行って1匹釣れてOKみたいなのはアジングのようでにアジングに有らずと私は考えます。
ある日、お寿司屋さんでアジの泳ぐ姿を観察していた時のこと。知っている方も多いかもしれませんが、お寿司屋さんで泳ぐアジ達は群れ化していません。サークル状態です。
なぜ群れ化しないのか?
なぜ群れ化が起こるのか?
「魚はなぜ群れるのか?」
どうすれば、列となるか?
そんな疑問をもっていたある日、飼っていたアジ1匹が自作したルアーを追従してついていく。すると、よそ見をしていた2匹、3匹が釣られるように先導した1匹に追従し、やがて全体がそれについていくようになっていったのである。
その時、列が出来たのである。
スクール → 列 へ。
群れの形態は変化し、その些細な発見は、私にとあるアルゴリズムを天から授かるまでに至ある。独自のアジングは進化した。
スクールから列に変化する要点は、「1匹の先導」ともう一つは潮の流れである。
が、潮には大小の変化が存在し、変化なきときに群れ1匹の先導を作る事が重要なのです。メタルバイブのブルブル波動後にリアクションバイトをすると説いたレオン先生ですが、
「ゴメンなさい!!!レオン先生の仮説に反する仮説を提唱します!!!!!」
メタルバイブで思わず口を使って釣れているのではなく、むしろメタルバイの振動により、1匹の先導(アジ一匹がサークル化している群れから飛び出て、2匹、3匹がそれに追従する)が起こり、小さな列状態が起こる。列状態になれば、たとえ潮止まりでも固体の活性は上がり結果、バイトが起こる。
何か、リアクションバイトって、アジ単体の角膜反射(思わず口を使う)っぽい捉え方だったけど。最近、どうも違うのでは?と思うようになった。
動物にとって「捕食」という行為には常にリスクが存在する。それのリスクを下げる意味で群れになることで自分が食われる確率は下がる。つまり群れになることでボイルが起こるのはある意味、理に叶った生命として当然の反応である。つまり、アジにしてみても単体と単体の距離が短くなれば、単体同士の活性は上がる。
群れが密集(列化)すれば捕食は活性化し、群れが拡散(サークル化)すれば群れの低活性となる。単体と単体の距離が縮まることで群れの活性があがる。それがバイトとして現れる。つまり、魚にはリアクションバイトなどと呼ばれるものはなく、単体の距離間を縮めることでバイト反応が生理学的な観点から誘発されているのではないかということだ。
これをカポコンのアジング第22法則に名付けます、別にアジでなくても魚であれば固体選ばず応用できると思います。
「群れアジング」への第一歩。いや、・・・これからの釣り。私カポコンの釣りです。
最近になり、キャロにアジが付いてくる習性があり、またキャロの色を変えると途端に無反応になったり、活性があがったり、2匹が追従するようになったりと・・・複数のキャロを将棋の駒のように使いわけてアジの群れを操作できないかと考えています。色々やってますねw。
何と言っても僕はキャロこそアジングと考える人間ですからw。ただしMキャロは絶対に使用しませんがね。
水面下にいる見えない魚をどのように列にするかって、アジングはなぜナイトゲーム有利といわれるのか?それについても明確な答えや仮説をしめしているプロはいない。ボクとしての仮説は、ズバリ、デイのほうがスクールとしての群れしか作っていないからだ。
だから、逆にレオン先生と重見が行った南の島でのデイアジングでは「列」としての群れがデイでも成立しており、入れ食いアジングとなる。だが、スクールとしてのアジングをレオン先生は説いたかったのだろうが、魚の群れに関する部分がまだ不明なところがあり、フィネスだの何だのと道具や志向にこだわってきたのだと思う。
ボクの場合は、そのような「道具が悪い」という考えもあるにはあるんだけど、どちらかといえば「全体」を見る事に意識している。それは自分が使用しているタックルはもとより、ラインや天候、釣りの状況、群れの活性度合い、アジの学習度合い、特にアジの学習度合いについては重要で、秋に豆アジが釣れないなんていうのは嘘で豆アジが前アタリを学習したての頃だからである。「前アタリ」は人間によって作られるのだ。
「全体」が見えれば、自分が何をすべきかが分かるし、問題点も把握できる。
このレベルに到達するには基礎をとにかくシッカリしていないと難しいんだけど、
寄せるアジングは「スクール」から「列」への陣形誘導釣法なのだ。
「ハゲingとアジing」編
昨年、ショア(岸)から釣った1枚。2007年5月のこと、今から3年も前のことだ。気付けばこのブログは自分史のようになっており、良かったなぁと思う。
当時、メバルのボトムポンパリングが盛んに言われ、アジも結局、レオン先生は底取り、底取りネタばかりを言ってたんだけど。メバルのポンパリングで釣り上げ、さらに再現性まであった初冬のこと。
あれ以来、カワハギの仕掛けにある集魚効果というネタをアジングでも応用してきたんだが、今度はアジングで練り上げたネタをカワハギでも逆輸入化したくなってきたw。
では、皆さんのアジングはアジングで楽しんでください・・・私は私の道を進みますよ。また~♪
アジング界の海軍大将より
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
←アジングファイトクラブDB(データベース)
ポチっとお願いします。
また明日「アジダス」。
あの「めばるing」のレオン先生も使用しているガルプワーム。これの入れ物は↓コレだ!
nalgene(ナルゲン) 広口ジャー30ml 90511
GENTOS(ジェントス) エクスプローラープロフェッショナル EX-777XP
EG-24 EVA丸水汲バケツ 24 青 075020
















![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/55/43/ba1ded3e191d49aad1324caaa9caa4f5.png)
![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4f/e6/cc248e15d0cc66086dc333a11372781e.png)
![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3b/3f/256d7992d774db4a1dbb49e7e2bf1676.png)
![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/75/5c/79f6bd541be9f49aa3c9cdd07b7e1fce.png)