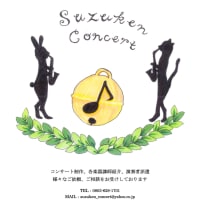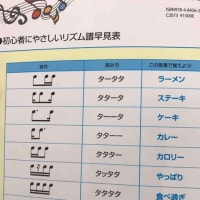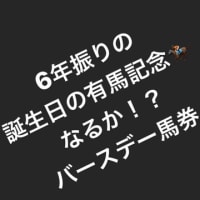昨日は、金曜日の岩本ゼミのコンサートで編曲したヴィヴァルディの「四季」より『夏』を演奏していただく[カルテット・レピス]の練習にお邪魔し、最終チェックをしました。
ソプラノとアルトは当たり前のようにフラジオが、ブレスもする所が極端に少なく全体的に終始ダブルタンギングが必要とされる中、元々ヴァイオリンコンチェルトの曲をサックス4本で奏でることへの挑戦。
一昔の自分だったらこんなアレンジはできなかったと思います。
音の厚みが薄くなる、音が足りない。
メロディーを各パートに回すということへの抵抗もありました。
オリジナルのイメージばかり先行してしまっていましたし。
それらを大事にしながらサックスの良さを出すという発想を持たせてくれたのは[カルテット・レピス]です。
難しい事を考えるのではく、シンプルに。
やってみたら感触も悪くなく、それもアリか!!
自分の中で幅が広がりました。
おかげで服部先生、岩本先生からは太鼓判をいただき残りの3曲もやる事にしました。
昨日は何度も無理難題な注文をしたり、困らせた部分も多々あったと思いますがカルテットが一つになって取り組んでくれました。
一人ひとりの技術というのは様々だと思います。
門下も、やっていることも、考えも皆違います。
それを時間と労力と気持ちを使って4人が1つになるというのは計り知れないものがあると思います。
それぞれがそれぞれの役割を理解して、その役割を高レベルでこなす。
カバーし合うのではなく刺激し合い互いを高めていく、それが「レピス」なのかな。
これがカルテットの良さなのかなと思いました。
ソプラノとアルトは当たり前のようにフラジオが、ブレスもする所が極端に少なく全体的に終始ダブルタンギングが必要とされる中、元々ヴァイオリンコンチェルトの曲をサックス4本で奏でることへの挑戦。
一昔の自分だったらこんなアレンジはできなかったと思います。
音の厚みが薄くなる、音が足りない。
メロディーを各パートに回すということへの抵抗もありました。
オリジナルのイメージばかり先行してしまっていましたし。
それらを大事にしながらサックスの良さを出すという発想を持たせてくれたのは[カルテット・レピス]です。
難しい事を考えるのではく、シンプルに。
やってみたら感触も悪くなく、それもアリか!!
自分の中で幅が広がりました。
おかげで服部先生、岩本先生からは太鼓判をいただき残りの3曲もやる事にしました。
昨日は何度も無理難題な注文をしたり、困らせた部分も多々あったと思いますがカルテットが一つになって取り組んでくれました。
一人ひとりの技術というのは様々だと思います。
門下も、やっていることも、考えも皆違います。
それを時間と労力と気持ちを使って4人が1つになるというのは計り知れないものがあると思います。
それぞれがそれぞれの役割を理解して、その役割を高レベルでこなす。
カバーし合うのではなく刺激し合い互いを高めていく、それが「レピス」なのかな。
これがカルテットの良さなのかなと思いました。