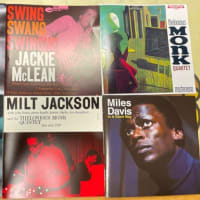きょうされん関係
【青森】…県内加盟作業所16カ所のうち、まだ2カ所と連絡がとれていません。
【岩手】…昨日16時現在、県内加盟作業所13カ所すべての作業所と連絡がとれています。やまだ共生作業所の職員の弟さんからメールが入りました。所長さん他、無事だそうです。
【宮城】…はらから福祉会に支部事務局機能を担っていただくことになり、安否確認を進めることになりました。はらから福祉会以外の施設では、県内加盟作業所22カ所のうち、まだ8カ所と連絡がとれていません。
【福島】
新たに1カ所からファックスで連絡が入りました。全員無事で、建物への被害もなかったそうですが、まだ水道が止まっているそうです。関係者の方が、これまで未確認であった施設の確認に行ってくれたとメールが入りました。建物の外観の損傷はなかったそうですが、人の気配はなく「しばらくお休み」の貼り紙がされていたそうです。県内加盟作業所35カ所のうち、前述の作業所を含めてまだ12カ所と連絡がとれていません。
【茨城】…昨日に引き続き、県内加盟作業所8カ所のうち、まだ2カ所と連絡がとれていません。
きょうされん以外で状況が聞けたところ
大阪社保協「ホームヘルパーのつどいin大阪」における記念講演、篠崎良勝准教授(八戸大学人間健康学部…青森)のメッセージ
生き続ける大切さ
今、八戸市・三沢市・おいらせ町は東北関東大震災の影響により、生活支援が必要な状況となっています。岩手県・宮城県・福島県・茨城県の沿岸で避難生活をしている方に比べれば、たいしたことないだろうと思って大阪から帰りましたが、生き続ける大変さを感じています。
私も今朝は朝3時からガソリンスタンドに並んでいます。首都圏と違い、車が無ければ何もできない生活圏がここにはあります。数量制限でようやく10㍑のガソリン入れても、スーパーにはお米がなく、24時間365日営業のコンビニも無期限休業です。
つまり、一人一人が生きるために必死で、ボランティアに入りたくても入れない状況が実はあります。
また介護では、小さなデイサービは送迎のガソリン不足で閉鎖されています。ヘルパーさんも通勤ができず、訪問介護もかなり制限されています。街全体としては、死ぬような追い詰められ感はありませんが、地域の子供たちが「おにぎり・カレーライスが食べたい」としても、スーパーには菓子類しかありません。大人は、仕事しながら生活物資を調達するのは不可能に近いです。私もそんな中の一人です。つまり、生活水準が一気に低下した中で、みんなが一分一秒が息を詰めながら暮らしている感じです。
この地域で今、本当に必要なのは、物では、やはりガソリン・灯油・お米・トイレットペーパーあたりでしょう。
でも、物資と同じくらい応援が欲しいです。生きる勇気、誰かに見守られている安心が欲しいです。いつでも「助けて」と言えば、「どうしたの」と声をかけて、共感してくれる人が必要です。ガソリンスタンドで並んでると、ガソリンスタンドの人が「長い間お待たせてしまい申し訳ありません」と言えば、並んでいる人も「なんも、こっちこそ有り難い」と話している様子(私も同じ)は、みんなで頑張っていこうというエール交換に感じます。
らく相談室 池添 素さん
「子どもたちにケアを」
「「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク」のメーリングリストに以下の内容のメールが流れました。阪神大震災での経験から被災した子どもたちへの早い段階からの心のケアが必要だと呼びかけられています。大切な内容なので引用させてもらいます。
以下メールより
そこには、「こんなときではありますが、子どもたちには、どうぞ遊びと笑いを大切にしてください。深刻な顔での大人同士の立ち話に子どもたちは耳を傾けています。深刻な映像を説明なく見せすぎないようにしてください。凄惨な映像を繰り返しみることで、子どもの恐浮ェ増します。被災の状況よりも、次におきたときにどうしたらいいかをあわてずゆっくりお話してください。一緒に避難グッズをそろえるのもいいかと思います。心の中に焦りがあってもゆっくりと一緒にどうして必要か説明しながら。浮ェる子どもは、どうぞ抱きかかえて、浮ゥったね、と気持ちを受けとめた上で、逃げる手順をゆっくりゆっくり話して大丈夫よ、と伝えて下さい。子どものゆれへの恐武Sが強くなれば、再び地震がきた際に、パニックになってあらわれます。いざというとき落ち着いて動けるように。恐ろしい映像でいたずらに脅かさないように。枕元にはヘルメットと防寒具を置きね、これだけ備えていれば大丈夫よ。と、伝えて下さい。安心して、たくさん、ぐっすり眠れるように。どんな時でも、子どもたちの中にある遊びたい気持ちを自粛させることはありません。こんなときだからこそ、安全に配慮しながらもしっかり遊ばせてください。そして大人の笑顔を見せてあげて欲しいと願います」
私が上海で飛行機に閉じ込められた時の障害のある仲間のパニックに対応した経験からも、被災地の障害のある子どもたちが直面している困難を想像します。しかし、被災地だけでなく、日本全国の子どもたちへの配慮も必要だと感じています。
たぶん、被災地よりそれ以外の地域のほうが情報をたくさん得ていると思います。次々と途切れることなくテレビから流れる地震被害の映像、子どもたちがいつも見ている番組はなく、地震災害関連の報道番組一色です。予想を超える大地震ですからもちろん仕方がないことですが、子どもにとっては不安や不満も高まります。
いつもより我がままや甘えたになったり、言うことを聞かなかったり、抱っこをねだったり、一緒に寝てほしいということがあるかもしれません。いつもできていることだからと頑張らせるのではなく、不安な子どもの気持ちに寄り添ってあげることが必要だと思います。そして、障害のある子どもはもっと不安な気持ちになっていることだと思います。大人はニュースを見たいところをちょっと我慢して、好きなDVDを一緒に見たり、できるだけいつもと同じ暮らしができる配慮が必要ではないかと思います。
地震が起こってからの毎日、悲惨な情報に大人も言葉を失っています。子どもたちはもっと敏感に受け止めていると思います。
ぜひ、多くの子どもにかかわっている方や家庭での子育てに生かしていただけたら嬉しいです。
最新の画像もっと見る
最近の「日記・日常」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事