諏訪のほうではミシャグチ神、ミシャグジさまという神様が有名です。
最近古代のことをいろいろ調べていたことで、
前に比べて神様や古代のことに一段階理解が進んだので
ミシャグチ様についても考えてみました。
一般的な名称として『ミシャグチ』『ミシャグジ』を考えると、
後ろの『チ』と『ジ』が違います。
この特徴は、最近の研究成果により、
蛇系の名前にありがちだとわかりました。
たとえば、『ヤマカガチ』と『ヤマカガシ』は同じものです。
とすると、『ミシャグチ』『ミシャグジ』は『ミシャグ蛇』となり、
神様の本体は『蛇』と考えられます。
そこでミシャグチ様を調べてみると、
蛇神としての神格があるように書かれていました。
よって、おそらく間違いはないでしょう。
ならば、名前の構造から考えて、その前につく、『ミシャグ』は、
神様の姿を形容するものであると推測できます。
蛇の語源は『噛むという動作』なので、
まずはそこらへんから関連語をひたすらあさります。
すると、噛むに関連した、『ミシャグ』という単語を見つけました。
口『噛み』酒をあらわす、『ミシャグ』。方言です。
その他の単語から考えると、『シャグ』は『シャゲ』。
御『シャゲ』のことで、御『酒』を表すようです。
なぜ酒が『サケ』なのかと言うと、
どうも『下げ』ではないかと思います。
口から下に吐き戻す=下げ
噛んだ米を下に吐く=下げ
下げたもの、かつ、神聖なもの→御下げ→御シャグ→御酒
でも、ミシャグチ様の伝説を見る限り、
御酒蛇という感じはしません。
タタリ神で、イケニエを欲する神のように書かれています。
とすると、酒ではなくて、酒の手前、下げの神様かもしれません。
蛇は川にたとえられるので、川が吐き戻すように下げるものが
その象徴だとする可能性はあります。
日本では、川の工事の際や氾濫を沈める際に
生贄を用いることがあったようです。
これは、ミシャグチ様がイケニエを求めるという性質とも矛盾しません。
かつてナイルでは洪水は、恐ろしがられるとともに
ありがたがられていたとのことです。
洪水は時には人の命も奪いますが、
運んできた土砂や水が、豊かな農作物の栽培を助けたからです。
このような、恐ろしくもありがたい川の氾濫を、
蛇に見立てて、『御下げ蛇』様、『ミシャグチ』様と呼び
恐れ敬ったのではないか
とするのが、今のわたしの結論です。
追記:
その後、きちんと研究しなおして、名前の意味と正体が判明しました。
成果は下のものにまとめてあります。
今、この文を見ているその方法で見られます。
・神様よろづごと 1
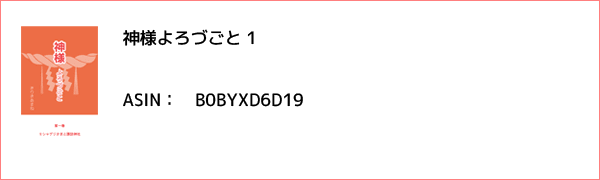
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BYXD6D19
いまこれを見ているその手段で同じく見られます。
中身サンプルはリンク先の左上のボタンから。

























