登った山:観音山(713m )登り尾山(1056.6m)
平成23年3月27日(日)晴/曇り/霰 単独 所要時間:7時間1分 距離:GPSにて計測=13.1km
高度の上昇1016m/高度の下降1017m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
鉢の山側8:41---観音山10:00---石仏群11:03---再び尾根筋に11:26---999m高点13:00---新山峠13:24
---登り尾山13:56---奥原川15:15---鉢の山出発点へ15:38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


本日のログ

高度

観音山石仏群周辺のログ

登り尾山周辺のログ(三角点の位置は上記ログの△地点より左側へ15mmほどの地点)

上佐ヶ野と泉奥原を結ぶ林道の「鉢の山」北側に車を止め、この桧林から観音山、登り尾山を目指します。

3ピーク目の600m地点より653mの頂を望みます。 よく見ると「十郎左ェ門」に似た山です。

653mの頂から西へ延びる尾根筋に踏み込んでしまいましたが、後戻りし観音山の頂に立ちました。(後でログを見ると誤って踏み
込んでしまった尾根を北西方向に進めば石仏群に辿り着けたのでした。kawaさんのログをしっかりとチェックしておけばよかったです。)

下降地点より廃山葵沢の沢に辿り着き、さらに杉林を下ると観音山の石仏群へ至る山道に出合いました。その道に案内され
沢を渡ると、すぐ左側の向岳寺跡に六地蔵が淋しげに並んでいます。一本の杉の生え際に真新しいお菓子袋が置いてあり、
目線を下げた瞬間、左後方に人の気配を感じびっくり! 正体は案内看板でしたが一瞬ドキッとしました。

大きな岩山を削り取った溝に高さ30~40cmのお顔の良い石仏が並んでいます。(下窟側の観音山石仏群)
案内には1735年西国33ヶ所に摸して仏像33体を凝灰岩(沢田石)で造立とあります。今から276年前です。

しみじみと時の流れを感じ入ります。

上窟側には11体が造立されていますが1790年に破損のため12体造立とあります。今から221年前です。

上窟のすぐ上には山上様の祠があり、そこより先ほど通過した尾根筋へ復帰しましたが、途中は岩稜帯で慎重を期し登りあがりました。
そこから北側へ延びる尾根筋を辿りいくつかの小ピークを越え山道らしき踏み跡を横切り1020m地点まで上がります。新山峠へ
の変針点が不明瞭ですがコンパスを登り尾山に合わせ南西方向にくだり999m高点を確認するとすぐ新山峠へ到着しました。

新山峠には先ほどらいから降り始めた霰が白く山肌にかかりはじめています。

新山峠から2ピーク目には背丈が高くなったアセビが密集し始めていました。この登り尾山北側は落葉樹の木々が広がりアオ
スズ台、天城連山を見渡すことができます。

登り尾山には本日先行者がいたようで雪面に泥の付いた踏み跡がくっきりと付いていました。

Y先生と以前登ったとき南斜面のヤマグルマの巨木に案内されました。本日その巨木を15分ほど探してみましたが見当たらず
あきらめ南南東に下りる尾根を林班界に沿って泉奥原方向へどんどんと降下していきます。(写真は860m付近の緩やかな尾根)

地形図には泉奥原へ下りる破線の山道が記されていますが道らしきものはありません。明瞭な尾根筋を下ると横断する山道に
合流し沢を二つ越えると鉢の山へ登る林道の取次ぎに出ることができました。 本日も爽快登山なり。


















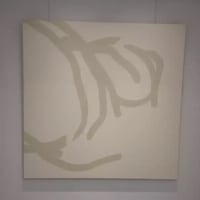
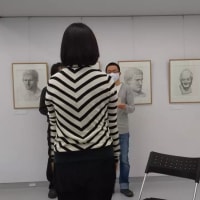








観音山から1020mと 上り尾からの尾根下りは
地図をよく読んでないと考え付かないですね。
そして私だったら迷ってしまいます。
以前このコースを1020m→東の猿山→三筋山
手前展望ピーク→出発点に帰還したことがあり
ますが大変疲れたのをおぼえています。
今回はいたって快調でした。
大人の休日はマンネリで飽きてきたところ
ですがメタポ解消に頑張ろうと思います。