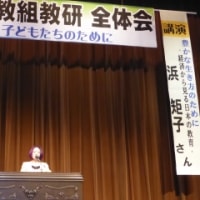11月4日(木)消防組合議会議員の行政視察に参加しました。
まず、大阪府立消防学校を訪問しました。


大阪府立消防学校は、消防組織法第51条に基く消防職員及び消防団員に対する教育訓練施設です。
2007年度から建て替え方式による大阪府の消防学校再整備等事業が進められ、2010年3月に竣工されました。
初任教育として6ヶ月間訓練を受け、前・後期生)になっています。
117人入校中で、内女性が4人現在いるそうです。寮にはいり、休日に帰宅するそうです。
建て替えが行われたので、部屋も簡易個室になっていて、消防署員の人たちが、自分の時と比べておられました。
初任教育の他に、専科教育(救急救命)、幹部教育、特別教育、消防団教育 などが行われています。訓練の卒業前には、火災を消火する実地訓練も行われています。
様々なシチュエーションを想定して、訓練が行われます。
それぞれ消防署に戻っても、日々訓練を欠かさない消防隊や救急隊などに、信頼を寄せ、感謝ですね。
その後は、大阪市消防局に行き、昨年10月に国のモデル事業として大阪市域を対象に開設された「大阪市救急安心センター」を、今年4月1日に「救急安心センターおおさか」と改称して対象地域を大阪府内に拡大されたので、枚方・寝屋川市においても同日から参画しているこのセンターを視察させていただきました。
24時間365日体制で、医師・看護師・相談員が救急医療相談に対応されています。
#7119 がそれにあたります。救急車を呼べばいいのか、どこの医者にいけばいいのか、等など、状況を把握し、対処されています。「助かる命を助けたい!」ということで手遅れを防ぐことが一番の目的です。そして救急車の適切な利用にもつながるわけです。
#8000 の小児医療の相談も含めて、どうすればいいのかわからない時は、電話で相談してくださいね!!
まず、大阪府立消防学校を訪問しました。


大阪府立消防学校は、消防組織法第51条に基く消防職員及び消防団員に対する教育訓練施設です。
2007年度から建て替え方式による大阪府の消防学校再整備等事業が進められ、2010年3月に竣工されました。
初任教育として6ヶ月間訓練を受け、前・後期生)になっています。
117人入校中で、内女性が4人現在いるそうです。寮にはいり、休日に帰宅するそうです。
建て替えが行われたので、部屋も簡易個室になっていて、消防署員の人たちが、自分の時と比べておられました。
初任教育の他に、専科教育(救急救命)、幹部教育、特別教育、消防団教育 などが行われています。訓練の卒業前には、火災を消火する実地訓練も行われています。

様々なシチュエーションを想定して、訓練が行われます。

それぞれ消防署に戻っても、日々訓練を欠かさない消防隊や救急隊などに、信頼を寄せ、感謝ですね。
その後は、大阪市消防局に行き、昨年10月に国のモデル事業として大阪市域を対象に開設された「大阪市救急安心センター」を、今年4月1日に「救急安心センターおおさか」と改称して対象地域を大阪府内に拡大されたので、枚方・寝屋川市においても同日から参画しているこのセンターを視察させていただきました。
24時間365日体制で、医師・看護師・相談員が救急医療相談に対応されています。
#7119 がそれにあたります。救急車を呼べばいいのか、どこの医者にいけばいいのか、等など、状況を把握し、対処されています。「助かる命を助けたい!」ということで手遅れを防ぐことが一番の目的です。そして救急車の適切な利用にもつながるわけです。
#8000 の小児医療の相談も含めて、どうすればいいのかわからない時は、電話で相談してくださいね!!