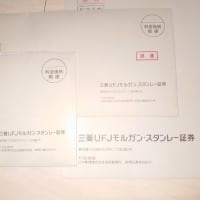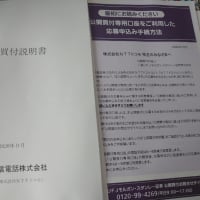| 鉄道業界で水素を動力に活用した車両の実用化を目指す動きが加速している。二酸化炭素(CO2)の排出が抑えられ、脱炭素への貢献が期待できる。国は規制のあり方を検討し、「水素列車」の普及を後押しする考えだ。 「水素を燃料にしたクリーンなエネルギーで走ります」。東京都内で今月上旬まで開かれた「ジャパンモビリティショー2023」。JR東日本の社員が、試験車両「HYBARI(ひばり)」をPRしていた。 車体の屋根の水素タンクから供給した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電する「水素燃料電池」などを動力源とする。軽油が燃料のディーゼル車と異なり、CO2を排出しない。 JR東は、2050年度にCO2の排出量を「実質ゼロ」にすることを掲げ、22年にひばりを完成させた。同社で稼働する約450両のディーゼル車をすべて置き換えると、年間約6万トンのCO2を削減できると試算する。現在、30年の実用化を目指し、神奈川県内の鶴見線や南武線で実証試験を進めている。 ひばりでは走行中の振動や衝撃に耐えられるよう頑丈な水素タンクを使用し、緊急時は外部に放出する機能も組み込み、安全性に配慮している。 走行距離の向上も課題だ。現在は一度の補充で約140キロ・メートルを走るが、実用化までにディーゼル車と同等の300〜500キロ・メートルを目指したいという。 JR東海は、水素を燃やして走る水素エンジンを使った車両の開発を目指すと今月16日に発表した。来年度以降に模擬走行試験を行って性能を検証する予定で、実現できれば世界初という。 普及に向けて欠かせないのが、水素の安定的な供給体制の構築だ。 30年代前半での水素列車の実用化を視野に入れるJR西日本は今年、既存の駅や線路を活用した大規模な水素ステーションを同時期に整備すると発表した。水素の供給や輸送を担う拠点として、兵庫県姫路市にあるJR貨物・姫路貨物駅での設置を計画する。 将来的には自治体や企業と連携し、JRグループの枠を超えてバスやトラック、乗用車への供給も想定。さらに貨物列車を使って各地に水素を輸送しながら、地域一体となって脱炭素の実現を目指すという。 JR東は自治体や企業などとともに水素の利用の取り組みを検討している。 国は、30年代に鉄道分野からのCO2排出量を13年度比で半分以下とする目標を掲げている。 現行法令は、水素を鉄道の動力源として想定しておらず、水素タンクなどは高圧ガス保安法、車両本体は鉄道営業法によって規制がかかっている。水素列車の普及、商用化への足かせになりうるとして、鉄道事業者側には規制の一元化を求める声がある。国側は「今後、規制のあり方を整理、検討しながら、実用化を推進したい」とする。 国土交通省は今月1日、JR7社や私鉄団体、研究機関で構成する水素燃料電池車両の官民連絡会を設置し、初会合を開いた。電池の高出力化や走行距離の延伸などに向け、技術的な課題を共有するほか、国交省が進める制度面の検討状況も定期的に報告する。 水素列車の開発は、昨夏にドイツ北部で本格運行を始めたフランスの車両メーカーを筆頭にスイス、英国、中国などが先行する。国交省の岸谷克己・技術審議官は「海外勢に追いつくため官民で連携し、技術開発や安全性の検証を効率的に進める必要がある」と話す。 鉄道業界の脱炭素に向けた取り組みは、水素列車以外にも広がっている。 西武鉄道は来年1月から、運行する全12路線で使うすべての電力を再生可能エネルギー由来に切り替える。 同社では2年前から、山口線で先行して太陽光発電で生み出した電力で運行。来年1月からは他の11路線でも、風力や太陽光など再生可能エネルギーで発電した際に発行される「非化石証書」付きの電力を購入して使用する。この結果、年間約15万7000トンあったCO2の排出量が、実質ゼロになるという。 JR東海は、ディーゼル車の軽油をバイオ燃料に置き換えることを目指す。すでに紀勢線で本線走行試験を実施。今後も国やJR各社とともに、バイオ燃料の実用性について検証を重ねていく。(読売新聞)/span> |
これ車ではトヨタが製品化して販売していますね。