
“ 今日の会に ふたたびかへらざる事を思えば、実に我 一世一度の会也。 ”
井伊直弼、激動の幕末、幕府大老にして一世の茶人。号をして、井伊宗観と呼ばるる人。
かつての徳川四天王井伊直政を開祖とし、三十万石を領する譜代の筆頭、名門彦根井伊家。
直弼は、その井伊家当主になるまでは、部屋住みの身でした。その間に、直弼は武家の倣いの武道の他に、茶・和歌・鼓なども学び、茶湯は徳川宗家指南であった石州流の奥義を極め、当主になる前年には一派を開いたほどであった。現在でも、彦根一会流としてその流派は伝わっている。
その宗観(以降は、直弼をこう記す)が、大老職に任じられる直前に書いたといわれるものが、今回の『茶湯一会集』である。
『一期一会(1) 入門記・茶湯一会集・茶湯をりをり草』
井伊直弼茶書 校訂解題 井伊正弘・倉沢行洋 燈影舎 1988年
宗観は、茶湯の奥義を石州流祖、さらには千利休に求め、茶湯の新境地を目指すようなものよりは、茶湯の原点・正統を継ぐものとして自身の茶湯を形作っていったのだと思う。
日本の茶湯は、室町時代の村田珠光・武野紹鴎そして千利休へと続く「侘数寄」の形が出来上がり、利休の死後、その茶道を三千家(武者小路千家・表千家・裏千家)が継いだ。
とはいえ、その時々の政権、豊臣・徳川での筆頭茶人としては、利休のあと門人・古田織部正(徳川秀忠の指南)が立ち、そののちは彼の高弟・小堀遠州(家光の指南)、そして片桐石州(家重の指南)と続いた。片桐石州以後、徳川宗家の茶道は石州流となったという。
江戸時代までは、茶湯を学ぶのは、武家・公家、それに豪商といった一部の者たちだけだったが、以降茶湯を学ぶものは増加の一途をたどり、さらに茶湯の流派も数多く増えた。
利休が目指したという侘数寄自体、茶湯の中から変容していた。
上述したが、彼が一派を開いた年に書かれた『入門記』に、
「不得止正流源、及作吾一派。」(止むことを得ず流源を正して、吾が一派を作すに及べり。)
…とあるように、宗観はあるべき茶湯の道を追い求めた。
宗観は、茶会ごとに、器や手前を取り替え、工夫して客に「どうだ、すごいだろう」と思わさせようとすることこそ、不快なこととした。
同じ器、手前であっても、客に相対するごとに 心をひきしめ、もてなすことこそ茶道の大本とした。
宗観の、茶湯の極意「一期一会」である。
「…抑、茶湯の公会は、一期一会 といひて、たとへば幾度おなじ主客交会するとも、今日の会に ふたたびかへらざる事を思へば、実に 我一世一度の会也。
去るにより、主人は、万事に心を配り、聊も麁末なきやう深切実意を尽くし、客にも、此会に 又逢ひがたき事を辨へ、亭主の趣向、何壱つもおろかならぬを感心し、実意を以て交るべき也。
是を一期一会といふ。…」
これが、『茶湯一会集』の序文である。(改行は、読み易い様に、少し変えました。)
ドラマ「篤姫」でも、宗観の「今日の会にふたたびかへらざる事を思へば…」という心得が紹介され、天璋院と井伊大老との茶会場面でナレーションが流れた。
私が、お客様をおもてなしにする際、よくよく心しておくのが、この「一期一会」である。
二度とは、同じおもてなしは、同じお客様であってもできるものではない。
良かれ悪しかれ、お客様と相対するのはその一度一度で異なり、「二度」はない。 だからこそ、心を尽くす。
本を一冊であれ、コーヒーを一杯であれ、牛丼を一杯であれ、同じものを二度はお出しできず、それを楽しんでいただけるよう心を配る。
それが、私にとっての「一期一会」と心得ている。
…また、茶人宗観は、一会集の終りの近くに、
「一。 主客とも、餘情残心を催し、退出の挨拶終れば、客も、露地を出るに声高に咄さず、静にあと見かへり出行ば、亭主は猶更のこと、客の見へざるまでも見送る也。
扨、中潜り・猿戸、その外、戸障子など、早々〆立などいたすは、不興千万、一日の饗応も無になる事なれば、決て、客の帰路見えずとも、取りかた付、急ぐべからず。
いかにも心静に茶席に立もどり、此時、にじり上りより這入、炉前に独座して、今暫く御咄も有べきに、もはや何方まで可被参哉、今日、一期一会済て、ふたたびかへらざる事を観念し、或は独服をもいたす事、是、一会極意の習なり。
此時、寂莫として、打語ふものとては、釜一口のみにして、外に物なし。 誠に自得せざればいたりがたき境界なり。…」
…と記しており、「独座観念」 の極意を述べている。
一期一会にしろ、独座観念にしろ、宗観の独創ではなく茶の先人らによって到達されたものではある。
しかし、当時すでにそういったことが等閑にされる風潮があればこそ、宗観によって改めて提唱されたものだろう。
言い換えれば、建前のみにてあった、のではなかろうか。
面白いのは、ここまでの大茶人が、政治に携わっていた、ということである。
よく、政治家にも「心」が必要だ、という趣旨のことが取り沙汰される。非情な采配を取ったりなどすると、指弾され批難される。
しかし、マックス・ヴェーバーが言うように、「善い目的」のためには、先ず、いかがわしい・危険な手段を用いなければならず、政治にとっての決定的な手段というのは、「暴力」である。
国政の指導者である宗観、大老・井伊直弼にとっては、譜代筆頭という立場から、国家の最高府としての徳川幕府の維持と存続こそが「善いもの」であり、それを覆そうとする動きは処断せねばならないものであったろう。
また、老中を暗殺しようとした軽輩や諸外国と開戦させようとする密勅などに対し、厳しく臨んだのは、国政指導者ならば当然とはいえないだろうか。
そう考える私にとって、井伊直弼をして、
「徳川宗家を護る」
「帝に近づくために 攘夷攘夷 と口にする、さまで 卑怯な者たちに この国の行く末を任せられましょうや」
「愚劣な輩からこの国を護るため、恨みを買うこともやむを得ず」
そして、「私は己の役割を果たしたまで」とまでも言わせたドラマ「篤姫」。
観ていておもしろいのも、当然なのかもしれません。
( 2011/01/01 誤字、改行など訂正 )
井伊直弼、激動の幕末、幕府大老にして一世の茶人。号をして、井伊宗観と呼ばるる人。
かつての徳川四天王井伊直政を開祖とし、三十万石を領する譜代の筆頭、名門彦根井伊家。
直弼は、その井伊家当主になるまでは、部屋住みの身でした。その間に、直弼は武家の倣いの武道の他に、茶・和歌・鼓なども学び、茶湯は徳川宗家指南であった石州流の奥義を極め、当主になる前年には一派を開いたほどであった。現在でも、彦根一会流としてその流派は伝わっている。
その宗観(以降は、直弼をこう記す)が、大老職に任じられる直前に書いたといわれるものが、今回の『茶湯一会集』である。
『一期一会(1) 入門記・茶湯一会集・茶湯をりをり草』
井伊直弼茶書 校訂解題 井伊正弘・倉沢行洋 燈影舎 1988年
宗観は、茶湯の奥義を石州流祖、さらには千利休に求め、茶湯の新境地を目指すようなものよりは、茶湯の原点・正統を継ぐものとして自身の茶湯を形作っていったのだと思う。
日本の茶湯は、室町時代の村田珠光・武野紹鴎そして千利休へと続く「侘数寄」の形が出来上がり、利休の死後、その茶道を三千家(武者小路千家・表千家・裏千家)が継いだ。
とはいえ、その時々の政権、豊臣・徳川での筆頭茶人としては、利休のあと門人・古田織部正(徳川秀忠の指南)が立ち、そののちは彼の高弟・小堀遠州(家光の指南)、そして片桐石州(家重の指南)と続いた。片桐石州以後、徳川宗家の茶道は石州流となったという。
江戸時代までは、茶湯を学ぶのは、武家・公家、それに豪商といった一部の者たちだけだったが、以降茶湯を学ぶものは増加の一途をたどり、さらに茶湯の流派も数多く増えた。
利休が目指したという侘数寄自体、茶湯の中から変容していた。
上述したが、彼が一派を開いた年に書かれた『入門記』に、
「不得止正流源、及作吾一派。」(止むことを得ず流源を正して、吾が一派を作すに及べり。)
…とあるように、宗観はあるべき茶湯の道を追い求めた。
宗観は、茶会ごとに、器や手前を取り替え、工夫して客に「どうだ、すごいだろう」と思わさせようとすることこそ、不快なこととした。
同じ器、手前であっても、客に相対するごとに 心をひきしめ、もてなすことこそ茶道の大本とした。
宗観の、茶湯の極意「一期一会」である。
「…抑、茶湯の公会は、一期一会 といひて、たとへば幾度おなじ主客交会するとも、今日の会に ふたたびかへらざる事を思へば、実に 我一世一度の会也。
去るにより、主人は、万事に心を配り、聊も麁末なきやう深切実意を尽くし、客にも、此会に 又逢ひがたき事を辨へ、亭主の趣向、何壱つもおろかならぬを感心し、実意を以て交るべき也。
是を一期一会といふ。…」
これが、『茶湯一会集』の序文である。(改行は、読み易い様に、少し変えました。)
ドラマ「篤姫」でも、宗観の「今日の会にふたたびかへらざる事を思へば…」という心得が紹介され、天璋院と井伊大老との茶会場面でナレーションが流れた。
私が、お客様をおもてなしにする際、よくよく心しておくのが、この「一期一会」である。
二度とは、同じおもてなしは、同じお客様であってもできるものではない。
良かれ悪しかれ、お客様と相対するのはその一度一度で異なり、「二度」はない。 だからこそ、心を尽くす。
本を一冊であれ、コーヒーを一杯であれ、牛丼を一杯であれ、同じものを二度はお出しできず、それを楽しんでいただけるよう心を配る。
それが、私にとっての「一期一会」と心得ている。
…また、茶人宗観は、一会集の終りの近くに、
「一。 主客とも、餘情残心を催し、退出の挨拶終れば、客も、露地を出るに声高に咄さず、静にあと見かへり出行ば、亭主は猶更のこと、客の見へざるまでも見送る也。
扨、中潜り・猿戸、その外、戸障子など、早々〆立などいたすは、不興千万、一日の饗応も無になる事なれば、決て、客の帰路見えずとも、取りかた付、急ぐべからず。
いかにも心静に茶席に立もどり、此時、にじり上りより這入、炉前に独座して、今暫く御咄も有べきに、もはや何方まで可被参哉、今日、一期一会済て、ふたたびかへらざる事を観念し、或は独服をもいたす事、是、一会極意の習なり。
此時、寂莫として、打語ふものとては、釜一口のみにして、外に物なし。 誠に自得せざればいたりがたき境界なり。…」
…と記しており、「独座観念」 の極意を述べている。
一期一会にしろ、独座観念にしろ、宗観の独創ではなく茶の先人らによって到達されたものではある。
しかし、当時すでにそういったことが等閑にされる風潮があればこそ、宗観によって改めて提唱されたものだろう。
言い換えれば、建前のみにてあった、のではなかろうか。
面白いのは、ここまでの大茶人が、政治に携わっていた、ということである。
よく、政治家にも「心」が必要だ、という趣旨のことが取り沙汰される。非情な采配を取ったりなどすると、指弾され批難される。
しかし、マックス・ヴェーバーが言うように、「善い目的」のためには、先ず、いかがわしい・危険な手段を用いなければならず、政治にとっての決定的な手段というのは、「暴力」である。
国政の指導者である宗観、大老・井伊直弼にとっては、譜代筆頭という立場から、国家の最高府としての徳川幕府の維持と存続こそが「善いもの」であり、それを覆そうとする動きは処断せねばならないものであったろう。
また、老中を暗殺しようとした軽輩や諸外国と開戦させようとする密勅などに対し、厳しく臨んだのは、国政指導者ならば当然とはいえないだろうか。
そう考える私にとって、井伊直弼をして、
「徳川宗家を護る」
「帝に近づくために 攘夷攘夷 と口にする、さまで 卑怯な者たちに この国の行く末を任せられましょうや」
「愚劣な輩からこの国を護るため、恨みを買うこともやむを得ず」
そして、「私は己の役割を果たしたまで」とまでも言わせたドラマ「篤姫」。
観ていておもしろいのも、当然なのかもしれません。
( 2011/01/01 誤字、改行など訂正 )










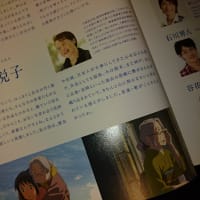
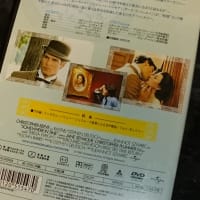

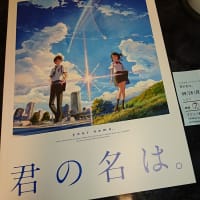






 Name; Melville
モットーは「Bygones!」
JAPAN辺境四国在住。
Name; Melville
モットーは「Bygones!」
JAPAN辺境四国在住。




