
8月23日(土) 講師 春山 進 先生
モリ供養は庄内地方に古くから伝わる死者供養の行事で8月22日~24日頃に行われる。「もり」「もりのやま」とも呼ばれ、死者の霊がこもる霊地のことも指している。庄内一円の寺や神社で受け継がれているが、本講座では歴史が古い鶴岡市清水の三森山と三ヶ沢の光星寺のモリ供養の様子を見学した。
庄内平野を一望できる大山公園で庄内地方の地形的特徴や歴史からモリ供養が長く受け継がれてきた理由についてお話をうかがった。四方を山・海に囲まれた閉ざされた地域で、為政者もあまり変動がなかった。出羽三山・鳥海山の山岳宗教の伝統も影響し祖霊の鎮まる所として畏敬され、信仰が続いてきた。

三森山のモリ供養(西のモリ)。上・中・下清水地区の人々が受け継ぎ守り続けている。登山口から標高120Mを30分位曲がりくねった道を登ると、優婆堂・閻魔堂・大日堂・観音堂・地蔵堂・仲堂・阿弥陀堂と7つの御堂が並ぶ。うっそうとした森の中にあり、モリ供養の期間だけ開山される。清水地区の4寺の僧侶達の読経の声とたちこめる香の匂いが独特の雰囲気を醸し出している。所々にモリノヤッコと呼ばれる子供たちが待ち受けていて参拝者の施しを受ける。ヤッコは乞食という意味で現代では差別用語とされているが、参拝者の喜捨は無縁仏への施しであり、清水地区の子供たちがヤッコに扮して伝統を守っている。


三ヶ沢の白狐山光星寺のモリ供養(東のモリ)。清水のモリノヤマとは庄内平野をはさんで向かい合っている。8月21~24日まで4日間供養が行われる。寺院と稲荷神社が同所にあり、神仏混交の宗教的歴史の証でもある。付近には縄文遺跡も在り、古代からの死者供養の習俗が現代まで続いていると考えられる。光星寺の開山は千年前とされている。境内には檀家宗の寄進により沢山の地蔵様や狐像、赤い鳥居があり独特の景観を見せている。庄内一円はもとより、県内外から多くの参拝者が訪れるという。


本講座はモリ供養が実際に行われる日に合わせて現地学習からのスタートとなった。2回目・3回目は座学で、さらに詳細なモリ供養の歴史的背景や現在まで大切に受け継がれている意義について講義していただくことになっている。















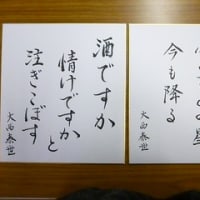



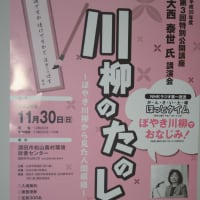
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます