赤のライン塗装の仕上げをします。
まずは、表面の段差を研磨する為に水砥ぎをします。
その際にマスキングのデコボコも研磨します。
続いてどうしてもガタガタになってしまう曲線の修正をします。
画像は半分ほど筆でラインをなぞりガタツキを直したものです。
けっこう、時間がかかりますがデカールとは違った一体感が
ライン塗装の魅力ですね。
ただ、どうしても曲面がキツイライン部になると
マスキンングがガタつきます。
つまり綺麗なアールの線にならない。
デカールでも曲面カウルに貼り込むとデコボコ感が隠せません。
無理に赤ラインを作ると、サイドカーカウルの
先端は見る方向によっては、ちぐはぐな感じになります。
つまり、先端が丸っこいカウルにキツイ曲線アールの
ラインはデザイン的にも破綻しやすいのです。
というか、実車のサイドマシーンのラインも
微妙にヨレヨレだから良いじゃん!と言う気がしますが、
どうにも、だらしないのですよね。
ですので、実車は実車!模型は模型。
その辺は、キッチリと模型的な解釈と見栄えを優先させます。
たぶん、模型にセンスが必要ならば最終的な仕上がりでの
見栄えの足し算引き算のセンスだと思います。
だって、プラモデルは誰でも組みたてられるように設計されているはずです。
それなら、他者との違いを表現するのは、
足し算(パーツデティールを追加)引き算(パーツの切り落とし)だけです。
そして、一番重要なのは色の足し引きです。
色を足せばリアルに見えるのですが、
それは、只単に情報量が増えたのでリアルに見えるだけです。
やり過ぎると。わけのわからない黒っぽいモノになります。
そこで、ある程度の色を何処まで足さないかという引き算もセンスですね。
これらの、センスは人が生まれついたモノでは無くて
経験による反復練習のみです。
プラモデル模型は美術的センスよりも工芸的センスが必要です。
普通に街の加治屋さんレベルで十分だと思う。
けっして、時計職人や宝石職人のような高度なスキルは必要としないです。
ですが、その先のフルスクラッチ原型を作る事になると
趣味のスキル次元が一歩進まなくてはいけませんよね。
良く昔のモデラーより今のモデラーの方が材料マテリアルが良いので
高度に簡単にできるという人がいますが、
今の方が、昔より高度な物を要求されます。
何時の時代も、材料は日進月歩なのですが
作る人間の少しずつの努力の積み重ねが
模型に限らず工芸の楽しみと思います。
そう言う意味では、昔も今も変わらないのです。
と、文章が長いのは・・・作業が思ったほど上手くいかないからです。
リカバリーの連続です。
もう、この時点では確実に飽きてきました。
でも、やればやるほどアラが出ますので
ホドホドで止めておきます。

ブログランキングに一票を~
下のロゴを「プチっと!クリックよろしく~」
(^-^p
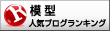
 にほんブログ村
にほんブログ村
まずは、表面の段差を研磨する為に水砥ぎをします。
その際にマスキングのデコボコも研磨します。
続いてどうしてもガタガタになってしまう曲線の修正をします。
画像は半分ほど筆でラインをなぞりガタツキを直したものです。
けっこう、時間がかかりますがデカールとは違った一体感が
ライン塗装の魅力ですね。
ただ、どうしても曲面がキツイライン部になると
マスキンングがガタつきます。
つまり綺麗なアールの線にならない。
デカールでも曲面カウルに貼り込むとデコボコ感が隠せません。
無理に赤ラインを作ると、サイドカーカウルの
先端は見る方向によっては、ちぐはぐな感じになります。
つまり、先端が丸っこいカウルにキツイ曲線アールの
ラインはデザイン的にも破綻しやすいのです。
というか、実車のサイドマシーンのラインも
微妙にヨレヨレだから良いじゃん!と言う気がしますが、
どうにも、だらしないのですよね。
ですので、実車は実車!模型は模型。
その辺は、キッチリと模型的な解釈と見栄えを優先させます。
たぶん、模型にセンスが必要ならば最終的な仕上がりでの
見栄えの足し算引き算のセンスだと思います。
だって、プラモデルは誰でも組みたてられるように設計されているはずです。
それなら、他者との違いを表現するのは、
足し算(パーツデティールを追加)引き算(パーツの切り落とし)だけです。
そして、一番重要なのは色の足し引きです。
色を足せばリアルに見えるのですが、
それは、只単に情報量が増えたのでリアルに見えるだけです。
やり過ぎると。わけのわからない黒っぽいモノになります。
そこで、ある程度の色を何処まで足さないかという引き算もセンスですね。
これらの、センスは人が生まれついたモノでは無くて
経験による反復練習のみです。
プラモデル模型は美術的センスよりも工芸的センスが必要です。
普通に街の加治屋さんレベルで十分だと思う。
けっして、時計職人や宝石職人のような高度なスキルは必要としないです。
ですが、その先のフルスクラッチ原型を作る事になると
趣味のスキル次元が一歩進まなくてはいけませんよね。
良く昔のモデラーより今のモデラーの方が材料マテリアルが良いので
高度に簡単にできるという人がいますが、
今の方が、昔より高度な物を要求されます。
何時の時代も、材料は日進月歩なのですが
作る人間の少しずつの努力の積み重ねが
模型に限らず工芸の楽しみと思います。
そう言う意味では、昔も今も変わらないのです。
と、文章が長いのは・・・作業が思ったほど上手くいかないからです。
リカバリーの連続です。
もう、この時点では確実に飽きてきました。
でも、やればやるほどアラが出ますので
ホドホドで止めておきます。

ブログランキングに一票を~
下のロゴを「プチっと!クリックよろしく~」
(^-^p



















