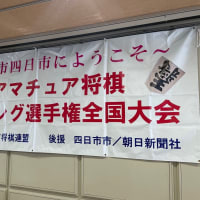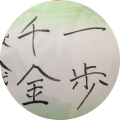クジ引きは、PTAや自治会の役員の決定
特に将棋大会では、予選の場所決め
トーナメント戦の位置決めなどなど
一大会で2回もクジを行うことは少なくない。
先日、来期の自治会、理事会の役員決定で
怪しいあみだくじ引きで、役員を決定してしまった
くじ引きの恩恵を受けてしまっている者ではありますが、
しかし、くじ引きは本当に公平で素晴らしい制度なのか?
将棋大会に限定し、その是非を考えてみました。
まずくじ引きはどうしてもデメリットがあります。
1 クジを作る手間。
2 クジを引く順番を決める時間。
3 参加に新たな番号を付番する。
1 クジの内容にもよりますが、一番簡単な
あみだクジでも1枚紙を用意して、参加者に
線を引いてもらう。順番に線を辿って決める必要がある。
抽選箱を用意して中にくじを入れて、、、等
それだけでも結構な手間と時間がかかる。
受付や早い順に決めてしまえばそんな手間や時間は
不要である。
2 もう一つ、くじの公平性を確保する上で、クジを引く
順番を決める作業がある。どっちが先に引くか決める場合。
譲りあったりする時間や、先にどっちが引くのかで揉めたり
することが多々ある。
3 意外に議論されないのはこの3番目である。
例えば、先日の令和最強戦や朝日アマ将棋名人戦の東京都
予選会のように、受付でクジを引いて最初の予選の番号。
その後、予選を通過した人にトーナメントのクジを引く
という場合。
受付番号No 、予選の番号、トーナメントの番号で、
3つの番号を100名を超える参加者の勝敗を管理することになる。
しかも当日申込であるため集計作業は困難を極める。
ただ、くじ引きで予選の番号や順番を決めることが、
一番良い選手を選ぶことになれば、デメリットがあっても採用する
必要がありますが、片方の山に強い選手が集まる。
とか、序盤で優勝候補がぶつかり合うということが多々あります。
個人的には、くじ引きは最初の1回までで、それも受付だけ。
決勝トーナメントの位置決めは、予選の成績で決めるのが、
最も公平ではないかと思いますが、、
なかなかこれはこれで、
「くじ引きは大会の華、これがないと盛り上がらない。」
「クジ引きこそ昔から公正で皆納得。」
等の御意見もあり新たなルールを定めるのは、結構時間がかかる。
悩ましいところであります。
事前にルールをしっかり作って、参加の皆様方の意見を聞き
修正しながら、周知を図っていくしかない。
とは考えています。