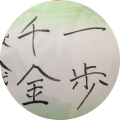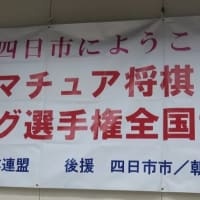将棋は独学。
教えてもらったのは小学生の高学年に囲碁の高段者の親父からついでに教えてもらったことだが、本格的にハマったのは中学2年生の時。
紙将棋と呼ばれるボールペンで盤を書いて、鉛筆で駒を書いて、動かしては消すという。今考えれば全く不効率な方法で遊んでいた。
対局が終われば4枚のはずの香車の数が7枚になっていたことも、、、
感想戦とかも当然ない、振り駒、大橋流?なにそれ、、、
ただ、数だけはこなしていたので、中学を卒業する頃には、学校で自分に勝てるのは、同じ県立の偏差値がほどほどの高校に進学したRしかいなくなった。
高校になって、初めて大会に出場するようになり、日頃の練習も流石に盤駒で対局するようになった。
顧問も多少将棋ができる先生がいたので、棋譜並べとか感想戦とかもするようになったが、ほぼRとの実戦が主であった。
高校3年には予選で5勝2敗で通過して、県大会ベスト8まで行けた。
隣の進学校の文化祭に乱入し、エース、OB、顧問に筋違い角という勝率の低い奇襲戦法で3勝したり、5人1組の団体戦で、準優勝した高校に自分だけ勝ったこともある。
しかしながら、野生育ちだったので、当時も適当に駒を並べ方も適当、感想戦などせず、未熟で無礼な輩であった。
私に負けた名門高校の生徒が「こんな奴に負けたんだ。」という顔は30年以上経った今でも覚えている。当時学歴コンプレックスの塊であった自分がこの顔を見るのが至上の喜びであったことはいうまでもない。
しかし「将棋には出会いがない。」と悟った私は、大学や20代には将棋はほとんどやらなかった。
同じ職場に学生将棋で鳴らしていた後輩が入ったのと、結婚したかみさんの実家と将棋道場が近くにあったので、それを通じてまた将棋にハマることになりました。
駒の並べ方を含め将棋の作法は、一回り以上年下の後輩や将棋道場での対戦者を通じて30代から学んだことです。
棋譜並べ、詰め将棋、感想戦。
言わば将棋の上達法の基本を学ぶことが初めてできました。
当時の才能を持った昔の自分が、現代の将棋の上達法を知れば、、と思うのは妄想かも知れませんが、条件は皆同じなので、これも運命でしょう。
私の場合はRというライバルや、同じ職場に後輩が入ったかきっかけがあったことが大きいです。
スポーツは学生時代にそれなりの実績がないと相手にされませんが、将棋では、私のように30代から本格的に始めても、将棋大会を主催するとか、プロの先生にお仕事が頼める位にはなれます。
昔の自分のような子供が、将棋で成功する。
これを将棋歴に加えたいな~。
長文失礼しました。