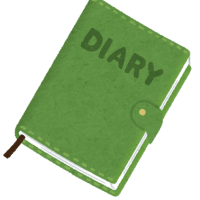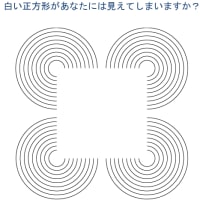正直、その間の記憶があまり残っていません。
しかし、とても嬉しかった記憶は強く残り、それは私たちの仕事にも関係するので、
私的なことで恐縮ですが、この場を借りてお礼を述べたいと思います。
我が家は、父母、私たち夫婦の4人暮らし。
母は心臓に病気を持ち、昭和61年に心臓の大きな手術をして、人工弁がついています。
10月末より発熱、嘔吐のため、急性期の病院に入院。
容態が悪化し、5週間に3回手術をしました。
点滴や人工呼吸器、排尿のためのカテーテルなど、体中に管がついて、
動きが制限されるため、家族が交代で付き添っていました。
環境が目まぐるしく変わり、日付や場所もわからない様子で、色々な意味で
目が離せない日々でした。
おかげで命を救っていただき、一つずつ管がはずれ、動いてよい状態になりましたが、
5週間の間にすっかり足腰が弱くなり、今までごく普通にできた動作が、こんなに大変
になるのか?という程、変化しました。
あまりの、体と頭の機能変化に、「もとの暮らしに戻れるだろうか?」と心配しました。
それまでの母の暮らしは、毎朝、近所の人達と公園でラジオ体操とウォーキング、植栽
の手入れから始まり、家事全般を担当する、我が家での重要な役割がありました。
また、毎週、ボランティアサークルやコーラスグループに所属し、家族以外にも、友達
や知り合いの多い、活動的な80歳でした。
「ふつうの暮らしを取り戻そう」という事で、リハビリの担当者さんと相談しながら、
起きている時間を延ばし、トレーニングを少しずつ始め、歩行器を使って歩く距離を
徐々に伸ばしていきました。同時進行で、手紙や日記を書き始め、最初はかすれて読み
取れない文字が、徐々に筆致が強く変わりましたが、内容は、手紙や日記とは思えない
ものでした。
7週目に自分の勤務する病院に、転院させてもらい、入院するご家族が経験される一連
の流れを実体験。いろんな職種に相談しながら、ご家族は、こんな気持ちになるんだな、
と感慨深い体験でした。
最初は、歩ける距離がごく短く、転倒のリスクが高く、自分では安全と危険の判断が
難しい状態でした。
ベッド周りやトイレ、食事場所の環境や、1日の予定、1週間の予定、トレーニングの
内容や量、趣味だった裁縫の再開、ラジオ体操ができるか、自分で行えるセルフケア
の拡大、料理のメニューを考える 等々、病棟チームのみなさんの様々な調整と、
リハ・ケアはじめ多職種チームの応援により、出来ることがちょっとずつ、日々、
拡がっていく感覚を実感できました。
勤務の後、洗濯物を取りに行くと、「今日はこんなだった、これをした」と、誇らしげ
に話す姿が、家族としてとても嬉しく思っていました。
驚いたのは、ハガキに手紙をしたため、旧知の友人やサークルの仲間に、「自分は生き
ている。また会いに行く」と手紙を出したこと。普段の会話では話がかみ合わない時が
あるのに、立派な文面でした。
年も押し迫り、正月に外泊し、大丈夫ならば年明けしばらくしたら家に帰れないかという
お話になり、9週目に「家庭訪問+外泊」が予定され、何よりも本人がとても楽しみにして
いました。
外泊の当日、新たに心不全が判明し、手術後の経過もあるため、急性期病院に戻って精査
・加療という事になりました。救急搬送に師長が同行してくれ、病状の変化やこれまでの
様子など、テキパキと心臓の主治医に伝達。これは本当に心強かったです。
あらためて様々な検査により、34年前に取り付けた人工弁を固定する糸が一部ほどけ、
血流が逆流している事、心不全は治療で改善するが、人工弁を付け替える手術は出来ない
事、今後は入院が長くなる事、急変がありえる事、最期の延命をするかどうかを決める
必要がある事、など、説明してもらい、家族で話し合うよう時間をもらいました。
父は即座に「つれて帰ろう」という決断でした。
「病院ではなく家で」
「したい事をしながらふつうに暮らさせたい」
「延命は必要ない」
と返答する父の声を聞きながら、家族はいろんな事を考え、病院の職員と話すんだ、という
事を、自分事としてあらためて考えました。
2週間で心不全の治療と退院準備を進め、11週目の1月10日に自宅へ帰ってきました。
同日に自宅で開催されたサービス担当者会議は総勢11名と圧巻で、緊急時の連絡方法や日々
の健康管理、これからの暮らしについての様々な調整をしてくれました。
その日から、椅子に座って夕食の準備を手伝い始め、料理すべては出来ないものの、一部分
を担当する事は可能なんだという事を確認出来ました。
退院直後は、つまづくことも見られ、屋外歩行は介助していても、転びそうになる事があり
ました。ちょっとずつですが、トイレ、入浴、寝起き、屋内の移動、屋外の移動などを安全
にできる方法を確認しつつ、掃除、食事づくりの補助、洗濯たたみと仕分け、アイロンがけ、
など、徐々に役割を増やしていきました。
自宅へ帰ってきて5週間。
県が作ったビデオを見ながらいきいき百歳体操、公園への散歩、夕食づくりの補助が日課に
なり、毎日3,000歩程、歩いています。台所に1時間程立って食事の準備に参加しています。
包丁やアイロンを握ったら、そこは長年の経験が手に染みついているのか、見事な仕事ぶり
です。
局面は色々ありましたが、一番の変化は、家族の姿が大きく変化したことです。
今までは、お互いに無関心だった老夫婦が、「お薬の時間やで」、「ご飯食べようか?」、
「散歩いこか?」とかまい合い、一緒に過ごしています。公園のベンチで並んで座っている
姿なんて、これまで見たことがありませんでした。
弟や娘も、何かと理由をつけて、両親の顔を見に来ます。
私と嫁も、どちらかが早く帰って、「さあ ご飯を作るよ!!」と、母親を台所へ。
まさか母親と台所に並んで立って、料理をするなんて思ってもみませんでした。
食器棚からそこにあるはずのない醤油が出てきたり、ゴミの分別が面白いことになっていた
り、洗濯すると服が行方不明になったりしますが、おかげで家に笑いが絶えません。
出来ない事は増えたけど、環境を整えておけば、充分役割を果たせます。
そして、そこにいるという、「存在している役割」のおかげで、家族の行動に変化をもたら
してくれています。
コーラスやサークルへの挨拶、自治会の食事会への復帰、お見舞い返し、と、やりたい事を
一つひとつかなえていますし、次は「コーラスを再開する」のだそうです。これから何があ
るかはわからないけれど、今の時間が少しでも長く続けばいいなと願っています。
今回の経験で色々と教わりました。
病院に入院する、というのは、非日常の世界であり、入院中は今までの暮らしと大きな変化
があります。病院の役割によって、行う事の優先順位や環境は変わります。家族や本人は、
展開のスピードに必死についていきつつも、大小様々な決断をしながら、その間も気持ちは
揺れる事を知りました。
その間、多くの専門職に支えられるという事。声のかけ方、目配り、気配りに、とても敏感
になり、それがとてもありがたいという実感を持ちました。
また、リハビリテーションは、朝起きてから眠る時間も含め、全ての場面に関係する一つひ
とつの行為や動作、家庭や社会の中での役割やしたい事、その人の「ふつうの暮らし」の中
での繰り返しでこそ元気になれる、という事を、あらためて実感しました。
霞ヶ関南病院での入院期間はあっという間の2週間でしたが、生活の再建をする時間として
充分効果を発揮し、今の母親と、我々家族の暮らしを支えてくれています。
「自分の大切な人を入院させられる病院にしたい」と、仲間と話し合いながら奮闘してきた
31年、本当にいい職場で働かせてもらっていると、心から思います。
一人でも多くの方の、「ふつうの暮らし」を支えられる職場であるよう、これからもがんば
っていきたいと思います。
関わって下さった全ての皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。
岡持利亘