初めに断っておくと、私は俳句を始めてようやく3年半、ましてや短歌に関してはほとんど素人である。ただし、それはある意味武器になるかもしれず、短歌の「調べ」に関しては、むしろ何の知識もない素人が素直に口に出して心地よい事が本質なのではないかと考えた。というわけで、日本人の遺伝子に予め組み込まれているであろう「調べに対する本能的な感覚」を信じて短歌を鑑賞してみたい。取り上げるのは、今を時めく歌人川野芽生さんの歌集、『星の嵌め殺し』(河出書房新社、2024年)である。
まず俳句の話から入ろう。俳句の韻律に関して必ず議論になるのは「字余り字足らずの可否」である。俳句の世界では定型死守派が多数派を占め、その中でも中七の字余り字足らずは基本的には忌避される。私は個人的に自由律でも破調でも俳句は俳句だと思っているが、中七が微妙な8音や9音になってしまった時にはなんとか7音に収められないか推敲する。俳句は短さに振りきっているだけあって1音1音の責任が大きいから、締まりが良くなるようすがたに気を遣う事は短歌以上かもしれない。
一方、短歌における字余り字足らずについて調べてみると、少し調べただけでも、俳句と違って「調べさえよければ」多少5・7・5・7・7から逸脱してもかまわない、と肯定する意見がほとんどだった。
実際、先述の『星の嵌め殺し』を音読してみたのだが、字余りは勢いで読めてしまうし、字足らずは詰まったような効果が出ていて技法として非常に活きていた。
逆にリズムにやや迷ったのは、下の句において、音数はあっていて「句またがり」している場合である。つまり下の句全体では14音に収まっているものの、第4句と第5句にかけて1つの言葉がまたがっている場合である。例えば。
落雷に狂ふこころのくらがりに苛々花開くライラック ・・・①
この歌の下の句は7・7で読もうとすると「いらいらはなひ/らくらいらっく」となり「開く」の途中で切れてしまうため、定型だと思って読むと戸惑う。読むなら9・5で「苛々花開く/ライラック」となるだろう。いや、むしろ14音をひと固まりと見て、切らないのが正解かも知れない。ひらがなにしてみると分かると思うが、一息に言ってしまった方がこの歌は面白い。大部分がら行、か行、「い」で構成されているのだ。ラップが尻尾を巻いて逃げていきそうな巧みな韻律である。
ちなみに、俳句にも音の繰り返しの面白い句はたくさんある。例えば。
昼顔の見えるひるすぎぽるとがる 加藤郁乎 ・・・②
「ぽるとがる」が分からない、という声があるが、意味の前に舌頭千転してみるとよい。「ぽるとがる」が動かない事が身に沁みる、いや、舌に沁みるはずだ。
次の句またがりの歌はこちら。
引き抜きてかつて捨てしを夜の卓に柘榴のくれなゐの乱杭歯 ・・・③
こちらも下の句の句またがり。「柘榴」「くれなゐ」「乱杭歯」という三つの強い語が、助詞「の」によって結び付けられている。この力強い三語、しかも濁音が合計三回も出てくる三語を滑らかに読ませる上で、かなり重要なのが実は助詞の「の」である。助詞の中でも最も自己主張しない助詞だからこそ、上記の歌のように二つ、あるいは三つ続けて使う場合がある。有名なのは百人一首にも入っている柿本人麻呂の歌だろう。上の句「あしひきの山鳥の尾のしだり尾の」のリズムの良さは助詞「の」あってのものだ。このように「の」が二つ三つ続けて使われる場合、歌にリズムができて車輪がぐるんぐるん回るように調べが滑らかになる。意味の上でも「柘榴」「くれなゐ」「乱杭歯」全てが「の」によって一本に繋がっているのだから、これも14音を区切らずに一気に読むべき歌だと言える。
さらに次の句またがりの歌。
極光を爪に灯して手を振ればいつせいに亡霊が振り向く ・・・④
上の歌は、7・7で読もうとすると「亡霊」のところで「亡」と「霊」に分かれてしまう。そこで今回は内容に着目。「いつせいに」亡霊が振り向くのである。音読する際にもぜひこの勢いが欲しい。その意味で、今回もあえて「切らない」のである。
どんどん面白くなってきた。短歌は俳句と対照的な部分が多い。俳句は17音で加速するには短すぎるが、31音あれば、1首の中で加速する事ができるのだ。
まとめに入るが、先入観無しにひたすら音読した事で、我ながら実に素人らしい素朴な気付きがあったように思う。短歌における句またがりの効果のひとつとして、非常に強い言葉をたたみかけるように用いて歌の力をどんどん増幅させたい場合や、句ごとに区切らずに一気に加速させたいような場合。上記のようなシーンで、非常に効果を発揮する技法だという事が分かった。
①、③、④出典:川野芽生『星の嵌め殺し』(河出書房新社、2024年)
②出典:加藤郁乎『加藤郁乎詩集』(思潮社、1971年)










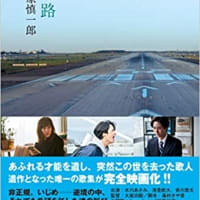
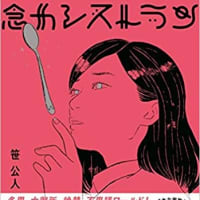
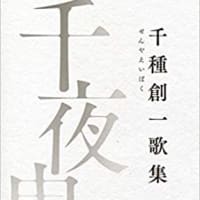
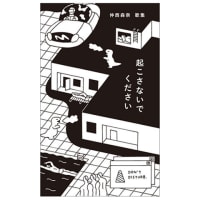
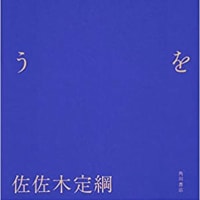
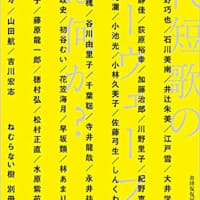

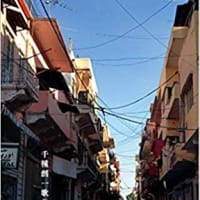

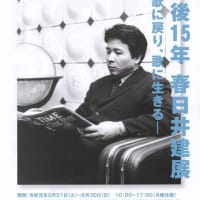
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます