この二ヶ月くらい、多くの魅力的な歌集に出会った。
『体内飛行』石川美南
『どんぐり』大島史洋
『丈六』柳宣宏
『展開図』小島なお
『ナラティブ』梶原さい子
『風と雲雀』富田睦子
『飛び散れ、水たち』近江瞬
など。
中でも、大島史洋(今年7月で76歳)と柳宣宏(今年4月で67歳)の二人の歌集に、短歌とは何かを考えさせられた。
年齢はそんなにたいせつなのか? という議論はある。
「コスモス」は今年4月から、折り込みの詠草用紙にあった年齢(と職業)の欄を除いた。(もともと性別欄はない。専用用紙でなくコピー用紙に印字でもよい。) その後、数回選歌を担当したが、大きな違和感はなかった。ただ、歌によっては年齢が読みを補佐する、というか歌を引き立てる面もある。年齢を知りたくなった作品はいくつもある。高齢者が多いグループだけれど、同じご病気でも七十歳と八十五歳では作者も読者も実感が違うものだ。読者(選者)が移入する感情の濃淡も変わってくる。とはいえ、雑誌になったときには年齢は掲載されないわけだし、その作者を知っているどうかの問題にもなる。詠草用紙の改訂は良いことだと思っている。
だが、すべての短歌作品から「年齢」を取り除いていいわけではないと思う。匿名の歌会、名前付きの一首投稿、名前付きの作品群、一冊の歌集、全集などの媒体によってかなりの差がある。それを一括りにして語るのは乱暴である。
同じ歌集の同じページの作品でも、匿名性の高いものと署名性が高いものが混在する。署名性が高そうな作品も、部外者からみれば類似作品のように見えることも多いだろう。当然ながら、短歌に何を求めるのかは、歌人の間でも大きく違う。だから、さまざまな議論をおもしろがり影響を受けながらも、直感的な向き合い方しかできないのだろうな、と思う。よくわからないままでいいと思う。
『体内飛行』石川美南
『どんぐり』大島史洋
『丈六』柳宣宏
『展開図』小島なお
『ナラティブ』梶原さい子
『風と雲雀』富田睦子
『飛び散れ、水たち』近江瞬
など。
中でも、大島史洋(今年7月で76歳)と柳宣宏(今年4月で67歳)の二人の歌集に、短歌とは何かを考えさせられた。
年齢はそんなにたいせつなのか? という議論はある。
「コスモス」は今年4月から、折り込みの詠草用紙にあった年齢(と職業)の欄を除いた。(もともと性別欄はない。専用用紙でなくコピー用紙に印字でもよい。) その後、数回選歌を担当したが、大きな違和感はなかった。ただ、歌によっては年齢が読みを補佐する、というか歌を引き立てる面もある。年齢を知りたくなった作品はいくつもある。高齢者が多いグループだけれど、同じご病気でも七十歳と八十五歳では作者も読者も実感が違うものだ。読者(選者)が移入する感情の濃淡も変わってくる。とはいえ、雑誌になったときには年齢は掲載されないわけだし、その作者を知っているどうかの問題にもなる。詠草用紙の改訂は良いことだと思っている。
だが、すべての短歌作品から「年齢」を取り除いていいわけではないと思う。匿名の歌会、名前付きの一首投稿、名前付きの作品群、一冊の歌集、全集などの媒体によってかなりの差がある。それを一括りにして語るのは乱暴である。
同じ歌集の同じページの作品でも、匿名性の高いものと署名性が高いものが混在する。署名性が高そうな作品も、部外者からみれば類似作品のように見えることも多いだろう。当然ながら、短歌に何を求めるのかは、歌人の間でも大きく違う。だから、さまざまな議論をおもしろがり影響を受けながらも、直感的な向き合い方しかできないのだろうな、と思う。よくわからないままでいいと思う。
さて、大島史洋『どんぐり』(現代短歌社)(2014年〜2018年の作品)に、
059 重くれを嫌うならねど重くれは身に添わぬなり七十過ぎて
(歌の左の数字は、ページ番号です。)
があった。
「重くれ」は俳句の批評用語のようで、「軽み」の反意語で、理知的な方向の句を指す概念であるようだ。内容的な面もあるし、文体的な面もあるという。ある俳人に聞いたところ、芭蕉の、
「重くれ」は俳句の批評用語のようで、「軽み」の反意語で、理知的な方向の句を指す概念であるようだ。内容的な面もあるし、文体的な面もあるという。ある俳人に聞いたところ、芭蕉の、
秋深き隣は何をする人ぞ
は、軽みで、
荒海や佐渡によこたふ天河
は、重くれかもしれない、と教えてくださった。
(単純化しすぎなことは承知している。)
そもそも「重くれを嫌うならねど」という大島の言挙げこそが「重くれ」に当たるようにも思う。短歌はもともと「重くれ」を志向してしまう長さを持つのだろう。(いつか、短歌は長嶋茂雄、俳句は王貞治、と喩えた歌人がいたのを思い出す。)
は、軽みで、
荒海や佐渡によこたふ天河
は、重くれかもしれない、と教えてくださった。
(単純化しすぎなことは承知している。)
そもそも「重くれを嫌うならねど」という大島の言挙げこそが「重くれ」に当たるようにも思う。短歌はもともと「重くれ」を志向してしまう長さを持つのだろう。(いつか、短歌は長嶋茂雄、俳句は王貞治、と喩えた歌人がいたのを思い出す。)
それはさておき、今回の歌集もまさに大島の老いの受け止め方がぼつぼつと描かれている。その訥々としてユーモラスなところに惹かれた。作者の生年はウィキペディアに載っている。収録された歌の制作時期は各章に明示されている。この歌集の場合、それらは歌を大いに引き立てる。(編年体の章立てで、「Ⅰ 二〇一四年」「Ⅱ 二〇一五年」というように明快に区切られているのが気持ち良い。)
078 しみじみと今日まで生きし喜びを言えどまったく深さが足らぬ
094 だんだんと変になりゆく自分なりそれを知りつつ少し楽しむ
122 脊柱管狭窄症のかそかなる痺れや雨の梅林公園
143 わがいだく不安は常に吾のみのものにてあれば世はこともなし
これらの歌は「重くれ」なのか。テーマはそれぞれ重いが、詩的処理が効いていて軽みがある。しかし、そこに七十代の男性、そして作者、いや大島史洋という歌人が歩んできた道のりを重ねて読む。年齢の重さゆえに、生み出される言葉の軽さがかえってバランスよく響いてくる。歳を重ねて好き勝手に詠んだ歌がヒットするのは茂吉や岡部圭一郎や岩田正を例にあげなくてもそこに豊潤な場所があるのはみな知っている。やはり、歌に生年は付いていた方がいいだろうという立場に傾く。この三首目の「かそかなる痺れや雨の」あたりのリズム感にこちらがシビレる。
紙幅の制限がないので、もう少しあげる。
紙幅の制限がないので、もう少しあげる。
075 若き日は美化されやすしいつからか老人ばかりのめぐりとなりぬ
123 ふるさとをうたいて美化を感ずると友に言われき美化してゆかむ
「美化」が使われている二首。なぜ私はこういう繰り言のような歌に惹かれるのだろうか。それは次の、
100 老人がこの世の害になることを繰り返し聞き老いてきたりし
045 時は過ぎ捨てねばならぬ地図などにマークしてあり茂吉歌碑の所
などを足して考えると、濃い年齢意識による表現への覚悟を読み取ることができるからだという答えに至る。長い中年期を経て老年期に入る。そこに人生の屈折が生まれる。そのあたり、短歌としての豊かな刈り入れ場があるのだ。
さて、柳宣宏『丈六』(砂子屋書房)に移る。
2015年〜2019年の作品。それが目次に記載されている。はっきりと六十代半ばを生きた人間としての足跡です、と宣言しているのだ。
亡き両親を恋う気持ち、ある学校を離れて別の学校に移る際の気持ち、家族や友人との関係、父や舅を通して見る戦争、妻子への気持ちなど、禅僧を思わせる(じっさいに座禅をお続けのようだ)静かな文体からあふれてくる。「気持ち」を前面に感じる。そこに私は打たれた。だって、「あゆみは長女である」と詞書に書いておいて、
2015年〜2019年の作品。それが目次に記載されている。はっきりと六十代半ばを生きた人間としての足跡です、と宣言しているのだ。
亡き両親を恋う気持ち、ある学校を離れて別の学校に移る際の気持ち、家族や友人との関係、父や舅を通して見る戦争、妻子への気持ちなど、禅僧を思わせる(じっさいに座禅をお続けのようだ)静かな文体からあふれてくる。「気持ち」を前面に感じる。そこに私は打たれた。だって、「あゆみは長女である」と詞書に書いておいて、
051 向うからあゆみの来れば電球が胸のあたりに点る気がする
なんて歌をしゃあしゃあと(失礼)発表できるなんて、すばらしいじゃないですか。もうご結婚されて家を出た娘さんですよ。
209 弁がたち計算達者な男にはあらざる息子をひそかに誇る
257 夕べには娘夫婦が来るといふ玄関先を掃いたりしてゐる
205 この家に妻と暮すも新年の朝のはじめに会ふは照れたり
というのもある。大人の息子を誇る歌に、娘に会う喜びでいそいそと掃除するみずからをコミカルに描く姿に、自然な夫婦像に、批評の余地はなく、ただ良いと思うのみだ。
あるいは、「島田修三夫人告別式」というタイトルのもとに、
118 妻なしとなりける島田の手を握り言ふことあるか妻あるわれに
120 修三が眼鏡のまへにわれはただ拳を固く握りて掲ぐ
120 修三が眼鏡のまへにわれはただ拳を固く握りて掲ぐ
という歌がある。長く「まひる野」を支え合ってきたおじさん(失礼)同士の愛を見る。島田修三という大人物と面識があるかどうかによっても歌の理解の深さは違ってくるだろう。だが、それを除いても、このとても個人的なシーンには普遍性がある。いや個人的であるからこそ明確な普遍性を発揮している。うまく詠もうとしがちなとき、こういう歌の底力を思うのである。
042 梅干しの固く赤きを齧りつつ心がはれるといふことがある
043 先輩はありがたきかな、なあヤナギ、咲くと思はず花は咲くんだ
048 ジャカルタの水にあたつて苦しみしそれも仕事の花の日々かも
081 この星は生まれて四十五億年まだ若いなあと口に出してみる
どれも明るい。懸命に生きている人の姿が見える。六十歳を過ぎて、「なあヤナギ」と肩を叩かれながら(想像です)言われている男性の姿。そこにはいわゆる昭和な上下関係の美質が残っている。文章語的口語言い切りの力強さもあろう。泥臭さもある。ジャカルタの夏の暑さにやられながら白ワイシャツにネクタイ姿で(想像です)校務出張をバリバリとこなす(これまた昭和的な)男性の姿が透けて見える。
あるいは四首目。そういう六十半ばを超えたおっさん(失礼)から、地球はまだ若いなあ!と口に出されたら、内臓からぐんと力が湧き出る感じがする。例えばこの歌にとっては、作歌時点の年齢は関係ありそうだ。「まだ若いなあ」は作者自身に向けられた言葉でもある私は直感的に読んだ。とすると、ある程度の年配者の言葉でなくてはおもしろみも説得力もない。七十代だとやや苦しげ。八十代だと合わないなあという印象。やはりまだまだ壮年という年齢が歌を引き立てる。恣意的な読みなのかもしれないが。
さて、あと2冊。
富田睦子『風と雲雀』(角川書店)。この著者もあとがき冒頭で、「二〇一三年の暮れから二〇一八年はじめまで、年齢で言えば四〇歳から四四歳までの作品を収録しています。」と明記している。背景がはっきりしているのは助かるし、好きだ。
主題は、小学生から中学生に成長する時期の娘さん。その彼女との関係(葛藤というべきか)である。全身全力で娘にぶつかり、お互いに傷つく。その姿を描いている。
富田睦子『風と雲雀』(角川書店)。この著者もあとがき冒頭で、「二〇一三年の暮れから二〇一八年はじめまで、年齢で言えば四〇歳から四四歳までの作品を収録しています。」と明記している。背景がはっきりしているのは助かるし、好きだ。
主題は、小学生から中学生に成長する時期の娘さん。その彼女との関係(葛藤というべきか)である。全身全力で娘にぶつかり、お互いに傷つく。その姿を描いている。
011 寝たふりを見破るところ眦に細くふたすじ皺よする子は
037 いいこだねかわいいねとぞゲシュタルト崩壊させつつ眠る子を見る
038 前髪のわずか巻毛をからかわれ帰りて泣く子の指の冷たし
199 きょうだいもいとこもおらぬわが少女ささいなケンカを泣くほど悔やむ
203 歩く木と育つ木わたしはどちらの木わがひとり子はたぶん歩く木
210 吾子の裡そだつ悪意を聞いている火蟻のごとき自我と覚えて
037 いいこだねかわいいねとぞゲシュタルト崩壊させつつ眠る子を見る
038 前髪のわずか巻毛をからかわれ帰りて泣く子の指の冷たし
199 きょうだいもいとこもおらぬわが少女ささいなケンカを泣くほど悔やむ
203 歩く木と育つ木わたしはどちらの木わがひとり子はたぶん歩く木
210 吾子の裡そだつ悪意を聞いている火蟻のごとき自我と覚えて
母と娘の距離感の近さの歌は先達があるが、なんど繰り返されてもいい題材だ。寝たふりを知っている母、自分の子なのかわからなくなるまで寝顔を見続ける母、十代の心の壊れやすさや友人関係をひたすら案じる母、自分と娘の比較、娘の内面的成長を恐れつつ見守る母。どれも懸命の母である自分を題材に、場面場面を詩に昇華している。
023 その元気わけてと言えば抱きついてくる少女なり三日月を抱く
084 風わたる葡萄棚われまだふいに抱きついてくる少女をいだき
091 鼻血垂る娘のひたいを胸に当て頸冷やすとき生まぎれなし
など、身体的距離感の近さを言うのも母娘の関係に特徴である。そしてこの歌集のひとつのハイライトが、
122 わが声にわれは興奮してゆけば子への衝動は愛より憤怒
123 一生をわれは忘れじ吾子に向けマウス投げつつ恫喝せしを
124 いまわれは吾子を殺せりまなうらがこんなに熱き怒りのうちに
124 退塾の理由にマウスを投げしこと告白すれば軽く笑わる
126 もう塾のない午後である手をつなぎ大きな木のある公園へゆく
127 今日なんか楽しかったと子の言えば泣きたいような夕焼けである
を含む一連である。そのしばらく前に、
043 月一度試験で席が変わる塾かよわせてわがこころは細る
がある。子供の私立中学受験へチャレンジは、どの家庭にとってもなかなかの試練であると聞く。それは、『二月の勝者−絶対合格の教室−』(高澤志帆)という漫画にリアルに描かれている。「君たちが合格できたのは、父親の「経済力」そして、母親の「狂気」」という塾講師のセリフで始まる。
状況はわかるし、ドキュメンタリーとして出色。だが、ここで思うのは、なぜこんな状況をわざわざ歌に残したのか、という疑問だ。
いや、答えはわかっている。富田睦子が歌人だからだ。偶然にしろ選び取ったにしろ短歌を続けている以上は、こんな辛い状況であっても、真っ向から受け止めて書くのだ。もちろんそこには場面の切り取り方や言葉の選び方、あるいは劇画化、構成のしかたなどの技術は関係する。だが、いちばん大切な、すべて受け止めて詠むという姿勢がなければ読者の心を動かさないのだ! と、書いている私も高揚してくる。
強引に冒頭の大島の一首とつなげれば、この「重くれ」た感じが短歌のひとつの喜びであるのだなあという結論にもなる。
だがもちろん、『風と雲雀』はこれが全てではなく、
状況はわかるし、ドキュメンタリーとして出色。だが、ここで思うのは、なぜこんな状況をわざわざ歌に残したのか、という疑問だ。
いや、答えはわかっている。富田睦子が歌人だからだ。偶然にしろ選び取ったにしろ短歌を続けている以上は、こんな辛い状況であっても、真っ向から受け止めて書くのだ。もちろんそこには場面の切り取り方や言葉の選び方、あるいは劇画化、構成のしかたなどの技術は関係する。だが、いちばん大切な、すべて受け止めて詠むという姿勢がなければ読者の心を動かさないのだ! と、書いている私も高揚してくる。
強引に冒頭の大島の一首とつなげれば、この「重くれ」た感じが短歌のひとつの喜びであるのだなあという結論にもなる。
だがもちろん、『風と雲雀』はこれが全てではなく、
070 夜を降りて闇へ消えゆくぼた雪を光の届く部分だけ見る
152 火を摑むされども夢のわたくしは火を知らざれば燃える手を見る
154 腹の足をいかに動かしたるべきか苦心したればふとも目覚める
152 火を摑むされども夢のわたくしは火を知らざれば燃える手を見る
154 腹の足をいかに動かしたるべきか苦心したればふとも目覚める
のような繊細な視点の動きや、自分の内面を覗き込み過ぎてわからなくなってしまった歌にも秀歌が多い。そして、そのあたりが融合された歌が、
119 シスジェンダー・ヘテロと吾子を喜びてのちを羞しき冬のはなびら
なのではないかと思う。最後に置いておく。
さて、最後の1冊。長くなってしまったけれど、挙げておきたい歌集である。
『飛び散れ、水たち』近江瞬(左右社)。
プロフィールによると1989年石巻市生まれ・在住。早稲田大学卒業。
現在はいわゆるUターンで、地元紙、つまり石巻日日新聞社の記者であるようだ。
私はいつも「あとがき」を読んでから巻頭に戻る。だが、この「あとがき」を読んでも、後半の展開が予測できなかった。序盤からは相聞を多く含んだ、青春の苦さや明るさを詠んだ歌。
『飛び散れ、水たち』近江瞬(左右社)。
プロフィールによると1989年石巻市生まれ・在住。早稲田大学卒業。
現在はいわゆるUターンで、地元紙、つまり石巻日日新聞社の記者であるようだ。
私はいつも「あとがき」を読んでから巻頭に戻る。だが、この「あとがき」を読んでも、後半の展開が予測できなかった。序盤からは相聞を多く含んだ、青春の苦さや明るさを詠んだ歌。
008 ふと君が僕の名前を呼ぶときに吸う息も風のひとつと思う
033 記憶にはない故郷の稜線を画像検索して取り戻す
033 愛想笑いだったと気付く口角をゆっくり元に戻していれば
046 十年後に見て騙されたりしないよう小さめのピースサインにしとく
104 ため込んだ悲しみ不良少年のバイクが「タラレバタラレバ」と鳴く
080 三人が車内に揺れてそれぞれのスマホに反射する月の色
033 記憶にはない故郷の稜線を画像検索して取り戻す
033 愛想笑いだったと気付く口角をゆっくり元に戻していれば
046 十年後に見て騙されたりしないよう小さめのピースサインにしとく
104 ため込んだ悲しみ不良少年のバイクが「タラレバタラレバ」と鳴く
080 三人が車内に揺れてそれぞれのスマホに反射する月の色
どれもいい。どれも巧い。複数の時間帯が視野に入っていて、その時間を行き来しているようだ。それはすでに記憶になり過去から十年後まで。不良少年の過去にまで及ぶ。現代風で軽そうでいながらしっかりと重りがついているようだ。
018 歩行者を数えるバイトの青年が僕をぴったり一人とみなす
028 使い方を知らないボタンに囲まれて放送室に君と僕だけ
065 筆談で祖父は「へへへ」と笑い声を書き足している険しき顔で
068 ビニールの中の金魚におそらくは最初で最後のまちを見せてる
103 この道を渡ると帰ってきた感があってふたりは暮らしになれた
028 使い方を知らないボタンに囲まれて放送室に君と僕だけ
065 筆談で祖父は「へへへ」と笑い声を書き足している険しき顔で
068 ビニールの中の金魚におそらくは最初で最後のまちを見せてる
103 この道を渡ると帰ってきた感があってふたりは暮らしになれた
高校時代のシーン(二首目はなかなかエロい。知らないボタンって。)から。闘病中の祖父。金魚。そして恋人との同居(結婚?)。歌材は広く、描写は的確である。しかしそれでも、同じ感じの青春歌は他の歌人にもあると思う。子細に見ればもちろん特徴はあるのだけれど、匿名性の方が先に立つ歌であろう。
しかし、そういう歌が続いたあと、全体の残り六分の一くらいに来て、三つの章のうちの三つ目きてトーンが変わる。
しかし、そういう歌が続いたあと、全体の残り六分の一くらいに来て、三つの章のうちの三つ目きてトーンが変わる。
120 新聞を折り込み終えれば手に黒が移ってほかの色は移らず
121 上書き保存を繰り返してはその度に記事の事実が変わる気がする
122 あの時は東京で学生をしてましたと言えば突然遠ざけられて
123 忘れたいと願ったはずのあの日々を知らない子どもを罪かのように
123 Uターンの理由は震災かと問われ「まあ」と答えてはぐらかしてる
125 薄く目を開けば水面は広がって聴く風は少し波と似ている
121 上書き保存を繰り返してはその度に記事の事実が変わる気がする
122 あの時は東京で学生をしてましたと言えば突然遠ざけられて
123 忘れたいと願ったはずのあの日々を知らない子どもを罪かのように
123 Uターンの理由は震災かと問われ「まあ」と答えてはぐらかしてる
125 薄く目を開けば水面は広がって聴く風は少し波と似ている
多めにあげてしまう。
地元に戻り新聞社に就職したあとの歌なのだ。三、四、五首目。故郷への愛と使命感を持って帰郷し就職したはずである。(と決めつけるの立場にないが、おそらく。)だが、心ない対応を受けることもある。いや、そういう対応をしてくれるならいい。そういう人の背後には、表面では受け入れるふりをしながら心の底では受け入れてくれない人がいるのだと賢明な作者なら気づいていたはずだ。その精神的な辛さは、類似の境遇の人が少ないだけに、どんな慰めも効かなかっただろう。題材はなかなかの「重くれ」である。
地元に戻り新聞社に就職したあとの歌なのだ。三、四、五首目。故郷への愛と使命感を持って帰郷し就職したはずである。(と決めつけるの立場にないが、おそらく。)だが、心ない対応を受けることもある。いや、そういう対応をしてくれるならいい。そういう人の背後には、表面では受け入れるふりをしながら心の底では受け入れてくれない人がいるのだと賢明な作者なら気づいていたはずだ。その精神的な辛さは、類似の境遇の人が少ないだけに、どんな慰めも効かなかっただろう。題材はなかなかの「重くれ」である。
128 仮設から復興住宅へと移る壁の厚さをさみしさと呼ぶ
128 必要というのはせっかく復興庁の予算を充てられるからということ
129 図書館も被災してれば国の金で立派にできたのになんて言葉も
138 まとめるのうまいですねと褒められてまとめてしまってごめんと思う
この一首目は作者自身の感慨とも読めるけれど境遇的にそうではないは。(こういうところ、許容範囲は読者によるけれど、そのユルさも短歌のいいところかな。あまり厳密に表現することだけを心がけると思い切った表現が死んでしまう。悩ましいところ。)二十代の記者が話を聞きに来て、ついつい本音を述べてしまったのか。そういう言説は現地ではよくあることなのか。それを掬い上げて歌にしているのがいい。先の富田と対象は違うが、受け止めて詠む、ひとつのありかたなのだと思った。
最後の一首を含む二つの連作は小文がついている。その小文がどれもよく、断片になるけれど引用したい。
・「忘れちゃいけない」と言う人の前日の投稿にあるディナーの肉がおいしそうだった。
・僕は、当時ここにいなかったことを聞かれるまで、言わない。
・相手が安心してくれればと思い、「僕もここが地元です」と伝えるように方言をいつもより大げさに使った。
・僕は、当時ここにいなかったことを聞かれるまで、言わない。
・相手が安心してくれればと思い、「僕もここが地元です」と伝えるように方言をいつもより大げさに使った。
近江歌集の前半と後半の題材的格差を楽しみつつ、そこに表現の一貫性、表現者としての一貫性を思いながら、重い題材を、この最後の4首のように軽めに読ませてもらえることを楽しみつつ、短歌ってなんだろうと思いつつ、稿を終えたい。
(2020.5)
(2020.5)










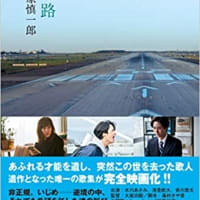
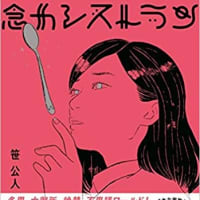
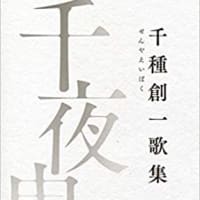
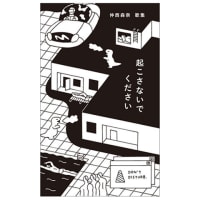
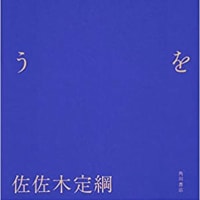
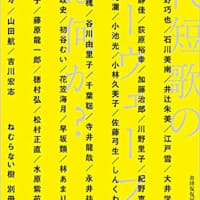

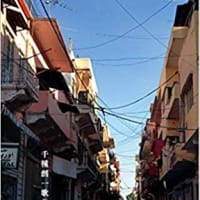

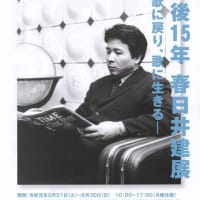
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます