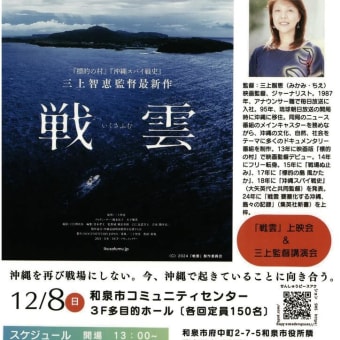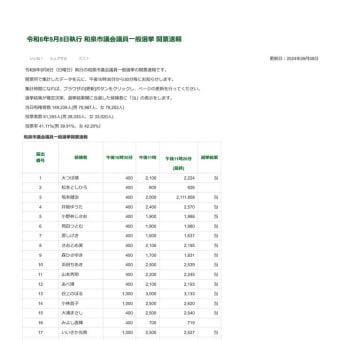月例給・一時金とも改定見送りへ<o:p></o:p>
= 賃下げ法を容認、「賃金回復・改善」勧告の要求には答えず =<o:p></o:p>
<o:p>
公務労組連絡会は6日、勧告を間近にひかえて人事院との最終交渉に臨みました。
交渉で人事院は、「賃下げ法」で減額される前の俸給表上の給与額と比較し、官民賃金はほぼ均衡しているとして、月例給・一時金ともに改定を見送ると回答しました。
労働基本権が踏みにじられて「賃下げ法」の成立が強行された経過からも、労働基本権制約の「代償措置」としての役割を発揮し、実支給額にもとづく「賃金回復・改善勧告」という要求には何ら応えない不当な回答に、交渉団は強く抗議しました。
再任用職員の賃金水準は、来年の民間実態調査から判断
人事院との交渉には、公務労組連絡会から野村議長、北村副議長、黒田事務局長、米田・関口の各事務局次長、松井書記、国公労連から國枝中執が参加、人事院側は、給与局給与第1課の奈良間課長補佐、職員福祉局職員福祉課の澤田課長補佐が対応しました。
野村議長は、はじめに「7月25日の人事院前行動では、国・地方自治体の公務員賃下げのもとで、労働基本権制約の『代償措置』としての勧告制度の役割発揮を求める声がつづいた。その際、人事院総裁への要求署名を提出したところだが、その後も署名が続々と届いている。署名に寄せられた切実な要求を人事院は真剣に受けとめるべきだ」とのべ、26,388人分(総計11万6千人分)の署名を積み上げ、人事院からの回答を求めました。
人事院側は、以下のように回答しました。
【人事院最終回答】
1、人事院勧告・報告は、8月8日(木)となる予定である。
2、官民較差と月例給について
(1)月例給の官民較差については、給与減額支給措置による減額前の給与額に基づく較差と給与減額支給措置による減額後の給与額に基づく較差を算出した。その上で、本年の勧告の前提となる官民比較については、昨年と同様、給与減額支給措置による減額前の給与額に基づき行うこととした。
官民較差は、極めて小さいもので、官民給与はほぼ均衡していると見込まれる。したがって、月例給の改定は見送る予定である。
(2)特別給についても同様に、官民の支給月数は均衡しているものと見られ、支給月数の改定はない見込みである。
3、雇用と年金の接続について(再任用職員の給与)
年金の支給開始年齢の段階的な引上げに伴う雇用と年金の接続については、本年3月に閣議決定された「国家公務員の雇用と年金の接続について」によって、現行の再任用の仕組みにより希望者を再任用するものとされた。定年延長ではなく再任用することとしたことは、雇用と年金の接続を図るための当面の措置として、やむを得ないものと考えるが、年金支給開始年齢が62歳に引き上げられる平成28年度までには、平成26年度からの再任用の運用状況を随時検証しつつ、平成23年の人事院の意見の申出に基づく段階的な定年の引上げもを含め再検討がなされる必要があると考える。
また、人事院は、同閣議決定における要請を踏まえ、給与制度上の措置について検討を行っているところであるが、再任用職員の給与水準や手当の見直しについては、「平成26年職種別民間給与実態調査」において公的年金が全く支給されない再雇用者の給与の具体的な実態を把握した上で、平成26年4月における再任用職員の職務や働き方等の人事運用の実態等を踏まえつつ、必要な検討を進めることとしたいと考えている。
4、非常勤職員等の処遇改善
非常勤職員の給与については、各府省において、人事院の発出した指針(平成20年8月)に沿った運用がなされることが重要と考えており、引き続き適正かつ円滑な運用が図られるよう取り組んで参りたいと考えている。
また、非常勤職員の休暇等については、従来より民間の状況等を考慮し、措置してきたところであり、今後ともこうした考え方を基本に民間の動向等に留意しつつ、適切に対応して参りたいと考えている。
期間業務職員制度は、職員団体を始め各方面の意見等を踏まえ、平成22年10月に導入したものであるが、人事院としては、各府省において本制度を設けた趣旨に則った適正な運用がなされるよう引き続き取り組んで行きたいと考えている。
5、給与制度の総合的見直しについて
給与構造改革に関する勧告を行ってから8年が経過し、我が国の社会経済情勢は急激な変化を続けている。こうした中、国家公務員給与については、一層の取組を進めるべき課題が種々生じてきている。
このような状況を踏まえ、国家公務員の給与に対する国民の理解を得るとともに、公務に必要な人材を確保し、職員の士気や組織の活力の維持・向上を図っていくため、俸給表構造、諸手当の在り方を含め、給与制度の総合的な見直しについて検討を進め、早急に結論を得ることとしたいと考えている。
今年の勧告時の報告では、そのような認識に基づいて、給与制度の総合的な見直しについて検討を行うことを表明し、具体的な検討課題、検討内容等について述べることとしている。
主な検討課題は、
○ 民間の組織形態の変化への対応
○ 地域間の給与配分の在り方
○ 世代間の給与配分の在り方
○ 職務や勤務実績に応じた給与。具体的には、
・人事評価の適切な実施と給与への反映
・技能・労務関係職種の給与の在り方
・諸手当の在り方
などである。
なお、これらの課題の検討に当たっては、職員団体や各府省等の意見も聞きながら進めていく所存である。
6、国家公務員制度改革等に関する報告について
以上のほか、国家公務員制度改革等に関して報告することとしている。
報告では、国家公務員制度改革について、これまでの改革の経緯を踏まえた留意点を示すとともに、幹部職員人事の一元管理、内閣人事局の設置と人事院の機能移管、自律的労使関係制度などについて、主な論点、留意点等を整理して示すこととしている。
そのほか、人事行政上の諸課題への取組として、能力・実績に基づく人事管理の推進のため、①幹部職員等の育成・選抜に係る人事運用の見直し等、②人事評価の適切な実施・活用、について述べるとともに、採用試験等の見直しとして、①国家公務員採用試験への英語試験の活用、②就職活動時期の見直しへの対応、についても言及することとしている。また、女性国家公務員の採用・登用の拡大と両立支援についても述べることとし、両立支援の推進に関しては、① 配偶者帯同休業の導入の意見の申出と多様で弾力的な勤務時間制度の検討、② 男性職員の育児休業取得の促進、③ 超過勤務の縮減について言及することとしている。
7、配偶者の転勤に伴う離職への対応について(配偶者帯同休業制度に関する意見の申出)
人事院は、同じ日に、国会及び内閣に対し、配偶者帯同休業制度に関する意見の申出を行う予定である。
配偶者帯同休業制度は、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業の制度を設けることにより、有為な職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とするものであり、意見の申出の主な内容は次のとおりである。
(1) 休業の対象となる職員について
外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する職員とする。(常時勤務することを要しない職員等を除く。)
なお、配偶者は国家公務員に限らない。
(2) 休業の承認について
職員の請求に基づき、任命権者が、職員の勤務成績等を考慮した上で、公務の運営に支障がないと認めた場合に承認することができることとする。
(3) 休業の期間について
1回の休業期間は3年を超えない範囲内の期間とする。(3年を超えない範囲内であれば、1回に限り期間の延長が可能)
(4) 休業の効果について
休業の期間中は、職員としての身分は保有するが、職務に従事せず、給与は支給しない。
(5) 休業に伴う任期付採用及び臨時的任用について
任命権者は、職員の配置換え等の方法により配偶者帯同休業を請求した職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、請求の期間を限度として、任期付採用又は臨時的任用を行うことができるものとする。
約60年ぶりに「勧告なし、報告のみ」の事態に
回答にかかわって、黒田事務局長は以下の点について質し、回答を求めました(以下、○組合側、●人事院側)。
○ 月例給・特別給の改定を見送り、その他、給与にかかわる改定事項がなければ、正式には「人事院報告」なのか。そうだとすれば「報告」にとどめた例は過去にあったのかどうか。
● 国公法28条にもとづく勧告はしないが、ただし同条項には、少なくとも年1回の報告が義務づけられており、これにもとづく「人事院報告」を国会と内閣に対しておこなう。勧告しないのはラスパイレス方式で比較がはじまって以来初であり、それ以前では昭和29(1954)年に報告にとどめた例がある。
○ 減額前と減額後の官民較差を算出したと言うが、それぞれどれくらいか。とりわけ、減額後の較差はどれくらいか。昨年と比べてどうか。
● 数字を明らかにすることは差し控えるが、減額前の較差はきわめて小さく、減額後で比較すると、民間を相当程度下回っている。
○ 減額前、減額後の較差を算出しながら、減額前で官民比較した理由は何か。
● 昨年と同様に、東日本大震災という未曾有の国難に対処するため、臨時特例措置とし給与減額がおこなわれていることを考慮した。
○ 非常勤職員の処遇改善要求への回答があったが、報告に問題意識をのべるということか。
● 今回の報告では触れない。
「相当程度民間を下回っている」のに勧告しないのは国公法違反だ
以上をふまえて、黒田事務局長は以下の点を主張しました。
○ 本日の回答は断じて認められない。実支給額にもとづく比較による「給与回復・改善勧告」という要求に背をむけた回答に厳しく抗議する。現実に、相当程度民間を下回っているなかでの勧告見送りは、国公法28条の「情勢適応の原則」にもとづく人事院勧告制度が、まったく機能していないことを明らかにしている。労働基本権回復が遠のくなかで、人事院が労働基本権制約の代償機関としての役割を果たしていないことに失望を感じる。
○ 非常勤職員の賃金や休暇制度などの改善を強く求めてきたにもかかわらず、昨年に続いて報告でもいっさい触れないというのは、「ゼロ回答」に等しい。非正規労働者が占める割合が全労働者の4割にせまり、貧困と較差がひろがるなかで、公務が先行して賃金・労働条件の改善をめざすべきだ。少なくとも給与制度の見直しの課題の一つに位置づけるくらいの問題意識を持て。
○ 給与制度の総合的な見直しにあげた地域間配分の見直しは、昨年の報告で示された「最近の傾向を見ると地域別の較差は縮小し、安定的に推移してきていると認められる」とする検証結果からすれば必要なのか疑問だ。また、地域の給与見直しは、地方公務員はもとより地域経済にもかかわる課題だ。きわめて慎重におこなうべき。
また、交渉団からは、以下のような厳しい追及がつづきました。
○ 人事院は職員の実態を見ていない。賃金が下がるなかでも、住民のために懸命に仕事をしている。そうした努力に応えるべきだ。また、60歳を過ぎても年金が支給されず、再任用者は、賃金が確定しないなか、生活不安のもとで働かなければならない。なぜ来年にならないと給与水準を示せないのか。
○ 減額前で官民賃金を比較するということが、本当に精緻な調査と言えるのか。恣意的な調査結果は、人事院としての価値をおとしめるだけだ。人事院の信頼そのもを失う。
○ 賃下げによって子どもの進学を断念した家庭もある。そうした厳しい実態を、人事院はくみ取る姿勢はあるのか。
○ 非常勤職員は、厳しい賃金・労働条件におかれて、常勤職員と同じ仕事をしている。そうした非常勤職員の声を、人事院はどれだけ受けとめているのか。
労働基本権制約の「代償措置」としての役割を果たせ
人事院側は、「職員のみなさんにとって、厳しい措置になっていることは認識している。ただ、減額措置は、民間準拠にもとづく勧告とは別に、臨時特例措置にもとづくもので、法律によって措置されているものだ。人事院としてはそれを考慮した」「非常勤職員の処遇改善の要求に対しては、改善の方向を回答しており、まったくの『ゼロ回答』ではない」「指摘の通り昨年の給与報告で、05年の給与構造改革による地域間給与配分の見直しについて最終的な検証結果を示したが、その際、今後とも各地域の官民給与の動向等に注視していくことも報告したところだ」などと回答しました。
その後、労働基本権が踏みにじられるなかで、賃下げが強行されてきたことに対して、労働基本権制約の「代償措置」としての人事院勧告の役割にかかわって、人事院と交渉団との間でやり取りがつづきましたが、平行線をたどりました。
こうしたもと、最後に野村議長は、「実支給額で官民比較すれば、今年も昨年と同様に公務が下回っていることが明らかであるにもかかわらず、月例給・一時金ともに据え置くことは、地方自治体にまでひろがっている政府による賃下げ攻撃に荷担するものであり、認められない」とのべたうえ、「人事院勧告が労働基本権制約の『代償措置』であることを、あらためて人事院は明確に示すべきだ。労働基本権が制約されるもとでは、人事院勧告制度が、公務労働者の賃金・労働条件改善にむけて本来の役割を果たすべきと繰り返しのべてきたが、そうした要求や願い、期待にも背をむけたものだ」と不当な回答に強く抗議して、最終交渉を閉じました。
以 上