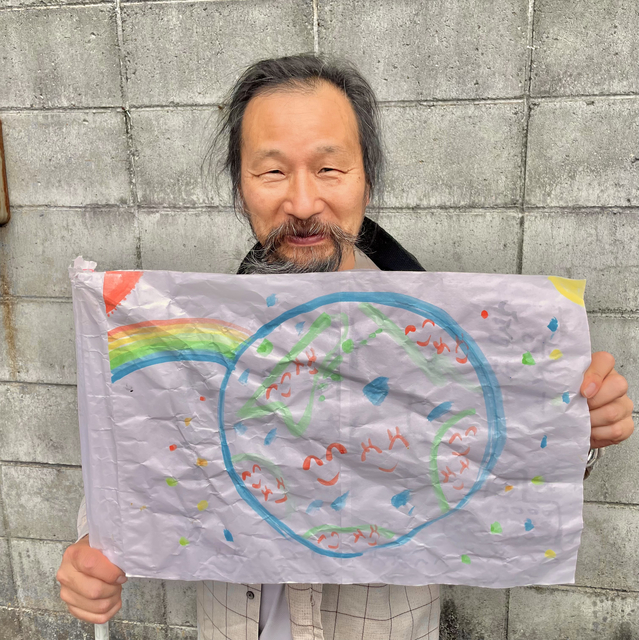みなさん こんにちは
いつもありがとうございます。
親子にわたり
お世話になっている
神主さんが
水のことについて
大切なことを書かれていたので
少しご紹介いたしますね。
どうぞよろしくお願いいたします。
「きれいな水を」
(元の文章から抜粋し、脚色を交えてお届けします。詳しくは「自然」872号をご覧ください)
水道水をそのまま飲めるのは
20か国ほどだそうです。
ほんとうに日本は水に恵まれている国ですね。
筆者は、昨年の春に
神奈川県横浜市に
人事異動により引っ越されました。
横浜市の水の取水している場所は
なんと
お隣の県の山梨県。
山梨県南都留郡道志村 と呼ばれる
丹沢山塊の北側の村に
横浜の水源があるとのことです。
距離にして約30キロ
そんな遠くから標高差を利用した
自然下流方式で
相模原市内の水道道を通り
横浜の浄水場まで送られてくるそうです。
山梨県の道志村は、降雨量が多く
自然豊富な村です。
そして豊かな自然にはぐくまれた水質は
きわめて良好で
世界の船乗りたちに(横浜は 日本有数の港)
「赤道を超えても腐らない水」と称賛された水を
供給している。
その水道の経営は
大正5年にさかのぼるということで
令和2年の夏
神奈川県を除いた
関東6都県に水を供給する
利根川水系のダムの貯水率が過去25年間で
最低の水準となり
各地で水不足が危惧されましたが、
6都県を
はために
独自の水源がある横浜市は
渇水のおそれがなかった。
今
グーグルマップで
山梨県 道志村の
横浜市の水源のあたりを
見ると
たしかに
たくさんの広葉樹に覆われた
山林が広がっています。
広葉樹は落ち葉を毎年落とします。
その落ち葉は何年も積み重なり
地層のようになるので、その間に
水が蓄えられて
かなりな降雨でも天然のダムの役割をして
洪水が起きにくくなります。
そしてなにより、針葉樹に比べて
土砂災害が格段と少ないのも
広葉樹の森の特徴です。
戦後の急激な広葉樹の伐採によって
そのバランスが崩れています。
そのバランスを取り戻すためにも
広葉樹を増やして
健全な森づくりを
私たちがしていく必要があります。
自然社本宮のことを愛していた
父は
やはり
「広葉樹をもうちょっと増やさないと・・・」
と言っていました。
父の遺志を継ぎ
自然社本宮にもっともっと広葉樹を
みなさんとともに植えていきたいと
思います。
先日自然社本宮の木を伐採してくださった
「空師」さんたちも
おっしゃっていましたが
自然に放っておいたら
広葉樹の森になる!
そうなんです。
はげ山は
放っておいたら
広葉樹の多い森になるんです。
もちろん、スギやヒノキも生えますが
ほとんどが広葉樹の森になるんです。
これが
自然なんですね~
皆様のご健康とご多幸を
お祈りいたします。