県民10万人あたりの「百寿者率」が5年連続でトップの島根県。同県の百寿者たちは、これまでなにを心がけ、今どう過ごしているのか。県内最長寿を含む5人にインタビューを試みたが、100歳を超えてインタビューに答えられる、という健康の秘訣はどこに?
***
松江市の西南に位置する雲南市に住む安井信子さん(100)を自宅に訪ねたが、そこは曲がりくねった山道の先。玄関から腰が真っすぐの女性が現れたので、娘さんかと思うと本人で、
「夫が7年ほど前に亡くなってからは、ここで一人暮らしをしています」
と、こう語りはじめた。
「朝は6時前に起きてご飯を食べます。白米とみそ汁、卵焼きなんかですね。家の前の畑で白菜や大根を作っていて、みそ汁には畑で採れた大根の葉っぱや春菊なんかも入れます。緑のものは血液をサラサラにしますからね。肉と魚なら魚のほうが好き。カルシウムがあるから食べにゃいかん」
どうやら健康オタクでもある安井さん、齢百にしてほぼ自立している。
「種まきから収穫まで全部一人でやります。夜ご飯でも畑で採れた白菜を煮たりしますね。柔らかくなって消化にいいから、何でも煮物にして食べる。ほかにやってるのは散歩。背筋を伸ばして手をしっかり振って、5分、10分歩く。肩こりもないし、どっこも痛くない。血圧も上が130くらいで、息子よりだいぶ低い」
お茶の水健康長寿クリニックの白澤卓二院長は、
「百寿者は寝たきりか自立しているかのどちらか。生活の自立は長寿を考えるうえで非常に重要で、それには自分で歩ける、自分の頭で判断できる、という二つの条件が必要となります」
と語るが、安井さんはそれらの条件に見事に適う。
同じ雲南市に住む岸本キミエさん(101)はデイサービスに通うが、そこで、
「洗濯物を畳んだり、絵を描いたり、踊ったりします。若い人たちは踊らないんだけど、私は若い先生と一緒に踊るの。踊りはだれにも負けません。洗濯物も一番きちんと畳んで、崩れないように重ねる。だらしない人のは崩れたりするの。家に帰ったら草取りとかする。草取りも速いですよ」
90歳くらいまで水墨画の達人だったという岸本さん。祭りで踊るのも好きで、家族によれば「熱中しやすい性格」だとか。食事は家族と同じものを食べており、
「3食、白いご飯。嫌いなものはないね。お腹いっぱい、何でも食べます。肉も魚も野菜もちゃんと食べる。寝るのは9時ごろかな」
どんなときに楽しいと感じるのだろうか。
「嫌なことはありませんわ。草取りでも何でも楽しい」
ストレスも最小限で済んでいるように感じられた。
松江市の山崎ミネ子さん(101)は今年、しまね健康超寿者に選ばれた。岸本さんと趣味が似ている。
「60歳くらいで書道を始め、今でも書くのが一番好きですわ。段位は10段までいって、県の展覧会に何度も入選しました。俳句や水墨画もやっていました」
今、週に3日通うデイサービスでは、
「足し算、引き算、掛け算とか計算したり、書き物したりしていますわ」
元気の秘訣を尋ねると、
「自然にね。長生きのために食べもの制限とかしちょらんね。甘いものと辛いものは好きじゃないから、カレーとキムチは食べません。娘や孫、ひ孫たちと一緒に同じものを食べます。シジミ汁も好き。魚が好きだけどお肉も食べますわ。いい加減なもんだね」
「人生はこれからだ」
青砥武一さん(104)も松江市在住。やはり食べものに頓着しないそうで、
「朝は白米やパンです。野菜も食べるし、魚もあれば食べる。昼や夕飯も家族と同じものを食べますわ。ひ孫が時々買ってくるケンタッキーも好き。嫌いなものはない。ただ軍隊にいたときのクセで速く食べて、孫たちに怒られます」
家族と一緒に、選り好みせず食べているそうだ。
「戦争から帰って米や野菜、黒毛和牛の繁殖を80すぎまで続け、月に1回は、松江中心部の護國神社の朝の清掃奉仕に、自転車で14キロくらい走って通ってました」
右耳はほとんど聞こえないそうだが、左耳に話しかければ、こうして返事をもらえる。そして今も、
「新聞は毎日読んでいる。あとひ孫が買ってきた計算ドリルを、もう3、4冊やりました」
最後に紹介するのは、江津(ごうつ)市に住む明治42年生まれの高田良夫さん。県内最高齢108歳だ。今は施設で車椅子の生活だが、昨年4月に転んで脚を圧迫骨折するまでは自宅ですごし、草むしりもしていたという。
なにしろ90歳まで毎朝晩、犬の散歩で1キロ歩き、93歳まで自転車に乗り、100歳をすぎても畑に出ていたという鉄人である。
「ここまでやってこれたのは、真面目に働いてきたからだと思います」
国民学校を出て陶工に丁稚奉公したのち、徳山曹達(ソーダ)に就職。36歳で徴兵されて台湾に送られたが、幸い食糧事情があまり悪くなかった。帰還後は70歳すぎまで陶工を務めたという。
百寿者の例に漏れず、好き嫌いがない。昔からタバコも吸わず、晩酌は毎回1合未満。ただ、施設に入るまで40年間、毎日「養命酒」を飲んでいたという。
「何でも美味しく食べますし、ゆっくり、よく噛んで食べています。昔、たくさん噛めば唾液がたくさん出るから、よく噛んで食べるようにと、牛は何度も吐いて噛み砕いて食べるから糞がほどけてるんだ、と教わりました」
車椅子は自分でこぐ。
「60くらいで死ぬと思ってたら、とうとう108です。先生も、家族は長生きするだけでも嬉しいものだと言ってくださるので、男性日本一の長寿になれるよう頑張りたいです」
前出の白澤院長は、
「私が会った百寿者で“もう自分の人生は終わりに近づいている”と悲観している方はいない。逆に“人生はこれからだ”と、とにかく前向きで肯定的です」
と語るが、それは5人すべてに共通していた。
***
松江市の西南に位置する雲南市に住む安井信子さん(100)を自宅に訪ねたが、そこは曲がりくねった山道の先。玄関から腰が真っすぐの女性が現れたので、娘さんかと思うと本人で、
「夫が7年ほど前に亡くなってからは、ここで一人暮らしをしています」
と、こう語りはじめた。
「朝は6時前に起きてご飯を食べます。白米とみそ汁、卵焼きなんかですね。家の前の畑で白菜や大根を作っていて、みそ汁には畑で採れた大根の葉っぱや春菊なんかも入れます。緑のものは血液をサラサラにしますからね。肉と魚なら魚のほうが好き。カルシウムがあるから食べにゃいかん」
どうやら健康オタクでもある安井さん、齢百にしてほぼ自立している。
「種まきから収穫まで全部一人でやります。夜ご飯でも畑で採れた白菜を煮たりしますね。柔らかくなって消化にいいから、何でも煮物にして食べる。ほかにやってるのは散歩。背筋を伸ばして手をしっかり振って、5分、10分歩く。肩こりもないし、どっこも痛くない。血圧も上が130くらいで、息子よりだいぶ低い」
お茶の水健康長寿クリニックの白澤卓二院長は、
「百寿者は寝たきりか自立しているかのどちらか。生活の自立は長寿を考えるうえで非常に重要で、それには自分で歩ける、自分の頭で判断できる、という二つの条件が必要となります」
と語るが、安井さんはそれらの条件に見事に適う。
同じ雲南市に住む岸本キミエさん(101)はデイサービスに通うが、そこで、
「洗濯物を畳んだり、絵を描いたり、踊ったりします。若い人たちは踊らないんだけど、私は若い先生と一緒に踊るの。踊りはだれにも負けません。洗濯物も一番きちんと畳んで、崩れないように重ねる。だらしない人のは崩れたりするの。家に帰ったら草取りとかする。草取りも速いですよ」
90歳くらいまで水墨画の達人だったという岸本さん。祭りで踊るのも好きで、家族によれば「熱中しやすい性格」だとか。食事は家族と同じものを食べており、
「3食、白いご飯。嫌いなものはないね。お腹いっぱい、何でも食べます。肉も魚も野菜もちゃんと食べる。寝るのは9時ごろかな」
どんなときに楽しいと感じるのだろうか。
「嫌なことはありませんわ。草取りでも何でも楽しい」
ストレスも最小限で済んでいるように感じられた。
松江市の山崎ミネ子さん(101)は今年、しまね健康超寿者に選ばれた。岸本さんと趣味が似ている。
「60歳くらいで書道を始め、今でも書くのが一番好きですわ。段位は10段までいって、県の展覧会に何度も入選しました。俳句や水墨画もやっていました」
今、週に3日通うデイサービスでは、
「足し算、引き算、掛け算とか計算したり、書き物したりしていますわ」
元気の秘訣を尋ねると、
「自然にね。長生きのために食べもの制限とかしちょらんね。甘いものと辛いものは好きじゃないから、カレーとキムチは食べません。娘や孫、ひ孫たちと一緒に同じものを食べます。シジミ汁も好き。魚が好きだけどお肉も食べますわ。いい加減なもんだね」
「人生はこれからだ」
青砥武一さん(104)も松江市在住。やはり食べものに頓着しないそうで、
「朝は白米やパンです。野菜も食べるし、魚もあれば食べる。昼や夕飯も家族と同じものを食べますわ。ひ孫が時々買ってくるケンタッキーも好き。嫌いなものはない。ただ軍隊にいたときのクセで速く食べて、孫たちに怒られます」
家族と一緒に、選り好みせず食べているそうだ。
「戦争から帰って米や野菜、黒毛和牛の繁殖を80すぎまで続け、月に1回は、松江中心部の護國神社の朝の清掃奉仕に、自転車で14キロくらい走って通ってました」
右耳はほとんど聞こえないそうだが、左耳に話しかければ、こうして返事をもらえる。そして今も、
「新聞は毎日読んでいる。あとひ孫が買ってきた計算ドリルを、もう3、4冊やりました」
最後に紹介するのは、江津(ごうつ)市に住む明治42年生まれの高田良夫さん。県内最高齢108歳だ。今は施設で車椅子の生活だが、昨年4月に転んで脚を圧迫骨折するまでは自宅ですごし、草むしりもしていたという。
なにしろ90歳まで毎朝晩、犬の散歩で1キロ歩き、93歳まで自転車に乗り、100歳をすぎても畑に出ていたという鉄人である。
「ここまでやってこれたのは、真面目に働いてきたからだと思います」
国民学校を出て陶工に丁稚奉公したのち、徳山曹達(ソーダ)に就職。36歳で徴兵されて台湾に送られたが、幸い食糧事情があまり悪くなかった。帰還後は70歳すぎまで陶工を務めたという。
百寿者の例に漏れず、好き嫌いがない。昔からタバコも吸わず、晩酌は毎回1合未満。ただ、施設に入るまで40年間、毎日「養命酒」を飲んでいたという。
「何でも美味しく食べますし、ゆっくり、よく噛んで食べています。昔、たくさん噛めば唾液がたくさん出るから、よく噛んで食べるようにと、牛は何度も吐いて噛み砕いて食べるから糞がほどけてるんだ、と教わりました」
車椅子は自分でこぐ。
「60くらいで死ぬと思ってたら、とうとう108です。先生も、家族は長生きするだけでも嬉しいものだと言ってくださるので、男性日本一の長寿になれるよう頑張りたいです」
前出の白澤院長は、
「私が会った百寿者で“もう自分の人生は終わりに近づいている”と悲観している方はいない。逆に“人生はこれからだ”と、とにかく前向きで肯定的です」
と語るが、それは5人すべてに共通していた。











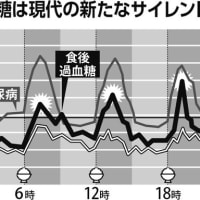

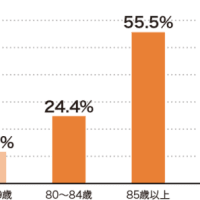
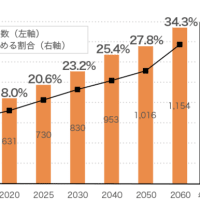

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます