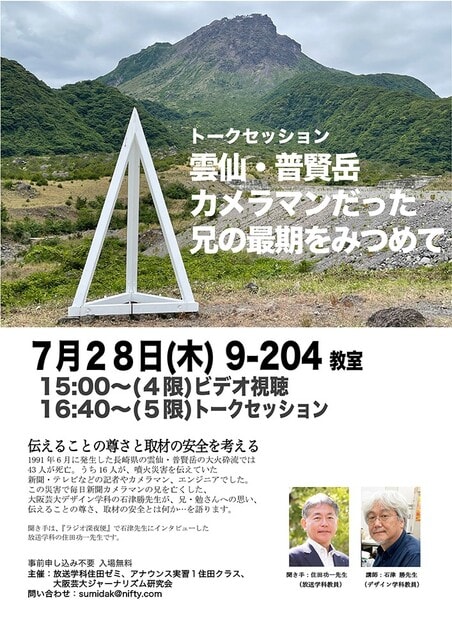<最後の「防空情報放送」>///////////////////////////
リポーター
退避放送はわずかの差で間に合いませんでした。
プルトニウム爆弾の一瞬の閃光にさらされた人々。長崎の原爆資料保存委員会の調査によりますと、亡くなった人7万4000人、重軽傷者7万5000人にのぼりました。
8月9日当日、参謀のもとで防空情報を担当していた将校・毎田一郎さんは、私たちの取材に対して、最後に、こう話してくれました。
毎田一郎さんの証言
「あれはねえ、爆弾が落ちて炸裂した後、ラジオを聞いておるものがおったかどう知りませんけど、30分ぐらいそういう情報を流してましたなあ。退避せよ、退避せよという情報を流してました。それは手遅れであったなあと」
「私たちの立場からすれば、いわゆる空襲警報を出すということはですね、それだけ国内の生産がストップするわけですよね。そういうことがやっぱり、なかなか空襲警報を出すのは慎重でなきゃならんという考えに結びついてましたから」
「まあ、考えてみれば3日前に広島にあれが落とされとるということが教訓になって、もっと頭に染み込んでおればね、もっと警戒したでしょうけれどもね」
リポーター
なぜ、広島の教訓を生かせないまま、長崎は8月9日を迎えたのか。
そして防空情報放送は一体どういう役割を果たし得たのか。
拓殖大学教授・秦郁彦さんに聞きました。
秦郁彦教授 解説
「広島のあとなのに、なぜ長崎市民の退避ということが間に合わなかったのか。今考えて見ると、非常に残念な気がしますね」
「ひとつにはですね、やはり陸軍中央部の誤った判断も影響していたと思います。これは8月9日の終戦を決めた御前会議の席上で阿南陸軍大臣が『アメリカが持っている原爆は一発しかないはずだ』と。これはぜんぜん根拠のないことなんですけど、もうこの段階になりますとね、根拠がなくてもなんとかして楽観的な見通しにすがりつこうと。そして、本土決戦に持ち込みたいという、そういう頑妄が、この発言に集約されていると思うんですね。それを議論している席上に、2発目が長崎に落ちたという情報が入りまして、これが終戦決定の非常に大きなきっかけになるわけですね」
「戦争中の日本人は徹底的な情報封鎖の中で暮らしておりましてね、この防空情報というのはその中で唯一の“明かり窓”のようなものでありまして、でもちろんそこから流れてくる情報だけでは十分じゃない。しかし、まあ、国民それぞれですね、自分の判断力、口コミで伝わって来た情報。そういうものを総合してですね、対処していったと」
録音素材
.玉音放送 F.I..
「爾(なんじ)臣民ノ衷情󠄁モ朕󠄁善ク之ヲ知ル 然レトモ朕󠄁ハ時運󠄁ノ趨ク所󠄁 堪ヘ難キヲ堪ヘ忍󠄁ヒ難キヲ忍󠄁ヒ 以テ萬世ノ爲ニ太平󠄁ヲ開カムト欲ス 朕󠄁ハ茲ニ…」→B.G
ナレーション
昭和二十年八月十五日正午、ラジオは全国民に決定的な情報を伝え始めた。
ナレーション
天皇の玉音放送によって、戦争は終結した。
これが、いわば、防空情報放送の最後であった。
効果音
・玉音放送
「…世界ノ進󠄁運󠄁ニ後レサラムコトヲ期󠄁スヘシ 爾臣民其レ克ク朕󠄁カ意󠄁ヲ體セヨ」
<クレジット>///////////////////////////
エンド音楽 → B.G.
アナウンス
『特集・長崎市民は退避せよ〜防空情報は何を伝えたか』
取材協力
秦郁彦(はた・いくひこ)
荒木正人(あらき・まさと)
泉洋二郎(いずみ・ようじろう)
斉藤聰(さいとう・さとし)
島津矩通(しまず・のりみち)
杉原宏子(すぎはら・ひろこ)
高松貞雄(たかまつ・さだお)
永田 収(ながた・おさむ)
半沢和郎(はんざわ・かずお)
広内信夫(ひろうち・のぶお)
松野秀雄(まつの・ひでお)
松本憲夫(まつもと・のりお)
偕行社(かいこうしゃ)
語り:長谷川勝彦(ナレーション)
報告:住田功一(リポーター)
取材:恩蔵憲一
技術:岩崎延雄
音響効果:川崎清
制作:渡辺俊雄、佐野剛平
『特集・長崎市民は退避せよ〜防空情報は何を伝えたか』を終わります。
エンド音楽 B. G. → F. O.
了
----【目次】---------------------------------------------------------------------
ラジオ番組『長崎市民は退避せよ〜防空情報放送は何を伝えたか』について
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/afb253570114e98ddc000d5120068743
①プロローグ〜奇妙な退避放送
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/b09ad1a93be448d330325aae4e919894
②八月九日、長崎<1>
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/e67a9aec6430e55282e5dc78a4353e74
③終戦前年に始まった「防空情報放送」
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/ca399be29520ddf6bda4ce5046f8f59e
④放送室からの悲痛な叫び
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/90448a443b5fd4d6f043a6031b176f60
⑤八月九日、長崎<2>
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/e704ec92a9161925a03d7f1739179110
⑥エピローグ〜最後の「防空情報放送」
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/dae1cfaf8ec2a0bebee13100e14cb269
リポーター
退避放送はわずかの差で間に合いませんでした。
プルトニウム爆弾の一瞬の閃光にさらされた人々。長崎の原爆資料保存委員会の調査によりますと、亡くなった人7万4000人、重軽傷者7万5000人にのぼりました。
8月9日当日、参謀のもとで防空情報を担当していた将校・毎田一郎さんは、私たちの取材に対して、最後に、こう話してくれました。
毎田一郎さんの証言
「あれはねえ、爆弾が落ちて炸裂した後、ラジオを聞いておるものがおったかどう知りませんけど、30分ぐらいそういう情報を流してましたなあ。退避せよ、退避せよという情報を流してました。それは手遅れであったなあと」
「私たちの立場からすれば、いわゆる空襲警報を出すということはですね、それだけ国内の生産がストップするわけですよね。そういうことがやっぱり、なかなか空襲警報を出すのは慎重でなきゃならんという考えに結びついてましたから」
「まあ、考えてみれば3日前に広島にあれが落とされとるということが教訓になって、もっと頭に染み込んでおればね、もっと警戒したでしょうけれどもね」
リポーター
なぜ、広島の教訓を生かせないまま、長崎は8月9日を迎えたのか。
そして防空情報放送は一体どういう役割を果たし得たのか。
拓殖大学教授・秦郁彦さんに聞きました。
秦郁彦教授 解説
「広島のあとなのに、なぜ長崎市民の退避ということが間に合わなかったのか。今考えて見ると、非常に残念な気がしますね」
「ひとつにはですね、やはり陸軍中央部の誤った判断も影響していたと思います。これは8月9日の終戦を決めた御前会議の席上で阿南陸軍大臣が『アメリカが持っている原爆は一発しかないはずだ』と。これはぜんぜん根拠のないことなんですけど、もうこの段階になりますとね、根拠がなくてもなんとかして楽観的な見通しにすがりつこうと。そして、本土決戦に持ち込みたいという、そういう頑妄が、この発言に集約されていると思うんですね。それを議論している席上に、2発目が長崎に落ちたという情報が入りまして、これが終戦決定の非常に大きなきっかけになるわけですね」
「戦争中の日本人は徹底的な情報封鎖の中で暮らしておりましてね、この防空情報というのはその中で唯一の“明かり窓”のようなものでありまして、でもちろんそこから流れてくる情報だけでは十分じゃない。しかし、まあ、国民それぞれですね、自分の判断力、口コミで伝わって来た情報。そういうものを総合してですね、対処していったと」
録音素材
.玉音放送 F.I..
「爾(なんじ)臣民ノ衷情󠄁モ朕󠄁善ク之ヲ知ル 然レトモ朕󠄁ハ時運󠄁ノ趨ク所󠄁 堪ヘ難キヲ堪ヘ忍󠄁ヒ難キヲ忍󠄁ヒ 以テ萬世ノ爲ニ太平󠄁ヲ開カムト欲ス 朕󠄁ハ茲ニ…」→B.G
ナレーション
昭和二十年八月十五日正午、ラジオは全国民に決定的な情報を伝え始めた。
ナレーション
天皇の玉音放送によって、戦争は終結した。
これが、いわば、防空情報放送の最後であった。
効果音
・玉音放送
「…世界ノ進󠄁運󠄁ニ後レサラムコトヲ期󠄁スヘシ 爾臣民其レ克ク朕󠄁カ意󠄁ヲ體セヨ」
<クレジット>///////////////////////////
エンド音楽 → B.G.
アナウンス
『特集・長崎市民は退避せよ〜防空情報は何を伝えたか』
取材協力
秦郁彦(はた・いくひこ)
荒木正人(あらき・まさと)
泉洋二郎(いずみ・ようじろう)
斉藤聰(さいとう・さとし)
島津矩通(しまず・のりみち)
杉原宏子(すぎはら・ひろこ)
高松貞雄(たかまつ・さだお)
永田 収(ながた・おさむ)
半沢和郎(はんざわ・かずお)
広内信夫(ひろうち・のぶお)
松野秀雄(まつの・ひでお)
松本憲夫(まつもと・のりお)
偕行社(かいこうしゃ)
語り:長谷川勝彦(ナレーション)
報告:住田功一(リポーター)
取材:恩蔵憲一
技術:岩崎延雄
音響効果:川崎清
制作:渡辺俊雄、佐野剛平
『特集・長崎市民は退避せよ〜防空情報は何を伝えたか』を終わります。
エンド音楽 B. G. → F. O.
了
----【目次】---------------------------------------------------------------------
ラジオ番組『長崎市民は退避せよ〜防空情報放送は何を伝えたか』について
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/afb253570114e98ddc000d5120068743
①プロローグ〜奇妙な退避放送
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/b09ad1a93be448d330325aae4e919894
②八月九日、長崎<1>
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/e67a9aec6430e55282e5dc78a4353e74
③終戦前年に始まった「防空情報放送」
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/ca399be29520ddf6bda4ce5046f8f59e
④放送室からの悲痛な叫び
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/90448a443b5fd4d6f043a6031b176f60
⑤八月九日、長崎<2>
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/e704ec92a9161925a03d7f1739179110
⑥エピローグ〜最後の「防空情報放送」
https://blog.goo.ne.jp/sumioctopus/e/dae1cfaf8ec2a0bebee13100e14cb269