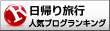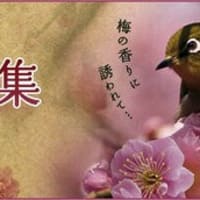当時、円覚(えんがく)上人(しょうにん)の教えを来聴する大衆が数十万人にも及んだので、人々は上人を「十万(じゅうまん)上人(しょうにん)」と呼んでいました。

上人は、正安2年(1300)、壬生寺において「大念佛会(だいねんぶつえ)」という法会を行いました。
この時に上人は、拡声器とてない昔、群衆を前にして最もわかりやすい方法で仏の教えを説こうとしました。
そして、身ぶり手ぶりのパントマイム(無言劇)に仕組んだ持斎融通(じさいゆうづう)念佛を考えついたのです。
これが壬生狂言の始まりと伝えられています。

せりふを用いない宗教劇
近世に入ると庶民大衆の娯楽としても発展し、本来の宗教劇のみならず、 能 や物語などから色々と新しく取材され、曲目やその数も変遷して現在上演されるものは、30曲であります。

しかし、一般の能狂言とは異なり、かね・太鼓・笛の囃子に合わせ、すべての演者が仮面をつけ、一切「せりふ」を用いず無言で演じられる壬生狂言の形は変わらず、娯楽的な演目の中にも勧善懲悪、因果応報の理を教える宗教劇としての性格を今日まで残しています。
この壬狂言を伝承して演じるのは、「壬生大念佛講(こう)」の人達です。

講員は、壬生狂言がその職業ではなく、会社員、自営業などの本職をもち、小学生から80歳台の長老まで、おもに地元に居住する約40名(「衣裳方(かた)」と呼ばれる衣裳の着付担当者以外は全員が男性)が狂言を演じています。

近年は東京、宮城、福岡、沖縄、ハワイなどからも招聘を受けて出張特別公演を行い、数多くの?結縁を得るとともに識者の関心を集めています。

新選組/壬生塚
新撰組は文久3年に壬生で結成されました。

壬生寺の境内には兵法の練習場や武芸などの訓練が行われていた、沖田総司が子どもを集めて遊んでいた、近藤勇など新選組隊士が壬生狂言を鑑賞したなどの記録があるため壬生寺は新選組のゆかりの寺としても有名で、壬生塚には新選組隊士のお墓が残されています。
毎年、池田屋騒動があった7月16日は、「新選組隊士等慰霊供養祭」を新選組隊士の霊を慰めるために行われています。
供養祭では京都新選組同好会の人たちが新選組に扮して壬生寺から八坂神社まで行進するので新選組ファンの方は必見ですね。

夜啼き地蔵
境内にあるお地蔵さんのひとつでもとは壬生寺の塔頭、中院に祀られていたようです。
病気平癒や幼児の夜泣きに御利益があるということで信仰を集めています。

■場 所:壬生寺 壬生寺内 重要文化財 大念仏堂(狂言舞台)にて
■期 間: 10月の連休(体育の日を含む)の3日間
■時 間: 午後1時~5時30分
■料 金
大人 1,000円
中学・高校生500円
当日券で自由席のみです。
予約、指定席はありません。
◎ カメラ・ビデオ・ケータイ等での撮影は、一切禁止です。
◎ 全席当日の自由席のみです。
予約席、指定席はありません。
◎ 満席(400席)の場合、やむなく入場制限をすることがあります。
■アクセス
市バス では 壬生寺道で下車 坊城通りを南へ200m
(JR「京都駅」から26・28・71系統の市バス「壬生寺道」~徒歩3分)
阪急電車 では 大宮で下車 四条通りを西へ信号2つ目の坊城通りを南へ
嵐電(京福電車)では 四条大宮終着駅下車 阪急電車と同じ道順です
自家用車 では 門前にコイン駐車場(8台分)があります
嵯峨野線「丹波口駅」から徒歩10分
■JR「京都駅」から26・28・71系統の市バス「壬生寺道」~徒歩3分
■問い合わせ先TEL 075-841-3381
■公式:http://www.mibudera.com/.
※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。
京都の古都ならhttp://www.e-kyoto.net/

上人は、正安2年(1300)、壬生寺において「大念佛会(だいねんぶつえ)」という法会を行いました。
この時に上人は、拡声器とてない昔、群衆を前にして最もわかりやすい方法で仏の教えを説こうとしました。
そして、身ぶり手ぶりのパントマイム(無言劇)に仕組んだ持斎融通(じさいゆうづう)念佛を考えついたのです。
これが壬生狂言の始まりと伝えられています。

せりふを用いない宗教劇
近世に入ると庶民大衆の娯楽としても発展し、本来の宗教劇のみならず、 能 や物語などから色々と新しく取材され、曲目やその数も変遷して現在上演されるものは、30曲であります。

しかし、一般の能狂言とは異なり、かね・太鼓・笛の囃子に合わせ、すべての演者が仮面をつけ、一切「せりふ」を用いず無言で演じられる壬生狂言の形は変わらず、娯楽的な演目の中にも勧善懲悪、因果応報の理を教える宗教劇としての性格を今日まで残しています。
この壬狂言を伝承して演じるのは、「壬生大念佛講(こう)」の人達です。

講員は、壬生狂言がその職業ではなく、会社員、自営業などの本職をもち、小学生から80歳台の長老まで、おもに地元に居住する約40名(「衣裳方(かた)」と呼ばれる衣裳の着付担当者以外は全員が男性)が狂言を演じています。

近年は東京、宮城、福岡、沖縄、ハワイなどからも招聘を受けて出張特別公演を行い、数多くの?結縁を得るとともに識者の関心を集めています。

新選組/壬生塚
新撰組は文久3年に壬生で結成されました。

壬生寺の境内には兵法の練習場や武芸などの訓練が行われていた、沖田総司が子どもを集めて遊んでいた、近藤勇など新選組隊士が壬生狂言を鑑賞したなどの記録があるため壬生寺は新選組のゆかりの寺としても有名で、壬生塚には新選組隊士のお墓が残されています。
毎年、池田屋騒動があった7月16日は、「新選組隊士等慰霊供養祭」を新選組隊士の霊を慰めるために行われています。
供養祭では京都新選組同好会の人たちが新選組に扮して壬生寺から八坂神社まで行進するので新選組ファンの方は必見ですね。

夜啼き地蔵
境内にあるお地蔵さんのひとつでもとは壬生寺の塔頭、中院に祀られていたようです。
病気平癒や幼児の夜泣きに御利益があるということで信仰を集めています。

■場 所:壬生寺 壬生寺内 重要文化財 大念仏堂(狂言舞台)にて
■期 間: 10月の連休(体育の日を含む)の3日間
■時 間: 午後1時~5時30分
■料 金
大人 1,000円
中学・高校生500円
当日券で自由席のみです。
予約、指定席はありません。
◎ カメラ・ビデオ・ケータイ等での撮影は、一切禁止です。
◎ 全席当日の自由席のみです。
予約席、指定席はありません。
◎ 満席(400席)の場合、やむなく入場制限をすることがあります。
■アクセス
市バス では 壬生寺道で下車 坊城通りを南へ200m
(JR「京都駅」から26・28・71系統の市バス「壬生寺道」~徒歩3分)
阪急電車 では 大宮で下車 四条通りを西へ信号2つ目の坊城通りを南へ
嵐電(京福電車)では 四条大宮終着駅下車 阪急電車と同じ道順です
自家用車 では 門前にコイン駐車場(8台分)があります
嵯峨野線「丹波口駅」から徒歩10分
■JR「京都駅」から26・28・71系統の市バス「壬生寺道」~徒歩3分
■問い合わせ先TEL 075-841-3381
■公式:http://www.mibudera.com/.
※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。
京都の古都ならhttp://www.e-kyoto.net/