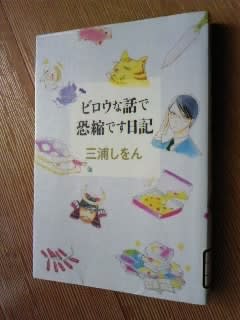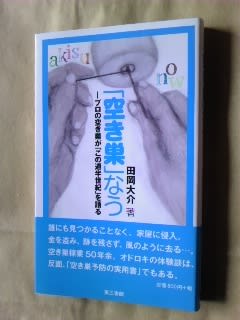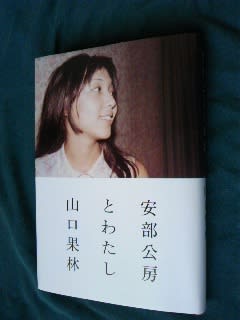《1/16読了 双葉社 2013年刊 【手記 大王製紙前会長 カジノ】 いかわ・もとたか(1964~)》
大王製紙前会長の手記。
御曹司として生まれ育つって、うらやましい反面、なんだか孤独みたい。
何か困難にぶち当たったとき、「みんな似たようなもんだ。おれも同じだ」っていう逃げ(なぐさめ)が許されなくて。
「大王製紙で仕事をしていて「楽しい」と思ったことは、実を言うと一度もない」(262p)
創業者の息子であるお父さんがとにかく完璧な“強い父”として君臨しているのが印象的でした。
大赤字を抱えた子会社を任された意高氏が見事に立て直したのに、後になってそれがすべて父親のお膳立てどおりだったと知ったという気の毒なエピソードも。
さらに、社内で同じ立場の人間がいないから、弱さやダメさを分かち合う相手もいない、仲間と一緒に苦労を背負って乗り越える喜びもない。
交流する“セレブ”たちは金のにおいに集まってきているだけ。
本人に寂しいという自覚がないからよけいにつらい感じがします。
ギャンブルにはまった理由としては、
生育環境に問題があるんじゃないかとか、
なまじ能力があるからこそ、約束された成功じゃもの足りなくて、ヒリヒリするような勝負の快感にのめり込んじゃうんだとか、
そういう解釈を世間はしたがったし、
わたしもそう思ってました。
読んでみた印象としては、それらは半分当たり、半分はずれ、というかんじ。
そして、そうやって分析されることをかたくなに拒む雰囲気に満ちた本でした。
「私は小学生のころから、ゲーム性が高く頭脳プレイを必要とする麻雀を好んできた。その私が、なぜ丁半バクチのようなバカラにはまってしまったのだろう」(170p)
たまたまはまったのがギャンブルだっただけで、他のもの、例えば麻薬だってありえたんじゃないか。
どっちがマシだったのかな。
でも、彼がただの人であれば、たとえバクチにはまっても、106億円あまりの会社の金をつぎ込み、背任で有罪になることはなかったわけで、
そう考えると、“金持ちだからこそできた犯罪”なんですね。
/「熔ける 大王製紙前会長 井川意高の懺悔録」井川意高
大王製紙前会長の手記。
御曹司として生まれ育つって、うらやましい反面、なんだか孤独みたい。
何か困難にぶち当たったとき、「みんな似たようなもんだ。おれも同じだ」っていう逃げ(なぐさめ)が許されなくて。
「大王製紙で仕事をしていて「楽しい」と思ったことは、実を言うと一度もない」(262p)
創業者の息子であるお父さんがとにかく完璧な“強い父”として君臨しているのが印象的でした。
大赤字を抱えた子会社を任された意高氏が見事に立て直したのに、後になってそれがすべて父親のお膳立てどおりだったと知ったという気の毒なエピソードも。
さらに、社内で同じ立場の人間がいないから、弱さやダメさを分かち合う相手もいない、仲間と一緒に苦労を背負って乗り越える喜びもない。
交流する“セレブ”たちは金のにおいに集まってきているだけ。
本人に寂しいという自覚がないからよけいにつらい感じがします。
ギャンブルにはまった理由としては、
生育環境に問題があるんじゃないかとか、
なまじ能力があるからこそ、約束された成功じゃもの足りなくて、ヒリヒリするような勝負の快感にのめり込んじゃうんだとか、
そういう解釈を世間はしたがったし、
わたしもそう思ってました。
読んでみた印象としては、それらは半分当たり、半分はずれ、というかんじ。
そして、そうやって分析されることをかたくなに拒む雰囲気に満ちた本でした。
「私は小学生のころから、ゲーム性が高く頭脳プレイを必要とする麻雀を好んできた。その私が、なぜ丁半バクチのようなバカラにはまってしまったのだろう」(170p)
たまたまはまったのがギャンブルだっただけで、他のもの、例えば麻薬だってありえたんじゃないか。
どっちがマシだったのかな。
でも、彼がただの人であれば、たとえバクチにはまっても、106億円あまりの会社の金をつぎ込み、背任で有罪になることはなかったわけで、
そう考えると、“金持ちだからこそできた犯罪”なんですね。
/「熔ける 大王製紙前会長 井川意高の懺悔録」井川意高