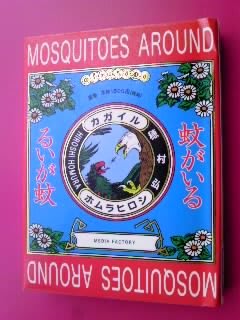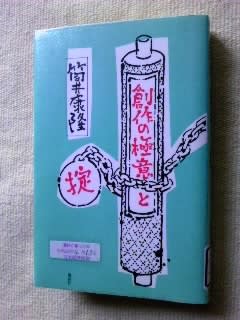《☆☆ 8/4読了 幻冬舎文庫 2014年刊(2011年に幻冬舎から刊行された単行本を文庫化) 【日本のエッセイ】 さかい・じゅんこ(1966~)》
橋田壽賀子(90)は毎日1km泳ぐそうですがそれはともかく、「我々はいかにしておばあさんになってゆくべきか」は中年女にとって切実なテーマです。
それを他ならぬ酒井順子が考察してくれるというんであれば、読まねばなりますまい。
本書は、筆者の祖母・綾子さんを筆頭に、がばいばあちゃん、文楽や歌舞伎の「三婆」、いじわるばあさん、森光子、ターシャ・テューダー、瀬戸内ジャッキー、ジョージア・オキーフ、内海桂子、市川房枝、駒尺喜美、小倉遊亀などなど、あらゆるおばあさんモデルの見本市です。
でも、「すごいおばあさん」は生まれつき「すごいおばあさん」だったわけではなく、女の子だったりお姉さんだったりおばさんだったりした時代があるわけで、そこらへんでどう生きたかの「結果」なんですよね。
おばあさんたちの時代、女であることは現実的に大きなハンデで、彼女たちはそれと戦い、乗り越えてきたツワモノです。
あなたはどのおばあさんになりたい?
続編があるとしたら、篠田桃紅、黒柳徹子、緒方貞子なども取り上げてほしいです。
読後得た「どんなおばあさんになるか」の答えは、「今、どう生きているかの中にある!」です。
わたしたちはある日突然おばあさんに変身するのではなく、今歩いているこの道がおばあさんにつながっているんです。
/「おばあさんの魂」酒井順子
橋田壽賀子(90)は毎日1km泳ぐそうですがそれはともかく、「我々はいかにしておばあさんになってゆくべきか」は中年女にとって切実なテーマです。
それを他ならぬ酒井順子が考察してくれるというんであれば、読まねばなりますまい。
本書は、筆者の祖母・綾子さんを筆頭に、がばいばあちゃん、文楽や歌舞伎の「三婆」、いじわるばあさん、森光子、ターシャ・テューダー、瀬戸内ジャッキー、ジョージア・オキーフ、内海桂子、市川房枝、駒尺喜美、小倉遊亀などなど、あらゆるおばあさんモデルの見本市です。
でも、「すごいおばあさん」は生まれつき「すごいおばあさん」だったわけではなく、女の子だったりお姉さんだったりおばさんだったりした時代があるわけで、そこらへんでどう生きたかの「結果」なんですよね。
おばあさんたちの時代、女であることは現実的に大きなハンデで、彼女たちはそれと戦い、乗り越えてきたツワモノです。
あなたはどのおばあさんになりたい?
続編があるとしたら、篠田桃紅、黒柳徹子、緒方貞子なども取り上げてほしいです。
読後得た「どんなおばあさんになるか」の答えは、「今、どう生きているかの中にある!」です。
わたしたちはある日突然おばあさんに変身するのではなく、今歩いているこの道がおばあさんにつながっているんです。
/「おばあさんの魂」酒井順子