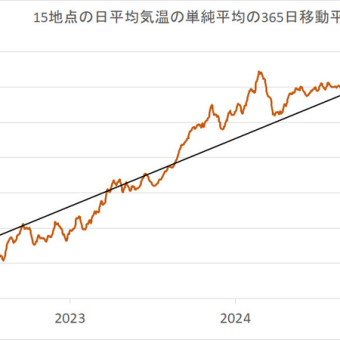WINDOWSのインストールに比べれば、DOSのインストールは、CONFIG.SYS AUTOEXEC.BATなどをメモしておけば、短時間でできるものの、それなりの時間がかかる作業である。あの頃は、DOSのバージョンアップも頻繁だったし、ソフトもそれに合わせてバージョンアップがあった。また、今では忘れ去られているが、常駐ソフトが塞ぐメモリーの節約に気を使わなければならないとか、EMSとかMSCDEXだHIMEMだとか、次々にいろいろなものをインストールする必要がでてきた。
また、メモリーの増設や画像メモリーの増設など次々に行わないと、当初高額だったパソコンも満足な動きをしなくなるものだった。
とにかく、ハードディスクから一太郎を動かせるようにし、何かあった時にこちらでの対処が容易にするように3.5インチのフロッピーを外付けで付け、N5200のデータを読めるようにPC9801用の8インチフロッピーを増設したりした。
N88BASICもディスクから立ち上げるようにした。ただ、これらの努力も父からあまり喜ばれなかった。便利になっていることを実感できなかったからである。便利になると、前の全然動かなくなっていた頃のことをすぐ忘れ、動いて当たり前のような感じがある一方、互換性が落ちることへの不満の方が多かったようだ。確か、N88BASICはROMのものとDISKのもので、内部コードが違っていたように記憶している。そのため、プログラムを内部コードでセーブしていると、ディスクベーシックでは読み込めないのだ。
父は、プログラムを打ち直したという。父は具合が悪いのに、そんなことで体調をさらに崩していると母からも大きな非難を浴びた。ASCIIモードでセーブすれば読み込めるのだが、それを説明しても、遠い感じであった。そこで、フロッピーにあるプログラムをすべてASCIIモードにセーブしなおす作業などを引き受けた。週末の大事な時間はこのような作業で大部分潰される日々が続いた。
その頃、木田祐司氏のUBASICを入手し、父に紹介したら、便利だといって使い出した。その後、WINDOWS環境になっても、UBASICは動くようにしてほしいといわれるようになった。
===================================
今日も朝から雨で、一時強い降りとなっている。
おとといまで騒がしかった蝉の鳴き声は、早朝は聞こえなかった。
午前中に雨が上がると、11時40分から蝉は一斉に鳴きだした。
再び、蝉の鳴き声がする夏を感じさせる日が戻ってきた。
最新の画像もっと見る
最近の「日記」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2005年
人気記事