エスのグラフィの講演会(?)スタートしました。
■一人目の方
本日、博士課程を無事終了したという
博士課程にいる間に就職(!?卒業後ずっと院だったらしい)され、顧客理解PJなるものにお勤めの方
アカデミアではなく、ビジネスエスのグラフィを利用するようになり、
そこでの発見を元に、アカデミアとビジネスで求められる者の違いを発表。。。
こういうのも発表として成り立つのか。目から鱗
「どのようにすれば、人への深い理解が可能となるのか」
しかし、ビジネスでは、効率も求められるし
チームで対応するし、そもそも企業の意思があって
研究対象が指定される
そこがびっくりと言うけど。
質問をしてしまった。
就職したのは初らしくて、大学卒業後修士とって白紙に9年いらっしゃったらしい
・・・そうか、異文化交流
頭のいい人がするとこうなるのか
■二人目 この方も教が食い取得。心理学らしい
いいもの作っても売れない時代
アーリ-マジョリティを相手にしなきゃ
ってことでこの10年研究していらっしゃるらしい
エスのグラフィの産業応用事例では、、、
・顧客理解
・サービス評価
・手法開発
⇒で、市場に何か出したい
あと、聞き逃したけど
調査って、社内を驚かせるのに使うらしい
確かに。。。
で、やったこととして、例えば5人の若者のお宅訪問調査とか。
それで学会発表しちゃうらしい
そうか、そういうものか
そうなのか
調査会社の人とかと話していると、
調査っていろんな人がやっている、、ってつい思うけど
そうではない。目的もって調査して、結果こうで、こういう風に使えそう
ってストーリーがたてば、発表に値するのか。。。
認知科学の学者が、エスのグラフィを利用したら、、
って話。
■3人目
ライフヒストリーとして、エスのグラフィと歩んだ日々を紹介してくれるらしい
しょっぱな、大手企業の文系研究所の研究員。。。
結婚してやめたりとしかしたけど、また研究員になっていらっしゃるようで、
すごいなあ
学生時代何してきたんだろう
今の勤務先では、イノベーションを支援する以上自分がやってなきゃだめってことで、
ほぼ全員が、Wワークで
自分の会社をもっているらしい
はたらける美術館、、、知ってる!!?
おおおおおおお
リサーチにどんな意味があるのか
山とある情報から何を拾うのか
これ、、高度。
んーーーーー
エンジニアの会社で、定性調査に懐疑的だったけど、、
the art of innovation
なる本を元に、
デザイン思考という考え方を、政治的政略的に利用
社内でその意義を認めさせたらしい・・・
この方、すごいな
横文字が色々入ってくる。
たぶん、英語での論文読めるレベルだな
あ、、東大大学院でごりごりやってたらしい。東大をさらっと流し
そこで何を学んだのかとか、調査における哲学を熱く語るあたり
すごいな
どんだけエッジが効いていても
「理解される言葉」に落とし込むことが大切
技術開発とサービス改善の違い
サービス改善は、thick & quick(内容は求めらるが、短納期) で、かつ現場の声を経営に届ける(顧客の声という体で)という役割も。
fly on the wall
はえのように静かにそこにいて、改善するのだ
売るためには、、、
理解してもらい、アピールしていくことは大切
しかし、、長い。
なんて熱量の高い方だろうか
色々学び
学んだのに、社内でうまく活用できないのは何故か、ってのを考えているらしい。
組織の関係性の悪さ
企業文化か、個人のリーダーシップか。。
ってことで、
組織開発の1つに
「U理論」ってのがある。本が2~3冊出てる
※デザイン思考と似ているけど、逆向きかも
視座の転換。これを解説してくれている
感じ取る(視座が上がる)をもたらす要素
⇒自分がうすうす感じていたことを、他者にFBされたとき、
みたいなあるあるがたくさん記載されてて、、
頭のいい人って、こういう素朴な話にインスパイアーされるんだなと
(わたしだったら、はいはい、って流しちゃうだろうな)
健在な危機意識と、新しいことに挑戦しようというエネルギー
企業の圧力主義との戦いがテーマらしい
YAHOO+東大中原准教授の本らしい
(ここにも野中先生の推薦の言葉有り)
しかし、話が長居。
でもI先生はまったくせかさない。。すごいなあ。
鷹揚?想定内???
何だろう
しかし、、、
社会学とは違うけど人類学の話って
しっくりくるなあ
■4人目
わが、指導教官。自己紹介から
本日のOさんの修了で二人目の博士課程を出したらしい
へええ
この大学では12年目らしい。
へええ
知らないこともまだまだたくさんある
今回のテーマは、
文化人類学「を」豊かにできないか
らしい。
「を」に『』つけてしまうあたりが、面白い
人類学者は人類学についてよく知っているが、
人類学者以外にどう伝えるのかの知見がない
ってノランの言葉を紹介される。
手厳しい
世の中が複雑化し多様化し、専門特化していく中で
各々の専門領域を超えようとする動きもある
常に行ったり来たり
学問は
脱時間化されており
「時間がなかったのでできませんでした」
というのはない
かつ、学問は個人が報われる世界
会社だと、チームになり個は埋没するし、会社の都合があるけど、、
学問は個人がどこまで取り組むかだから。
へえ
人類学の考えとは、メソドロジイでははなく、マインドセットらしい
手法ではなく、
何を切り取るかの嗅覚だとしたら、、、
「観察する」ことの本質をついたこと
「観察する」視点
それは、どうやって体得できるんだろうな
制約があるからこそのクリエイティブがある
逆に「手続き化しない」
・・・なるほど!
企業で必要なのは
「適度な驚きと適度な納得感」
あ、、これ読んでみたいな
サイロ・エフェクト
高度専門家社会の罠
文化人類学者から転じて、ファイナンシャルタイムズのアメリカ版編集長になった方の本!
とある方の質問:
企業では資金的、時間的制約が多いというけど、
大学は今改革という元、とにかく論文出せ-、院生増やして適度で卒業させろー
みたいな感じで、でもどんどんレベル下がっているし
それでいうと、民間の方が自由があるのでは???
⇒そうか、、、KPI主義って、大学にも来ているのか
そうだよなあ。










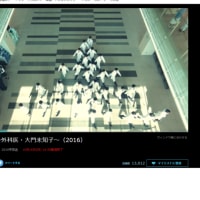


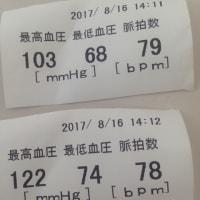


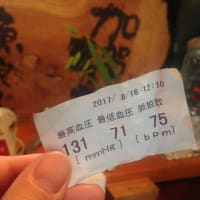



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます