大学院で勉強するにつれ(あまりできてないけど)、自分がすごくバカであること
自分が日ごろいかに勉強をしていないのかを知る。。。
高いレベルの思考、自律、こだわっての仕事…
自分のしょぼさを知る。
----------------------------------------------------------
ゼミを決めた後で、なぜ、ゼミの紹介に出るのかというと
とある後期課程の方が「この大学ってよくわからないことがあるから、説明が聞きたい」
とのこと。。。そういう考え方もあるのかと思って
何もわからずにゼミをゑ段々だなあと今、自分の知ら無すぎることに苦笑
ダメダメだなあ。先生方の研究分野とかなんも知らない。
本当に、、何も知らないで入ってしまって
----------------------------------------------------------
①知識メディア領域
②システム知識領域
↓これ楽しそうだな
小林助教 「経済成長に依拠しない持続可能な社会のための制度設計」
・地域通貨
・サードプレイス(カフェ)
↓何やら、すごく面白そう。。。ああこっちだったかもしれないなあ。。。
吉田武稔教授「システム方法論」
サービスシステム、組織マネジメント(ナレッジマネジメント)
システム論 1+1が2にならない 「部分と全体の関係は分からない」
問題の解決を図るのではなくて、経験論的に、良い方向に持っていく
勉強にいまいち身の入らないAくんを、合コンに連れて行き
勉強熱心なBさんという恋人を作ることで、Aくんも勉強熱心になる的な。。。。
認知心理学 「適応的熟達者」→ 適応的熟達化
脳科学からいうと「長期記憶をいかに増やしていけるのか」がポイント
豊かな経験の繰り返しが大切
暗黙知の哲学から長期記憶の科学へ
「やったこと
やらなかったことを
文書化し
じっくり考える」
→全体的に考えるのが大事!!!
③社会知識領域
伊藤泰信先生 文化人類学、知識社会学、産業・組織エスノグラフィ、医療エスノグラフィ
④サービス領域
21世紀の諸問題を解決するのにはサービスイノベーションが必要
・「満足」を理解しないといけない
・満足を理解するには、多様な問いかけが必要
「これが問題」ってすぐ「how」を重視してしまうと、浅い回答になる。
部分最適レベル。 why what howを広く考える必要がある
いかに情報や知識から価値を共創するのか
↓頑固(気難し)そうに見えて、話していらっしゃる姿は優しそう。。面白くて、ついつい聞いてしまう。
楽しそうに勉強されているのを感じます。
神田先生
情報科学を専門とされてて、最初「社会科学」系の論文を読んだとき
なんでこの論文に価値があるのか、さっぱりだった。
でも、社会科学の先生から「情報科学の論文って何よんでもわからない」と言われ
そこに面白さを感じた。
RQってなんなんだろう?
それをずっと考えています
-----------------------------------------------------










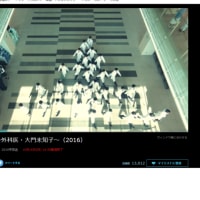


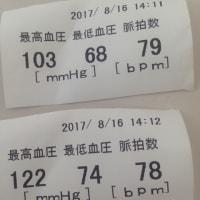


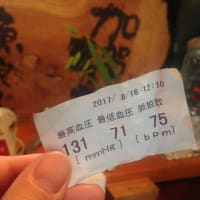



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます