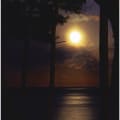『日本書紀』推古天皇 11
十二曰。國司・國造、勿斂百姓。國非二君、民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
十三曰。諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然、得知之日、和如曾識。其以非與聞、勿防公務。
十四曰。群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、人亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悅、才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢、千載以難待一聖。其不得賢聖、何以治國。
十五曰。背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨、有憾必非同、非同則以私妨公、憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。
十六曰。使民以時、古之良典。故、冬月有間以可使民、從春至秋農桑之節、不可使民。其不農何食、不桑何服。
十七曰。夫事不可獨斷、必與衆宜論。少事是輕、不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辨、辭則得理。
≪英訳≫
12th Article:
It is stated: Provincial governors (Kuni no Mikotomochi, 国司) and regional chiefs (Kuni no Miyatsuko, 国造) must not extort taxes from the people (Ōmitakara, 百姓).
A nation cannot have two rulers, nor can its people serve two masters. All the people within the land take the king (Kimi, 天皇) as their sole master. All officials who serve are subjects of the king. How could they dare, for private interests, to collect taxes from the people?
13th Article:
It is stated: All appointed officials must clearly understand their respective duties.
Even if they are absent from their work due to illness or official assignments, when they return to their duties, they must act as if they have been continuously engaged in them. They must not excuse themselves by claiming ignorance of their responsibilities and thereby disrupt public affairs.
14th Article:
It is stated: Ministers (Gunshin, 群臣) and court officials (Momono-tsukasa, 百寮) must not harbor jealousy.
If I envy others, others will surely envy me. The harm caused by envy knows no bounds. When another’s wisdom surpasses one’s own, one feels displeased; when another’s talents exceed one’s own, one feels jealousy.
Thus, it is difficult to encounter a wise person even once in five hundred years or a saintly ruler even once in a thousand years. Without such wise and saintly individuals, how can the nation be governed?
15th Article:
It is stated: To cast aside personal interests and act for the public good is the way of a loyal subject.
When people are driven by selfish motives, resentment inevitably arises. Resentment leads to discord, and discord disrupts harmony. When selfishness obstructs public duties, resentment arises, causing violations of established systems and laws.
As mentioned in the first article, the harmony between superiors and subordinates is rooted in this principle.
16th Article:
It is stated: To employ the people in accordance with the seasons is an excellent teaching of old.
Therefore, during the winter months (from the tenth to the twelfth months), when there is less agricultural work, the people may be employed for public tasks. From spring to autumn, however, they are occupied with farming and sericulture, and must not be called upon. Without farming, what will they eat? Without sericulture, what will they wear?
17th Article:
It is stated: Matters must not be decided through individual judgment alone. They must always be discussed collectively.
For minor issues, consulting everyone is not necessary. However, for significant matters where mistakes must be avoided, discussions with many people are essential. By consulting collectively, the right course of action can be discerned.
≪この英文の和訳≫
第十二条
国司(くにのみこともち)や国造(くにのみやつこ)は、民(たみ)から税をむやみに搾取してはならない。
一つの国に二人の君主があってはならず、民に二人の主君がいてはならない。国土に住むすべての人々は、ただ天皇陛下を主君として仰いでいるのである。
役職に就く者はすべて天皇陛下の臣下である。どうして私的な目的で民から税を取ることなどできようか。
第十三条
任命された役人は、それぞれの職務を明確に理解しておくべきである。
たとえ病気や公務のために一時職務を離れた場合でも、復職した際には以前からその職務に従事していたかのように振る舞い、自分はその業務に無関係だと言って公務を妨げるようなことがあってはならない。
第十四条
群臣(ぐんしん 諸臣)や百寮(もものつかさ)は、互いに嫉妬してはならない。
自分が人を羨(うらや)めば、人もまた自分を羨むであろう。嫉妬がもたらす害悪は限りがない。人の知恵が自分より勝っていると不快に感じ、才能が自分より優れていると妬むのである。
これでは、五百年に一度の賢人に出会い、千年に一度の聖人が現れるのを待つことさえ難しくなる。賢人や聖人を得られなければ、どうして国を治めることができようか。
第十五条
私心を捨て、公のために尽くすことは、臣下としての道である。
すべての人が私心を持つと、必ず他者に恨みを抱かせる。恨みが生じれば、必ず人々の心が乱れる。人々の心が乱れることは、私利私欲によって公務を妨害する原因となる。
また、恨みが募れば規則を破り、法を犯すことにもつながる。
第一条において、上下が調和し、協力し合うようにと述べたのも、このような気持ちに基づくものである。
第十六条
民を使役する際は、時節を考慮するべきである、というのは古来からの良き教えである。
そのため、冬の月(十月から十二月)は農作業が少なく暇があるので、民を使役してもよい。しかし、春から秋にかけては農耕や養蚕(ようさん)の季節であるため、民を使役してはならない。
農業をしなければ何を食べればよいのか。養蚕をしなければ何を着ればよいのか。
第十七条
物事を独断で決めるべきではなく、必ず大勢で議論するようにせよ。
些細なことについては、必ずしも全員で相談する必要はない。しかし、重要な事柄においては誤りを避けなければならない。
多くの者と議論すれば、道理にかなった正しい判断が得られるのである。
令和6年12月29日(日) 2024